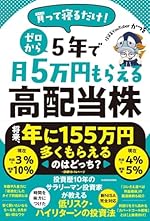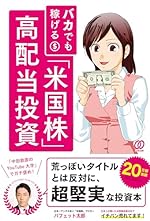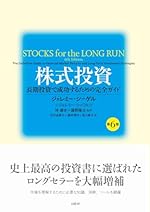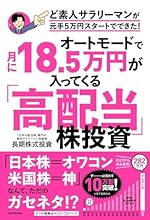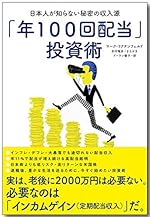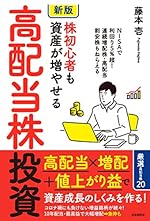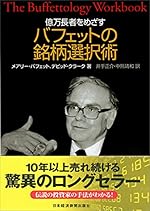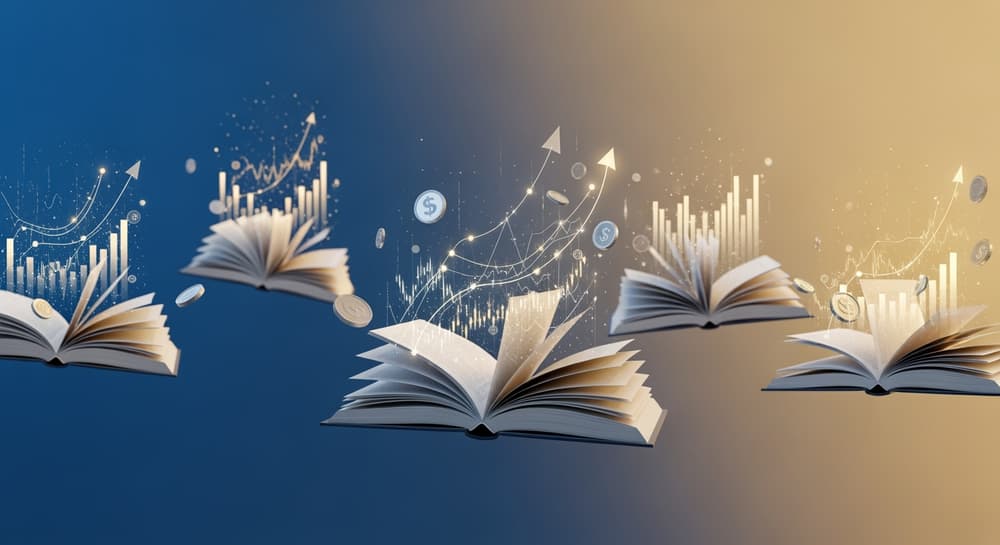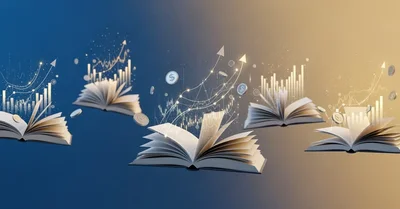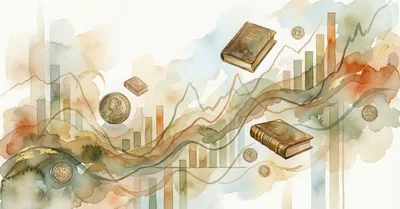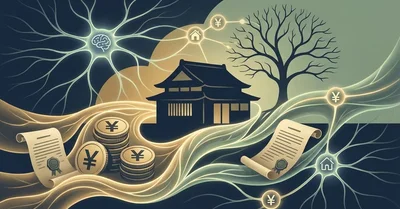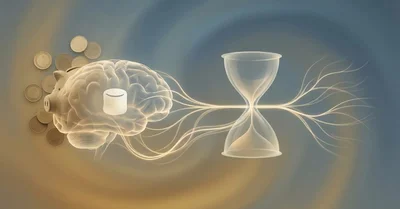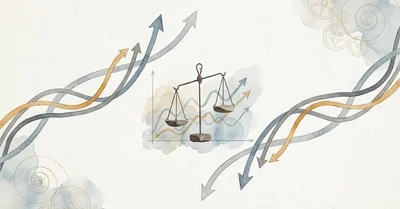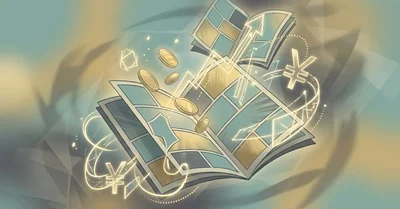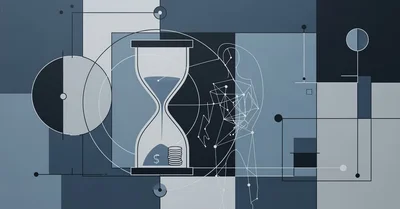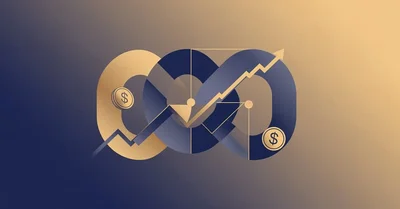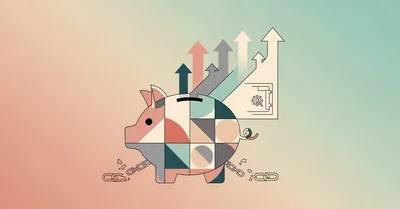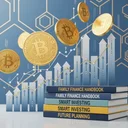投資本おすすめ2025決定版!初心者でも月5万円の配当金を作る必読書10選

「月5万円の配当金があれば、子供の習い事代がまかなえるのに…」
37歳になった今、切実にそう思います。実は、配当金投資は私たち30代後半の会社員にこそ向いている投資法なんです。なぜなら、まとまった資金を作れる年齢でありながら、まだ複利効果を最大限活用できる時間が残されているから。
驚くべきことに、日本には25年以上連続で増配している企業が花王1社しかないのに対し、アメリカには100社以上も存在するんです。この事実を知ったとき、私は配当金投資の本当の可能性に気づきました。
今回は、年間200冊以上読む私が厳選した、配当金投資で月5万円を実現するための必読書10冊を紹介します。特に新NISA制度を活用した戦略や、必要投資額の現実的な試算など、実践的な内容にフォーカスしました。
なぜ今、配当金投資なのか?37歳編集長の本音
私が配当金投資に注目し始めたのは、長男が生まれてからでした。将来の教育費、住宅ローン、そして自分たちの老後資金…考えることが山積みです。
でも、配当金投資には他の投資法にない大きな魅力があります。それは「見える化された不労所得」という点です。株価の上下に一喜一憂せず、定期的に入ってくる配当金は精神的な安定をもたらしてくれます。
実際、配当利回り3%で2,000万円を投資すれば年間60万円、つまり月5万円の配当収入が得られる計算になります。これは決して夢物語ではありません。
月5万円の配当金を実現する投資本10選
1. 買って寝るだけ!ゼロから5年で月5万円もらえる高配当株
配当成長率に着目した新しい投資戦略。新NISA活用で最短で月5万円の配当収入を実現する具体的な方法を解説。
¥1,760(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
まず紹介したいのが、2025年2月に発売された話題の新刊です。著者のかつを氏は、現役サラリーマンでありながら投資YouTuberとして4万人以上の登録者を持つ実践派。
この本の最大の特徴は「高配当」ではなく「配当成長率」に着目している点です。単に今の配当利回りが高い銘柄を買うのではなく、将来的に配当金が増えていく可能性の高い企業を選ぶ。この視点の転換が、長期的な資産形成の鍵となります。
新NISAの活用法も詳しく解説されており、年間投資枠240万円を最大限活用して、最短で月5万円の配当収入を作る道筋が具体的に示されています。私も実際にこの戦略で銘柄選定を始めましたが、従来の高配当株投資とは違った魅力を感じています。
2. 本当の自由を手に入れる お金の大学
両@リベ大学長の『お金の大学』は、もはや投資入門書の定番と言えるでしょう。累計140万部を突破し、私の周りでも「これだけは読んでおけ」と言われる一冊です。
配当金投資については「真の不労所得」として詳しく解説されており、日本株と米国株の両方について、銘柄選定の基準から実際のポートフォリオ構築まで学べます。特に印象的だったのは、「生活費の一部を配当金でまかなう」という現実的な目標設定です。
私はこの本を読んで、まず固定費の見直しから始めました。浮いたお金を投資に回すという基本戦略は、37歳の今からでも遅くありません。むしろ、収入が安定している今だからこそ実践しやすいと感じています。
3. バカでも稼げる「米国株」高配当投資
英語力ゼロ、投資知識ゼロでもOK。10万円から始める米国株高配当投資の実践ガイド。
¥1,650(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
バフェット太郎氏の代表作です。タイトルは挑発的ですが、内容は極めて真面目で実践的。米国株投資を「スタバでフラペチーノを飲むくらい簡単」と表現し、心理的ハードルを下げてくれます。
実際、私も最初は米国株投資に抵抗がありました。英語ができないし、為替リスクも心配でした。でも、この本を読んで考えが変わりました。コカ・コーラやジョンソン・エンド・ジョンソンといった、25年以上連続増配している企業(配当貴族)への投資なら、日本株より安定している場合も多いんです。
著者自身、300万円から始めて現在5,000万円の資産を築いており、その道筋が具体的に示されています。月3分のチェックで年間10%のリターンという実績も魅力的です。
4. 株式投資 第6版
ウォートン・スクール教授ジェレミー・シーゲルの最新改訂版。200年以上のデータ分析で長期投資と配当再投資の優位性を検証した決定版。
¥4,180(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
ジェレミー・シーゲル教授の名著です。少し専門的ですが、配当金投資の理論的裏付けを知りたい方には必読書です。
過去200年のデータ分析から、配当再投資が長期的に最も高いリターンをもたらすことが実証されています。特に「配当利回りの高い銘柄は、長期的に市場平均を上回るパフォーマンスを示す」という結論は、私の投資戦略の根幹となっています。
学術的な内容も多いですが、実践に活かせる知識が満載です。私はこの本を読んで、配当金を使わずに再投資することの重要性を理解しました。
5. オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資
長期株式投資氏の実践書です。月18.5万円という具体的な金額設定が印象的ですが、これは年間222万円、配当利回り3.7%で計算すると約6,000万円の投資が必要になります。
一見すると非現実的に思えますが、本書では段階的にこの目標に到達する道筋が示されています。特に「ダウの犬戦略」を日本株に応用した手法は、銘柄選定で悩む初心者にとって有益です。
私も実際にこの戦略を試してみましたが、機械的に銘柄を選ぶことで感情的な判断を排除できるのが良い点でした。
6. 年100回配当投資術
日本株とJ-REITを組み合わせて、毎月配当金を受け取る実践的な投資戦略を解説。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
これは少しユニークな視点の本です。日本株の配当は年2回が基本ですが、J-REITやインフラファンドを組み合わせることで、ほぼ毎週配当金を受け取れるポートフォリオを構築する方法が解説されています。
配当金の受取頻度が上がることで、モチベーション維持にもつながります。私も実際にJ-REITを組み入れてみましたが、定期的に入ってくる分配金は精神的な安定感をもたらしてくれました。
7. 高配当株投資術
日本株に特化した高配当投資の実践書。財務分析から銘柄選定まで詳しく解説。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
日本株に特化した高配当投資の実践書です。米国株と違い、日本株には株主優待という独自の魅力もあります。配当金と株主優待を組み合わせることで、実質的な利回りを高める方法が詳しく解説されています。
私の場合、家族で使える優待(外食チェーンなど)を中心に選んでいます。妻も「優待券が届くと投資を実感できる」と喜んでいます。
8. インデックス投資は勝者のゲーム
高配当ETFを含む、インデックス投資の決定版。リスクを抑えながら配当収入を得る方法。
¥3,080(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
ジョン・C・ボーグルによる名著です。個別株ではなく、高配当ETFへの投資を推奨しています。VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)やSPYD(SPDR ポートフォリオS&P 500高配当株式ETF)など、分散投資しながら配当収入を得られる方法が解説されています。
私も個別株選定に自信がない部分は、高配当ETFでカバーしています。手数料も低く、自動的に分散投資できるのが魅力です。
9. 配当成長株投資のすすめ
配当金が年々増える企業に投資する戦略。複利効果を最大限活用する方法を解説。
¥3,080(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
マーク・リクテンフェルド氏の著書を翻訳したものです。単に高配当な銘柄ではなく、配当金が年々増えていく「配当成長株」に投資する戦略が詳しく解説されています。
10年、20年という長期スパンで見ると、配当成長株への投資は驚くべきリターンをもたらします。私も実際に過去10年間の配当成長率をチェックして銘柄選定に活用しています。
10. 億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術
ウォーレン・バフェットの投資哲学を学ぶ。永続的な競争優位を持つ企業の見極め方。
¥1,870(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
最後は、投資の神様ウォーレン・バフェットの投資哲学を学べる一冊です。バフェットは配当金投資家ではありませんが、「永続的な競争優位を持つ企業」を選ぶ視点は、高配当株投資にも活かせます。
コカ・コーラやアメリカン・エキスプレスなど、バフェットが投資している企業の多くは安定配当を続けています。この本を読むことで、単なる高配当ではなく、長期的に配当を維持・成長させられる企業を見極める目が養われます。
月5万円の配当金に必要な投資額の現実
ここで現実的な話をしましょう。月5万円(年間60万円)の配当金を得るために必要な投資額は、配当利回りによって大きく変わります。
| 配当利回り | 必要投資額 | 月々の積立額(10年) |
|---|---|---|
| 3% | 2,000万円 | 約14万円 |
| 4% | 1,500万円 | 約10.5万円 |
| 5% | 1,200万円 | 約8.4万円 |
正直、厳しい数字だと思います。でも、諦める必要はありません。私が実践している現実的なアプローチは以下の通りです。
まず、段階的な目標設定が重要です。いきなり月5万円を目指すのではなく、最初は月1万円(年間12万円)から始める。配当利回り4%なら300万円の投資で達成できます。
次に、配当再投資による複利効果を活用します。受け取った配当金を使わずに再投資することで、雪だるま式に資産が増えていきます。実際、私も最初の3年間は配当金に手を付けず、全額再投資しています。
新NISAの活用も欠かせません。年間投資枠360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)を最大限活用すれば、配当金にかかる税金(通常20.315%)がゼロになります。これは実質的に利回りが25%アップするのと同じ効果があります。新NISAの詳しい活用法については、新NISA初心者向け完全ガイドでも解説しています。
私が実践している配当金投資の3つのルール
37歳から配当金投資を始めて気づいたことがあります。それは、単に本を読むだけでは成功しないということ。実践する中で自分なりのルールを作ることが大切です。
ルール1:生活防衛資金を確保してから投資する
私の場合、生活費6ヶ月分(約180万円)を現金で確保してから投資を始めました。子供がいる家庭では、急な出費も多いですからね。この安心感があるからこそ、株価の変動に一喜一憂せずに済みます。
ルール2:配当利回り4%以上にこだわらない
高配当株投資の本を読むと「利回り4%以上」という基準をよく見かけます。でも、私は3%台でも財務が健全で、増配傾向にある企業なら投資対象にしています。例えば、花王は現在の配当利回りは2.5%程度ですが、35年連続増配という実績があります。
ルール3:四半期ごとに見直し、年1回リバランス
毎日株価をチェックする必要はありませんが、四半期決算のタイミングで保有銘柄の業績を確認しています。そして年1回、ポートフォリオのリバランスを実施。これにより、特定の銘柄に偏りすぎるリスクを避けています。
配当金投資のメリット・デメリット
実際に配当金投資を始めて感じたメリットとデメリットを正直にお伝えします。
メリット
まず、精神的な安定感が得られます。株価が下落しても、配当金は比較的安定して入ってきます。実際、2024年の調整局面でも、私の配当収入はほぼ変わりませんでした。
次に、投資の成果が見える化されることです。含み益は「絵に描いた餅」ですが、配当金は実際に口座に入ってきます。これが投資継続のモチベーションになります。
最後に、老後の年金代わりになることです。65歳までに月10万円の配当収入を作れれば、年金と合わせて豊かな老後が送れます。
デメリット
一方で、即効性がないことは覚悟が必要です。月5万円の配当収入を作るには、多額の投資と長い時間が必要です。
また、減配リスクも無視できません。2020年のコロナショックでは、多くの企業が減配や無配に転じました。私も保有していた航空株で痛い目に遭いました。投資の失敗を避けるためには、投資の恐怖を克服する本で紹介している心理的な準備も重要です。
さらに、税金の問題もあります。日本株の配当金には20.315%の税金がかかります(新NISA枠を除く)。これを考慮した実質利回りで計算する必要があります。
まとめ:37歳から始める配当金投資の第一歩
月5万円の配当金という目標は、決して簡単ではありません。でも、不可能でもありません。重要なのは、今すぐ始めることです。
私も37歳で始めて、まだ道半ばです。でも、毎月少しずつ入ってくる配当金を見ると、確実に前進していることを実感できます。子供の教育費や老後の不安も、少しずつ和らいできました。
今回紹介した10冊の中から、まずは1冊手に取ってみてください。特に『買って寝るだけ!ゼロから5年で月5万円もらえる高配当株』は、新NISA時代の配当金投資の教科書として最適です。
配当金投資は、時間を味方につける投資法です。37歳の今から始めれば、50歳で月5万円、60歳で月10万円の配当収入も夢ではありません。配当金投資の基礎から学びたい方は、高配当株投資の本も参考になります。また、お金の勉強を基礎から始めたい方にはお金の勉強本完全ガイドもおすすめです。
一緒に、配当金による経済的自由を目指しましょう。
新NISA時代の配当金投資の決定版。配当成長率に着目した新しい投資戦略で、最短で月5万円の配当収入を実現する方法を解説。
¥1,760(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp