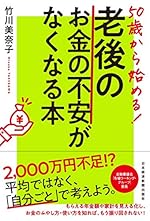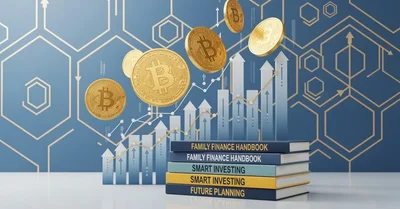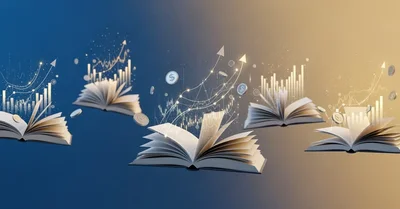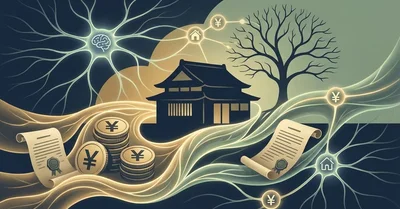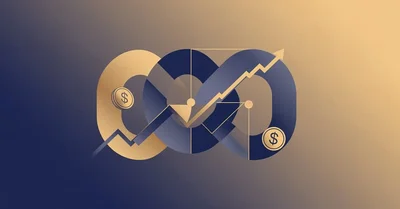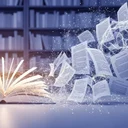老後不安でたまらない人の62.8%が知らない!『50歳から始める』資産形成の真実

内閣府の最新調査で驚くべき事実が判明しました。日本人の62.8%が「老後の生活設計に不安を感じている」と回答。さらに衝撃的なのは、その多くが具体的な対策を取っていないという現実です。
私も38歳で2児の父として、正直なところ老後への不安は尽きません。住宅ローンはあと20年、長女の教育費もこれから本格化。でも、だからこそ今回ご紹介する『50歳から始める!老後のお金の不安がなくなる本』に出会えたことは幸運でした。
著者の竹川美奈子氏は、ファイナンシャルジャーナリストとして長年活動し、「老後資金の見える化」という革新的なアプローチを提唱しています。本書では、漠然とした不安を具体的な数字に変え、実践可能な解決策を示してくれます。
著者: 竹川美奈子
老後資金の「見える化」で不安を解消。公的年金制度を理解し、新NISAやiDeCoを効率的に活用する方法を、ファイナンシャルジャーナリストが分かりやすく解説。
¥1,400(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
「老後2000万円問題」の真実——実は個人差が大きかった
金融庁の報告書が発端となった「老後2000万円問題」。メディアは大騒ぎしましたが、実はこの数字には大きな誤解があります。
報告書をよく読むと、「高齢夫婦世帯の平均値から算出したもので、個人差が大きい」と明記されています。つまり、2000万円という数字は万人に当てはまるわけではないのです。
実際に私が計算してみたところ、我が家の場合は以下のような結果になりました:
- 現在の生活費:月35万円(住宅ローン含む)
- 退職後の予想生活費:月25万円(ローン完済後)
- 予想年金受給額:月22万円(夫婦合計)
- 不足額:月3万円
この計算だと、65歳から90歳までの25年間で必要な金額は900万円。2000万円とは大きく異なります。
データが示す老後不安の3つの真因
竹川氏は、老後不安の真因を3つに整理しています。これはWHO-SAGE研究(2020年)の結果とも一致します。
1. お金の不安:医療・介護費用が最大の懸念
内閣府の高齢社会白書によると、高齢者の経済的不安の内訳は:
- 医療・介護費用の負担:30.8%
- 施設入居費用:26.0%
- 生活費不足:25.8%
医療・介護費用が最も大きな不安要因となっています。しかし、公的制度を理解すれば、この不安はかなり軽減できます。
2. 健康の不安:健康寿命を延ばす科学的方法
日本全国10年パネル調査(2017年)によると、退職後に余暇時間の身体活動が増加し、健康行動にポジティブな変化が起きることが実証されています。
3. 孤独の不安:社会的つながりの重要性
WHO報告(2023年)では、高齢者の約1/4が社会的孤立を経験していることが明らかになりました。経済的な準備だけでなく、人間関係の構築も重要です。
50代から始める!今すぐできる3つの資産形成術
竹川氏の提案する資産形成術を、私なりにアレンジして実践しています。効果で考えると、以下の3つが最も重要です。
なお、お金の勉強を始めたい方は、年代別・レベル別に厳選されたお金の勉強本ガイドも参考にしてください。20代から40代まで、それぞれの年代に最適な本が紹介されています。
1. 新NISAで月10万円の積立投資
2024年から始まった新NISAは、年間投資枠360万円、生涯非課税限度額1,800万円という画期的な制度です。
私の実践例:
- つみたて投資枠:月10万円(年120万円)
- 投資先:全世界株式インデックスファンド
- 期待リターン:年5%と仮定
50歳から65歳までの15年間続けると、元本1,800万円が約2,700万円に成長する計算です(複利効果)。
2. iDeCoで節税しながら老後資金作り
iDeCoの最大のメリットは、掛金が全額所得控除になることです。
私の場合(課税所得500万円):
- 月額掛金:2.3万円(企業型DCがない会社員の上限)
- 年間節税額:約8.3万円(所得税・住民税合計)
- 15年間の節税額:約124万円
この節税分を新NISAに回せば、さらに資産形成が加速します。
3. 「ねんきん定期便」を活用した見える化
多くの人が見落としているのが、公的年金の正確な把握です。
実践ステップ:
- ねんきん定期便で現在の加入記録を確認
- 「ねんきんネット」で将来の受給額をシミュレーション
- 不足額を具体的に計算
- 必要な積立額を逆算
急激な退職vs段階的退職——メンタルヘルスを守る選択
退職経路と精神的健康に関する研究(Mizuochi, 2023)によると、退職の仕方によってメンタルヘルスへの影響が大きく異なることが判明しています。
- 急激な退職:身体的制限を持ちやすいが、うつ病にはなりにくい
- 段階的退職:身体的制限は少ないが、うつ病になりやすい
私は段階的退職を選択する予定ですが、メンタルヘルスのケアも同時に計画しています。具体的には、退職前から趣味のコミュニティに参加し、社会的つながりを維持する準備を始めました。
知らないと損する公的支援制度3選
竹川氏は、意外と知られていない公的支援制度も紹介しています。
1. 高額療養費制度
医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。70歳以上の一般的な所得の方なら、月額上限は5.7万円程度。
2. 高額介護サービス費制度
介護費用にも同様の上限があり、所得に応じて月額1.5万円~4.4万円が上限となります。
3. 国民年金の任意加入制度
60歳時点で受給資格期間が不足している場合や、満額受給に満たない場合は、65歳まで任意加入できます。
実践した結果:3ヶ月で起きた意外な変化
本書の内容を実践して3ヶ月。数字以上に大きな変化がありました。
精神的な変化
漠然とした不安が、具体的な目標に変わりました。「老後が不安」から「月10万円の積立を15年続ける」という明確な行動指針ができたことで、気持ちが前向きになりました。
家族との会話の変化
妻とお金の話をオープンにできるようになりました。以前は「老後が心配」で終わっていた会話が、「新NISAの配分どうする?」「iDeCoの受け取り方は?」といった建設的な内容に変わりました。
同時に、子供たちへの金融教育の重要性も痛感しています。私が実践している7歳から始める投資マインド育成法では、複利の概念を楽しく学ぶ方法を紹介していますので、子育て世代の方はぜひ参考にしてください。
健康意識の向上
富と幸福度の11年パネル分析(2024)が示すように、富の蓄積と幸福度の関係は非線形です。お金だけでなく、健康への投資も始めました。週3回のジョギングと、月1回のサウナが新しい習慣になっています。
よくある質問:読者から寄せられた疑問
Q1. 50代では遅すぎませんか?
データによると、50代から始めても十分間に合います。新NISAで15年間積立投資すれば、複利効果で大きな資産を作れます。重要なのは「今すぐ始める」ことです。
Q2. 投資は怖くないですか?
私も最初は同じ不安を持っていました。しかし、長期・分散・積立という基本を守れば、リスクは大幅に軽減できます。まずは少額から始めることをお勧めします。
Q3. 独身の場合はどうすればいいですか?
竹川氏は独身の方向けのアドバイスも充実させています。特に重要なのは、社会的つながりの構築と、任意後見制度の活用です。
まとめ:今すぐ始められる老後不安解消アクション
老後への不安は、誰もが抱える自然な感情です。しかし、その不安を放置していても解決しません。重要なのは、具体的な行動を起こすことです。
今日から始められる3つのアクション:
- ねんきん定期便で年金受給額を確認する
- 新NISA口座を開設する(まだの方)
- 月々の積立額を決めて、自動引き落としを設定する
竹川美奈子氏の『50歳から始める!老後のお金の不安がなくなる本』は、これらの行動を具体的にサポートしてくれる実践的なガイドブックです。漠然とした不安を抱えているなら、まずはこの本を手に取ってみてください。
私のように、老後への不安が具体的な目標と行動に変わるはずです。データが示すように、50代からでも決して遅くありません。大切なのは、今この瞬間から始めることです。
著者: 竹川美奈子
老後資金の「見える化」で不安を解消。公的年金制度を理解し、新NISAやiDeCoを効率的に活用する方法を、ファイナンシャルジャーナリストが分かりやすく解説。50代からでも間に合う資産形成の決定版。
¥1,400(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp