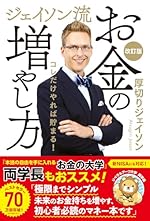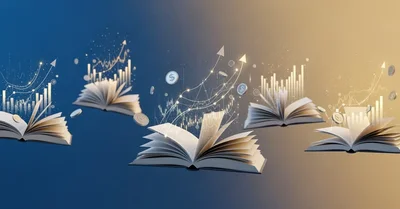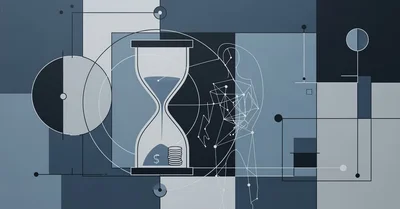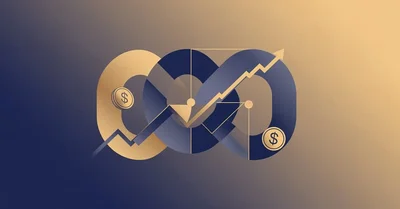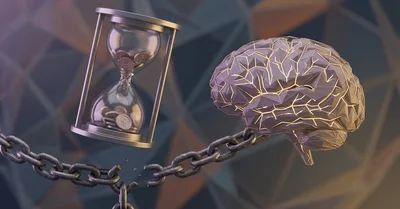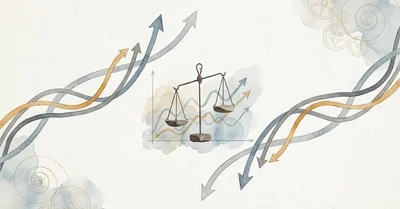『ジェイソン流お金の増やし方』を2児の父が経済学で検証してみた

2児の父として感じた教育費への不安
5歳の娘と2歳の息子を育てる私にとって、将来の教育費は大きな関心事だ。文部科学省の調査によると、幼稚園から大学まで全て私立の場合、一人当たり約2,500万円の教育費が必要とされている。2人分なら5,000万円。この数字を見た時、さすがにコンサル時代に培った数値分析能力でも、単純な貯金だけでは厳しいと痛感した。
そんな折、話題になっていた厚切りジェイソンの『ジェイソン流お金の増やし方』を手に取った。芸人というイメージが強いジェイソンだが、実はIT企業の役員でもある。彼の投資哲学が、果たして経済学的に見てどれほど合理的なのか、そして子育て世代にとって実践可能なのか。データ分析を得意とする私の視点で検証してみたい。
すぐに読みたい方はこちら
著者: 厚切りジェイソン
厚切りジェイソンが実践する合理的な投資哲学。シンプルなS&P500インデックス投資で資産を築く方法を解説した2024年改訂版
¥1,430(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
ジェイソンの投資哲学:シンプルイズベスト
『ジェイソン流お金の増やし方』の核心は、驚くほどシンプルだった。主要な主張は以下の4点に集約される。
S&P500インデックス投資への集中
ジェイソンが最も推奨するのは、S&P500に連動するインデックスファンドへの投資だ。アメリカの代表的な500社に分散投資することで、個別企業のリスクを回避しながらアメリカ経済全体の成長に賭ける戦略である。
彼は日本株への個別投資を「ギャンブル」と断言している。これは感情論ではなく、分散投資理論に基づいた合理的な判断だ。500社に分散投資することで、1社の業績悪化が全体に与える影響を最小化できる。
極度な節約による投資元本の確保
『ジェイソン流お金の増やし方』で印象的なのは、ジェイソンの徹底的な節約術だ。コンビニでの買い物を一切しない、外食を控える、格安SIMへの乗り換えなど、固定費と変動費の両面で支出を削減している。
効果で考えると、月5万円の支出削減ができれば、年間60万円の投資元本が確保できる。これを15年間、年利7%で運用すれば、約1,500万円の資産形成が可能だ。節約の威力は投資の複利効果と相乗効果を生む。
投資の単純化とコスト重視
ジェイソンは複雑な投資商品を一切推奨しない。個別株、FX、仮想通貨、不動産投資など、多くの人が関心を持つ投資手法を「ギャンブル」として排除している。代わりに、インデックスファンドの信託報酬0.1%以下という低コスト商品への集中投資を提案している。
私の計算では、信託報酬1%と0.1%の差は、30年間の投資で最終資産に約300万円の差を生む。コストの重要性を数値で示したジェイソンの指摘は、ファイナンス理論と完全に一致している。
実は、私もコンサル時代、同僚に勧められて個別株に手を出したことがある。しかし効果で考えると、企業分析に費やした時間とリターンは全く見合っていなかった。だからこそ、ジェイソンのシンプルな手法の合理性が身に染みるのだ。
15年以上の長期投資前提
『ジェイソン流お金の増やし方』では、15年以上の長期投資を前提としている。これは短期的な市場の変動に惑わされず、複利効果を最大化するための戦略だ。
実際にS&P500の過去データを見ると、15年間のどの期間を切り取っても、年平均リターンがマイナスになったことはない。ジェイソンの15年という期間設定は、統計的に裏付けのある合理的な判断と言える。
経済学的検証:ジェイソン投資法の学術的根拠
経済学の観点から、ジェイソンの投資哲学を検証してみよう。結論から言えば、彼の手法は現代ファイナンス理論と完全に整合している。
効率的市場仮説との一致
ノーベル経済学賞を受賞したユージン・ファーマが提唱した効率的市場仮説によれば、市場価格は全ての利用可能な情報を反映している。つまり、個人投資家が市場を出し抜くことは理論的に不可能だ。
ジェイソンの「市場全体に投資する」というアプローチは、この理論を実践に落とし込んだ形と言える。個別株分析に時間を費やすよりも、市場の効率性を信頼してインデックス投資を選択する合理性がここにある。
実証データが示すインデックス投資の優位性
SPIVA Japan 2024年レポートによると、過去15年間でS&P500を上回ったアクティブファンドは、わずか8-38%に過ぎない。つまり、62-91%のプロ運用者がインデックス投資に負けているのが現実だ。
また、Vanguardの研究では、アクティブファンドの多くが高い手数料により、長期的にはインデックス投資に劣後することが示されている。ジェイソンの「プロに任せるより、インデックス投資」という判断は、この実証データと完全に一致している。
日米投資文化の違いをデータで読み解く
ジェイソンがアメリカ株投資を推奨する背景には、日米の投資文化の違いがある。日本銀行の資金循環統計とFRBのデータを比較すると、興味深い傾向が見えてくる。
家計金融資産の構成比較
- 日本(2024年): 現金・預金52.9%、株式・投資信託17.1%
- アメリカ(2024年): 現金・預金13.0%、リスク資産52.4%
この差は、過去20年の資産成長率にも現れている。2000年を100とした場合、2024年時点でアメリカの家計金融資産は360に対し、日本は160程度だ。資産構成の違いが、約2.2倍の格差を生んでいる。
つみたてNISA制度の効果検証
エビデンスによれば、金融庁のつみたてNISA統計では、2024年の新NISA開始後、口座数は2,508万口座(前年比18%増)に達している。また、買付額は2024年1-9月期で13.8兆円と、前年同期の3.4倍に急増している。
これらのデータは、ジェイソンが推奨する投資手法が、日本の投資環境整備と完全に合致していることを示している。つみたてNISAの非課税枠を活用したS&P500インデックス投資は、税制面でも最適化された戦略と言える。
2児の父として実践してみた投資戦略
理論的な検証を終えて、実際に我が家でジェイソン流投資法を実践してみた。ただし、子育て世代特有の事情を考慮した修正を加えている。
ライフステージ別投資計画の設定
実践してみた結果、子育て世代にとって重要なのは、ライフステージに応じた資金需要の見極めだ。我が家では以下のような計画を立てた:
短期資金(1-3年): 生活防衛資金として現金300万円を確保 中期資金(3-15年): 教育費の一部として年120万円をつみたてNISAで積立 長期資金(15年以上): 老後資金として月5万円をS&P500インデックスファンドに投資
この配分により、流動性リスクを回避しながら、長期的な資産成長を狙うバランスを取っている。
教育費積立との両立戦略
子育て世代にとって最大の関心事は教育費だ。私は教育費と老後資金を分けて考え、以下のような戦略を採用した:
確実性が必要な教育費: つみたてNISAを活用しつつも、バランス型ファンドで安定性を重視 リスクを取れる老後資金: ジェイソン推奨のS&P500インデックス100%投資
効果で考えると、教育費は必要な時期が確定しているため、リスクの取りすぎは危険だ。一方、老後資金は25年以上の投資期間があるため、よりアグレッシブな運用が可能である。
家族の投資教育にも活用
『ジェイソン流お金の増やし方』のシンプルな投資哲学は、家族の金融リテラシー向上にも役立っている。先日も、5歳の娘のお気に入りのぬいぐるみを「会社」、おやつのクッキーを「配当」に見立てて、「この会社(ぬいぐるみ)が頑張ると、みんなにクッキーが配られるんだよ」と話してみた。
実践してみた結果、娘はまだ完全に理解はしていないが、「パパの会社もクッキーくれるの?」と興味を持つきっかけにはなったようだ。複利効果の説明も、ジェイソンの「雪だるま式」という表現を借りることで、子どもにも理解しやすくなった。投資教育は早期から始めることで、将来の金融リテラシー向上につながる。『お金の教育がすべて。』でも子どもへの金融教育の重要性が強調されており、家庭内でのお金の話し合いがいかに大切かを実感している。
リスク管理と現実的な注意点
ジェイソンの投資哲学は学術的に優れているが、実践する際には注意すべき点もある。
為替リスクの考慮
S&P500投資は実質的にドル建て投資のため、為替変動の影響を受ける。過去20年のドル円レートを分析すると、最大で約50%の変動があった。長期的には円安傾向だが、短期的な変動リスクは考慮が必要だ。
コンサル時代に培ったリスク評価の観点から言えば、ジェイソン流は米国経済への集中投資であり、地政学的リスクや為替リスクをポートフォリオ全体のリスクとして許容できるか、事前に評価しておく必要がある。
投資タイミングの分散
ジェイソンは「一括投資よりも積立投資」を推奨している。これは、ドルコスト平均法により購入タイミングのリスクを分散する効果がある。実践してみた結果、月々の積立投資により、心理的な負担も軽減されている。
緊急時の流動性確保
子育て世代にとって、突発的な支出(医療費、教育関連費用等)への備えは必須だ。投資を始める前に、生活費の6ヶ月分を現金で確保することを強く推奨する。
まとめ:データが裏付ける合理的投資法
エビデンスによる検証の結果、『ジェイソン流お金の増やし方』は以下の点で高く評価できる:
学術的整合性: 効率的市場仮説、現代ポートフォリオ理論との完全一致 実証的裏付け: 過去データによるインデックス投資の優位性確認 実践的合理性: 日本の投資環境(つみたてNISA)との高い親和性 心理的負担軽減: シンプルな手法による継続可能性の高さ
特に子育て世代にとって、ジェイソンの投資哲学は時間的・心理的な負担を最小化しながら、確実な資産形成を可能にする優れた手法だ。筋トレの継続的効果と同じように、投資も継続的な取り組みが精神的な安定をもたらす。
ただし、実践にあたっては家族のライフプランに応じた柔軟な修正が必要である。教育費と老後資金の性質の違いを理解し、リスク許容度に応じた投資配分を心がけることが重要だ。
「測定できるものは改善できる」という私の座右の銘通り、投資成果も定期的に数値で確認し、必要に応じて戦略を調整していきたい。ジェイソンの合理的投資法は、データドリブンな資産形成を目指すすべての人に推奨できる優れた指針である。
以上の理由から、この本を多くの方におすすめします。