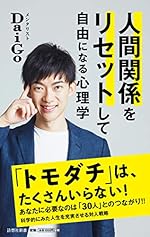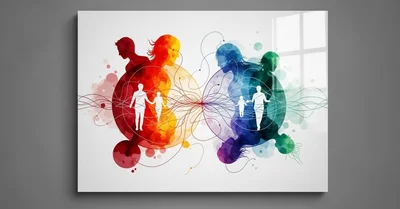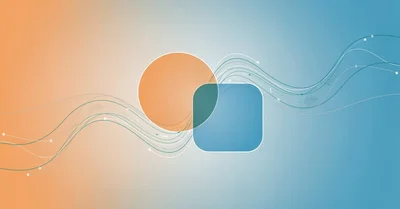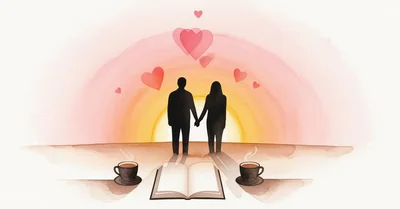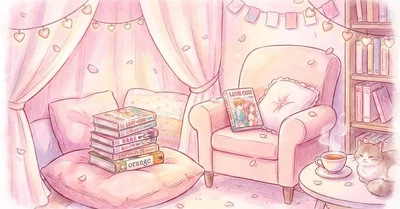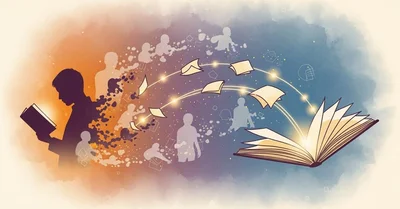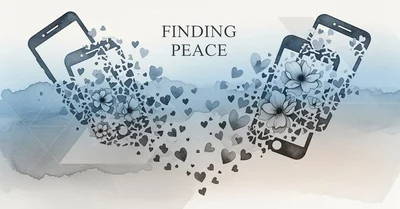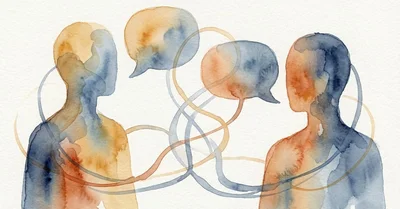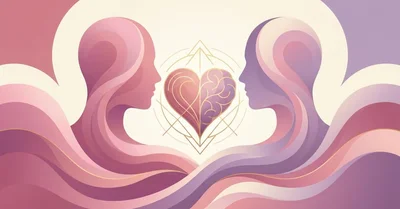職場の人間関係に疲れた28歳が実践!リセット心理学で見つけた3つの境界線
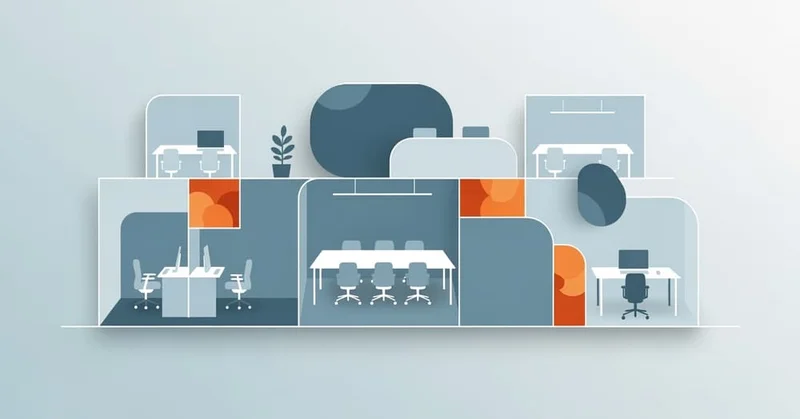
先週の月曜日、出社したくない気持ちがピークに達しました。
原因は明確です。先輩からの「これくらい察してよ」という言葉と、同僚の愚痴大会への参加を断ったことで感じる微妙な空気。フリーランスになって2年、いろんな職場を経験してきましたが、どこに行っても人間関係の悩みはついてきます。
厚生労働省の最新調査によると、82.7%の労働者が職場でストレスを感じているというデータが出ています。私だけじゃないんだ、と少し安心しつつ、このままじゃいけないと思い手に取ったのが『人間関係をリセットして自由になる心理学』でした。
職場の人間関係に疲れた人へ。メンタリストDaiGoが科学的根拠に基づいて教える、適度な距離感を保ちながら自由に生きる方法。
¥1,320(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
職場の人間関係で82.7%が感じる「疲れた」の正体
なぜ私たちは職場の人間関係に疲れるのか
28歳になって気づいたことがあります。学生時代と違って、職場の人間関係って「選べない」んですよね。
厚生労働省のデータを見ると、正社員の42.9%が「仕事の失敗・責任」をストレス要因として挙げていますが、これって結局、失敗した時の周りの目が怖いってことなんです。実際、私も締切に遅れた時、上司の顔より同僚たちの視線の方が辛かったです。
『人間関係をリセットして自由になる心理学』では、この疲れの正体を「他者への過度な期待と、自分への過小評価の組み合わせ」だと分析しています。確かに、「先輩なら分かってくれるはず」「同僚とは仲良くしなきゃ」という期待が、裏切られた時のダメージを大きくしているんですよね。
孤立を恐れる心理の裏側
職場で孤立することを恐れる気持ち、めちゃくちゃ分かります。ランチタイムに一人でいることの居心地の悪さ、グループチャットから外されているかもという不安…。
でも、DaiGoさんは興味深いデータを紹介しています。イギリスの研究によると、職場で深い友人関係を築いている人は全体の30%程度しかいないそうです。つまり、7割の人は表面的な関係で十分やっていけているということ。
この事実を知った時、肩の力が抜けました。みんな仲良さそうに見えて、実は適度な距離を保っているだけなんだと。実は私、以前『嫌われる勇気』を読んで人間関係の悩みを解決した経験があるんですが、今回のDaiGoさんの本も同じくらい効果がありました。
職場の人間関係に疲れた私が実践!DaiGoが教える3つの境界線テクニック
1. 時間の境界線:「5分ルール」で愚痴から解放
職場でよくある「ちょっと聞いてよ〜」から始まる愚痴タイム。気づけば30分経っていて、自分の仕事が進まない…なんてこと、ありませんか?
『人間関係をリセットして自由になる心理学』で紹介されている「5分ルール」を実践してみました。
具体的な方法:
- 相談を受けたら、スマホのタイマーを5分にセット(見えないように)
- 最初の5分は真剣に聞く
- 5分経ったら「ごめん、○○の締切が迫ってて…でも大変だよね」と切り上げる
実践して3週間、驚くべき変化がありました。最初は「冷たい」と思われるかと心配でしたが、むしろ「忙しいのに聞いてくれてありがとう」と感謝されることが増えたんです。時間を区切ることで、相手も要点をまとめて話すようになり、お互いにとってプラスになりました。
2. 感情の境界線:「課題の分離」で他人の機嫌に振り回されない
月曜の朝、上司が不機嫌そうな顔をしていると、「私、何かやらかした?」って不安になりますよね。でも、これってすごくエネルギーを消耗します。
DaiGoさんは、アドラー心理学の「課題の分離」という考え方を紹介しています。簡単に言うと、「他人の機嫌は他人の課題、自分の仕事は自分の課題」という線引きです。
実践方法:
- 朝一番に「今日の自分の課題リスト」を3つ書く
- 誰かが不機嫌でも「それは相手の課題」と心の中でつぶやく
- 自分の課題に集中する
正直、最初は難しかったです。でも、1週間続けたら、職場の雰囲気に左右されずに仕事ができるようになりました。生産性も上がって、定時で帰れる日が増えたのは嬉しい誤算でした。
3. 物理的な境界線:「パーソナルスペース」を守る3つの工夫
フリーアドレスの職場で働いていると、隣の人との距離が近すぎて集中できないことがあります。『人間関係をリセットして自由になる心理学』では、物理的な境界線の重要性も説かれています。
私が実践している3つの工夫:
- デスク周りに小さな観葉植物を置く(視覚的な境界線)
- ノイズキャンセリングイヤホンを使う(聴覚的な境界線)
- 立ち仕事スペースを活用する(場所を変えることで境界線をリセット)
特に効果があったのは、ノイズキャンセリングイヤホンです。音楽を流さなくても装着しているだけで「今は集中タイム」というサインになり、話しかけられる回数が激減しました。
職場の人間関係ストレスが激減した3つの変化
変化1:ランチタイムが自由になった
以前は「みんなでランチ行こう」という誘いを断れませんでした。でも、境界線を意識するようになってから、週2回は一人ランチを楽しむようになりました。
「今日は読書しながら食べたいから」と正直に伝えると、意外とあっさり受け入れてもらえました。むしろ「私も時々そうしたい」という声も聞こえてきて、職場に「一人時間OK」の雰囲気が生まれました。
変化2:仕事の評価が上がった
これは予想外でしたが、人間関係に使っていたエネルギーを仕事に向けたら、明らかに成果が上がりました。上司からも「最近、集中力が上がったね」と言われ、新しいプロジェクトを任されることに。
職場の人間関係を「リセット」することは、決して「冷たくなる」ことではなく、本来の仕事に集中できる環境を作ることだったんです。
変化3:本当に大切な関係が見えてきた
境界線を作ることで、逆に本当に大切にしたい関係が見えてきました。仕事の相談ができる先輩、ランチ後に「今日も頑張ろう」と言い合える同期。数は少なくても、質の高い関係性が築けています。
心理学研究によると、職場で親密な関係を持つ人の数は平均2〜3人で十分だそうです。全員と仲良くする必要はなかったんですね。
20代の私たちができる「ドライで温かい」関係の作り方
「察して」文化からの卒業
日本の職場特有の「察して」文化。でも、20代の私たちが率先して「言葉にする」文化を作っていけるんじゃないでしょうか。
私が実践しているのは:
- 「今日は集中したいので、イヤホンしてます」と朝一で宣言
- 「15時まで締切があるので、相談は16時以降にお願いします」と具体的に伝える
- 「助かりました、ありがとうございます」を忘れない
最初は勇気がいりましたが、明確に伝えることで誤解が減り、お互いにストレスが減りました。
SNS疲れも含めた「トータル人間関係」の見直し
職場の人間関係って、今やSNSまで含まれますよね。同僚のInstagramをフォローすべきか、上司のFacebookの投稿にいいねすべきか…。
DaiGoさんは「オンラインとオフラインの境界線」の重要性も説いています。私は思い切って、仕事関係のSNSは「見ない・つながらない」ルールを作りました。プライベートは完全に分ける。これだけで、精神的な負担がぐっと減りました。
リモートワークが増えた今、在宅勤務でのストレス管理も重要ですが、オフィスでもオンラインでも、境界線を作ることの大切さは変わらないんですよね。
職場の人間関係に疲れた時のまとめ:人間関係は「リセット」できる
『人間関係をリセットして自由になる心理学』を読んで実践して分かったのは、職場の人間関係の悩みは「距離感の調整」で解決できるということ。
82.7%の人が職場でストレスを感じている今、私たち20代が新しい働き方、新しい人間関係の形を作っていけるチャンスだと思います。全員と仲良くする必要はない。でも、誰とも敵対する必要もない。適度な距離感で、お互いを尊重し合える関係。それが、これからの職場に必要な人間関係なのかもしれません。
明日の月曜日、また新しい一週間が始まります。でも今は、以前のような憂鬱さはありません。自分の境界線を守りながら、必要な時は協力し合える。そんな「ドライで温かい」関係性を、これからも大切にしていきたいと思います。
もし職場の人間関係に疲れているなら、まずは「5分ルール」から試してみてください。小さな一歩が、大きな変化につながるはずです。
メンタリストDaiGoが教える、職場の人間関係に疲れたあなたへの処方箋。科学的根拠に基づいた実践的なテクニックで、自由な人間関係を手に入れる。
¥1,320(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp