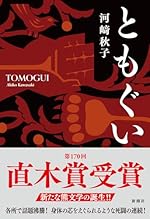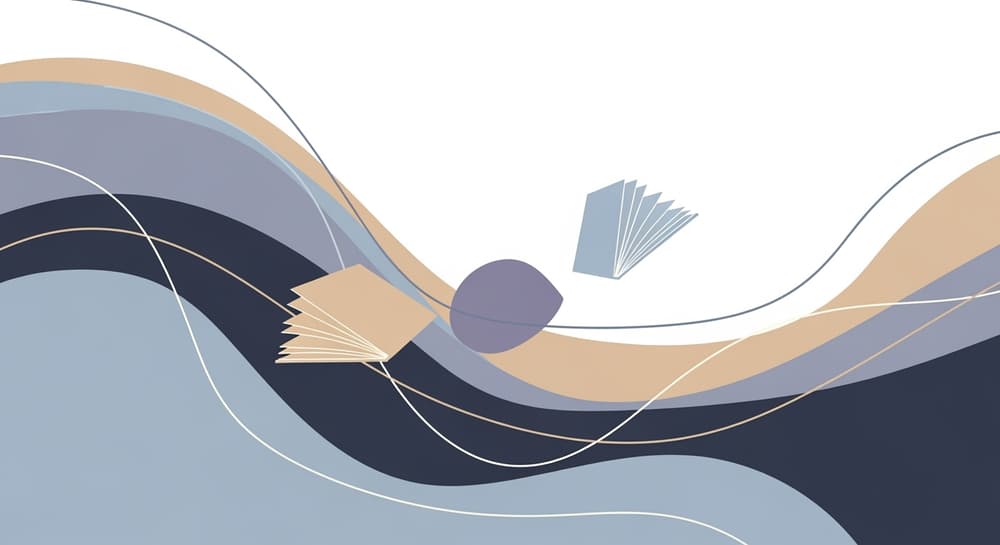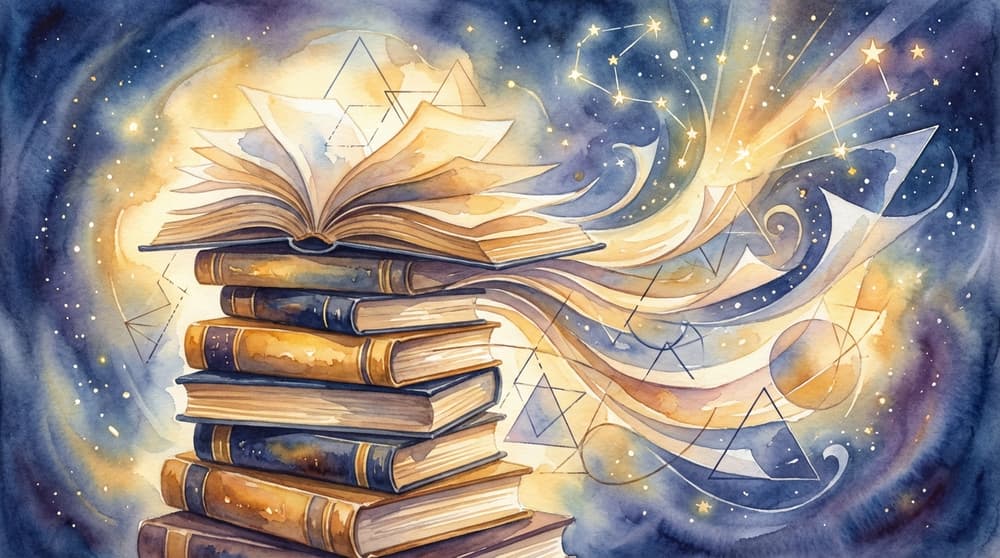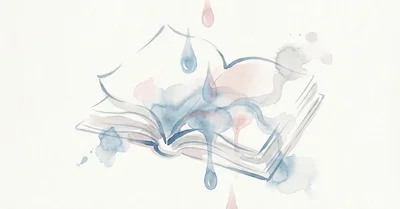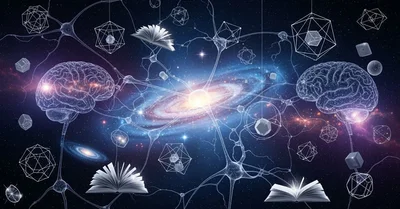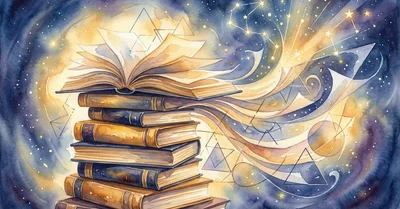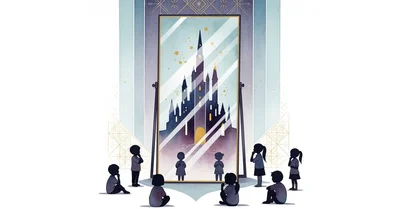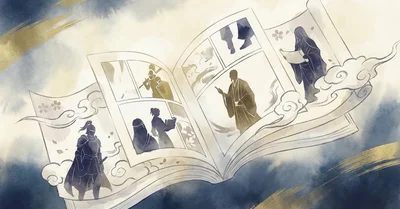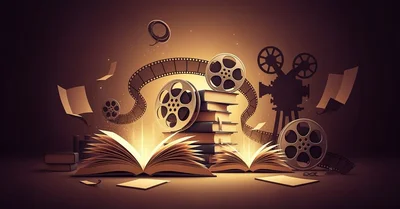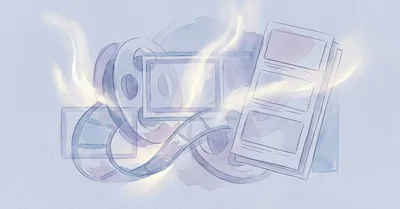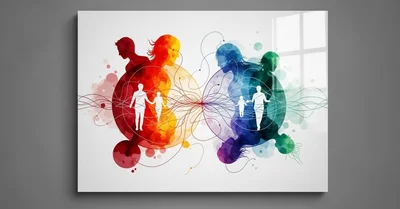『ともぐい』直木賞受賞作を読んで震えた、北海道開拓の壮絶な真実
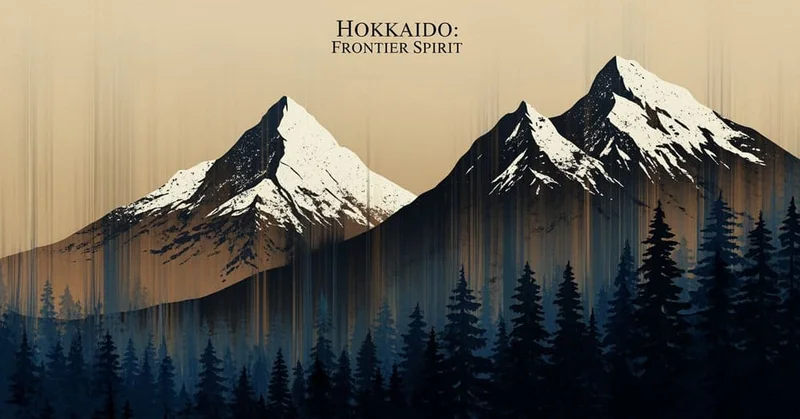
正直に言います、この本は想像を超えていました
直木賞受賞のニュースを見た時、『ともぐい』というタイトルから私が想像していたのは、もっと現代的な人間関係の複雑さを描いた作品でした。でも実際に読んでみると、明治後期の北海道の山奥で繰り広げられる、想像を絶する過酷な現実が描かれていて、最初のページから最後まで、文字通り震えながら読み進めました。
出版社時代にも数多くの文学作品を読んできましたが、これほど「作者の実体験に基づく重み」を感じた作品は珍しいんですよね。河﨑秋子さんがご自身の猟師としての経験を活かして書かれたということを知って、この作品の持つリアリティの源が理解できました。
個人的に、私たら20代が知らない日本の歴史の一面を、これほど生々しく描いた作品に出会えたことに深い感動を覚えています。この物語の詳しい内容について、以下でお話ししていきます。
『ともぐい』が描く明治後期北海道の現実
作者・河﨑秋子さんの圧倒的な背景
河﨑秋子さんは1979年生まれの44歳で、北海道別海町でご自身も狩猟を行いながら創作活動をされている作家さんです。実際にヒグマの生息地域に住み、エゾシカやヒグマの猟を経験されているんです。この作品を読んでいると、その実体験がどれほど物語に深みを与えているかがわかります。
特に印象的だったのは、動物の解体シーンや山での生活の描写です。これは単なる想像や資料調査だけでは書けない、実際に体験した人だからこそ描ける生々しさがありました。出版社時代に多くの作家さんとお話しする機会がありましたが、ここまで作品と作者の実体験が直結している例は珍しいと感じます。
明治後期の北海道開拓という歴史的背景
物語の舞台は明治後期、日露戦争前夜の北海道の山奥です。この時代設定がとても重要なんですよね。明治政府の開拓政策によって多くの人々が北海道に入植しましたが、その現実は私たちが教科書で習ったような美談とは程遠いものでした。
厳しい自然環境の中で、法律や常識が通用しない世界。文明から隔絶された場所で、人間がどこまで追い詰められるのか。この作品は、そんな極限状況を容赦なく描いています。現代を生きる私たちには想像もつかない過酷さですが、それがわずか150年前の日本の現実だったということに、改めて衝撃を受けました。
主人公・熊爪の人物像と生き様
主人公の熊爪(くまづめ)は、山で野生動物のように生きる猟師です。人里離れた山奥で、ほとんど人間との接触を絶って暮らしています。最初は粗野で野蛮な人物のように見えるのですが、読み進めるうちに、彼の中にある複雑な人間性が見えてきます。
熊爪が「穴持たず」と呼ばれる巨大な熊を追い続ける姿は、単なる狩猟を超えて、何か運命的なものを感じました。また、盲目の少女・イノとの関係性も、この物語の重要な軸になっています。二人の関係は、愛情とも保護とも違う、この作品でしか描けない独特なものでした。
「ともぐい」というタイトルの深い意味
最初に「ともぐい」というタイトルを見た時は、人間同士が争い合う話なのかと思っていました。でも読み終わってみると、このタイトルがいかに深い意味を持っているかがわかります。
この作品での「ともぐい」は、単純な共食いではありません。生き残るために何でもする、人間の生存本能の極限を表現しています。食べるか食べられるかという自然界の掟の中で、人間もまた一つの生物でしかないという現実。現代社会では忘れがちな、生きることの根源的な意味を問いかけているんですよね。
第170回直木賞受賞の意義
現代文学における新しい地平
この作品が直木賞を受賞した意義は、単に優れた歴史小説だからということではないと思います。河﨑さんのような、実際にその世界を知る作家が描く文学の新しい可能性を示したのではないでしょうか。
従来の文学作品では、都市部を舞台にした現代的なテーマが多かったように感じます。例えば、私が以前レビューした『ハンチバック』のような現代社会の問題を描いた作品も素晴らしいですが、『ともぐい』は、北海道という地域性と、猟師という職業、そして明治期という時代背景を、すべて作者の実体験と結びつけて描いています。これは新しい文学の形だと思うんです。
選考委員の方々のコメントを読んでも、この「リアリティの圧倒的な説得力」が高く評価されていることがわかります。読者として、これまでに読んだことのない世界を体験できる贅沢さを感じました。
Z世代として学んだこと、現代への示唆
生きることの根源的な意味を考える
私たちの世代は、物質的には恵まれた環境で育ってきました。でも『ともぐい』を読んで、生きることの根源的な意味について改めて考えさせられました。熊爪やイノが直面する生死の境界線は、現代の私たちの悩みとは次元が違いすぎて、最初は戸惑いました。
でも読み進めるうちに、彼らが見せる人間としての尊厳や、極限状況での判断力に、現代にも通じる普遍的なものを感じたんです。SNSで日々小さなことに一喜一憂している自分と比べて、「本当に大切なことって何だろう」と考えるようになりました。
歴史を「他人事」にしない大切さ
出版社時代から歴史小説は読んでいましたが、多くの場合、歴史は「過去の出来事」として消費していたように思います。でも『ともぐい』は違いました。この物語に登場する人々の血と汗が、現在の北海道の基盤を築いたのだと思うと、歴史が急に身近に感じられました。
特に印象的だったのは、開拓民たちの描写です。政府の政策に翻弄され、厳しい自然環境の中で生きるしかなかった人々。彼らの犠牲の上に、私たちの今の生活があるということを、この作品を通じて実感しました。
現代社会の豊かさを再認識する
極限状況での人間の選択を読んでいると、現代社会の豊かさを改めて実感します。食べ物があること、暖かい場所で眠れること、安全が保障されていること。当たり前だと思っていたことが、実はとても貴重なものなんですよね。
でも同時に、現代社会特有の問題もあります。物質的な豊かさの一方で、人間関係の希薄さや、生きる目的の見失いやすさ。熊爪やイノのような、生きることへの純粋な執着を見ていると、私たちが何かを見失っているような気がしました。
読書を通じた想像力の拡張
この作品を読んで最も感じたのは、読書が持つ「想像力を拡張する力」です。28歳の私が、明治期の北海道の猟師の気持ちを理解することなんて、普通に考えれば不可能です。でも河﨑さんの圧倒的な筆力によって、その世界を疑似体験することができました。
これは以前読んだ東野圭吾さんの『クスノキの番人』でも感じたことですが、優れた文学作品は時代や設定を超えて、読者の心に響く何かを持っているのだと思います。個人的に、この体験は今後の人生で大きな財産になると思います。自分とは全く違う環境で生きる人々への想像力、過去の人々への敬意、そして現在の自分の位置を客観視する視点。これらすべてを、一冊の本から得ることができたんです。
なぜ今、この作品を読むべきなのか
現代人が忘れがちな「生きる力」を思い出させてくれる
現代社会では、多くの問題がシステムや制度によって解決されます。でも『ともぐい』の世界では、最終的に頼れるのは自分の判断力と行動力だけです。熊爪の生き方を見ていると、私たちが普段どれだけ他人や社会に依存して生きているかがわかります。
これは現代を否定するということではありません。でも、いざという時に自分で考え、自分で決断し、自分で行動する力。この「生きる力」の大切さを、この作品は教えてくれます。
文学が持つ「時代を超える力」を実感できる
この作品を読んで、文学の持つ普遍性を強く感じました。明治期の北海道という、現代からは遠く離れた世界を描いているのに、そこには現代にも通じる人間の本質があります。愛、憎しみ、恐怖、希望。時代が変わっても、人間の感情の根本は変わらないんですよね。
特に私たちZ世代は、SNSなど瞬間的な情報に慣れ親しんでいます。でも『ともぐい』のような作品は、時間をかけて深く読み込むことで初めてその真価がわかります。この「じっくり向き合う読書体験」の価値を、改めて実感しました。
日本文学の新しい可能性を感じられる
河﨑秋子さんのような、実体験に基づく文学作品が注目されることは、日本文学にとって新しい展開だと思います。都市部の知識人が描く文学だけでなく、地方で実際にその仕事をしている人が描く文学。これは文学の多様性という意味でも重要です。
私たちの世代は、多様性を重視する世代です。文学の世界でも、もっと多様な背景を持つ作家さんの作品が読まれるべきだと思います。『ともぐい』は、その先駆けとなる作品の一つだと感じています。
以上の理由から、この作品を多くの方に読んでいただきたいと思います。
文学・歴史関連の記事として、以下もおすすめです。