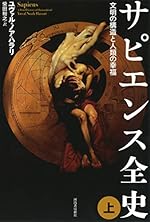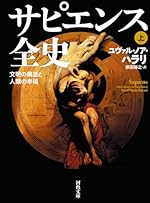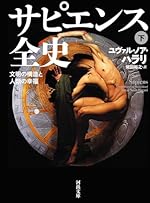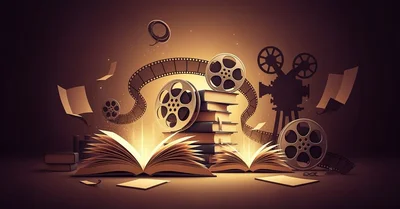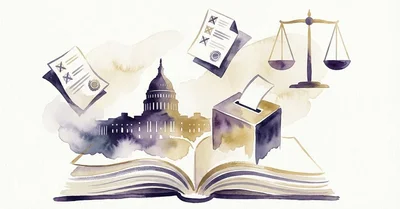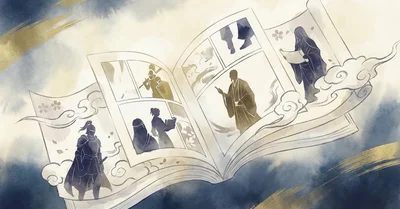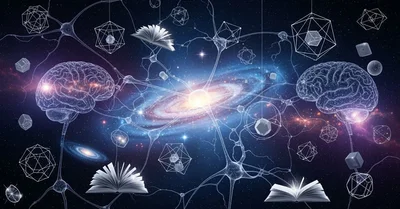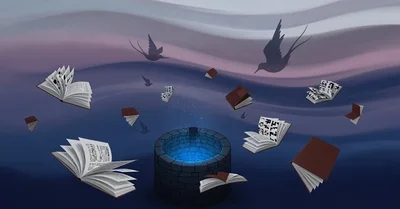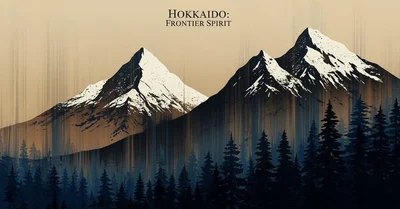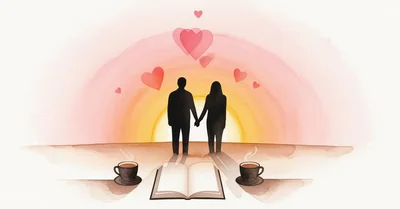『サピエンス全史』から考える人類の未来 - 認知科学が解き明かす虚構の力

京都大学大学院の研究室で日々認知科学の研究に取り組んでいる私にとって、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』は特別な一冊です。興味深いことに、この本が提起する「虚構を信じる能力」という概念は、私たちが研究している認知機能の核心に迫るものなのです。
先週、研究仲間との読書会でこの本を取り上げた際、激しい議論が交わされました。「本当に7万年前に認知革命は起きたのか?」「虚構を信じる能力は本当にホモ・サピエンス特有なのか?」これらの疑問に、最新の認知科学研究はどう答えているのでしょうか。
今すぐ『サピエンス全史』を読む
著者: ユヴァル・ノア・ハラリ
認知革命から農業革命まで、人類史の前半を描く。虚構を信じる能力がいかに人類を特別な存在にしたかを解き明かす。
¥2,090(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
人類の統一から科学革命まで、そして人類の未来への問いかけ。技術進歩は本当に私たちを幸福にしたのか?
¥2,090(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
認知革命は本当に7万年前に起きたのか?
『サピエンス全史』の中でハラリは、約7万年前に起きた「認知革命」によってホモ・サピエンスが地球の支配者になったと主張します。しかし、データによると、この時期設定には科学的な議論があります。
最新の研究論文「Language evolution to revolution」(Vyshedskiy, 2019)では、現代的な音声器官は60万年前にすでに獲得されていたことが示されています。興味深いことに、象徴的思考を示す考古学的証拠(複合的な芸術作品、骨製の針、住居の建設など)が現れるのは確かに7万年前頃からなのです。
この60万年前から7万年前までの長大なギャップをどう説明するか。仮説ですが、音声器官の獲得と、それを使って複雑な虚構を共有する認知能力の獲得には、大きな時間差があったのかもしれません。
虚構を信じる能力の認知科学的基盤
京都の古本屋で見つけた認知心理学の古典を読み返しながら、私は『サピエンス全史』の核心的主張について考えを巡らせました。「虚構を信じる能力」とは、認知科学的にはどのような機能なのでしょうか。
原著論文では、この能力は「Prefrontal Synthesis」(前頭前野統合)と呼ばれる認知機能と深く関わっているとされています。人間の前頭前野は他の霊長類と比べて格段に大きく、これが抽象的な概念を生成し、未来を計画する能力の基盤となっているのです。
データによると、現代人の脳では、虚構的な物語を聞いているときと実際の出来事を経験しているときで、驚くほど似た神経活動パターンが観察されます。つまり、私たちの脳は「物語」を「現実」と同じように処理しているのです。これは、『ファスト&スロー』で解説した二重過程理論とも深く関連する現象です。
最新研究が示す認知革命の複雑性
2022年にPhilosophical Transactions of the Royal Society Bに掲載された論文では、認知革命は単一の出来事ではなく、段階的なプロセスだったことが示唆されています。
14万年前から、人類は物質文化を通じて未来を形作り、アイデアを交換していた証拠があります。さらに、16万4千年前の南アフリカでは、すでに象徴的思考の兆候が見られるのです。
追試研究によると、「現代的行動」とされる特徴は、アフリカ大陸の異なる地域で非同期的に現れています。これは、ハラリが描くような単純な「革命」というよりも、複雑で多様な文化進化のプロセスだったことを示しています。
学術界からの批判と反論
研究室の哲学カフェで議論になったのは、『サピエンス全史』への学術的批判です。福岡伸一氏は、認知革命が突然変異による急激な変化ではなく、より長期的なプロセスだったのではないかと指摘しています。
人類学者のロビン・ダンバーによれば、初期の宗教は集団統率のためというより、個人的経験を共有するためのものだった可能性があります。また、最近の実験では、サルも貨幣システムという「虚構」を理解できることが示されており、ハラリの「ホモ・サピエンス特有説」に疑問を投げかけています。
興味深いことに、「想像の共同体」(ベネディクト・アンダーソン)や「共同幻想論」(吉本隆明)など、虚構が社会を支えるという考え方自体は新しいものではありません。しかし、『サピエンス全史』の価値は、この概念を人類史全体の文脈で捉え直した点にあるのかもしれません。
認知科学から見る人類の未来
夜遅くまで論文を読みながら、私は人類の未来について考えずにはいられません。『サピエンス全史』の最後でハラリは、私たちが「神になろうとしている動物」だと述べています。
認知科学の観点から見ると、AIやバイオテクノロジーの発展は、まさに新たな「認知革命」を引き起こす可能性があります。仮説ですが、人工知能が人間と同等の「虚構を信じる能力」を獲得したとき、何が起こるでしょうか。
最新の神経科学研究では、脳とコンピュータのインターフェース技術が急速に進歩しています。これらの技術が、人類の認知能力を根本的に変える可能性は否定できません。
『サピエンス全史』から学ぶべきこと
京都の古本屋巡りから研究室に戻り、改めて『サピエンス全史』を読み返すと、この本の真の価値が見えてきます。それは、私たちが当たり前だと思っている社会の仕組みが、実は共同の「虚構」に基づいているという気づきを与えてくれることです。
データによると、現代社会の複雑な協力関係は、確かに共有された物語なしには成立しません。国家、貨幣、企業、人権 - これらはすべて、私たちが集団で信じることで初めて「現実」となるのです。
原著論文では触れられていませんが、この洞察は私たちの日常生活にも応用できます。例えば、研究者として論文を書くとき、私たちは「科学的真理」という共同幻想を前提にしています。それは幻想だから無意味なのではなく、むしろその共同幻想があるからこそ、知識の蓄積と進歩が可能になるのです。この点は、編集長が『FACTFULNESS』の書評で指摘した思い込みの克服とも通じる重要な洞察です。
まとめ:虚構の力を理解し、より良い未来を構想する
『サピエンス全史』は完璧な本ではありません。学術的な批判も多く、単純化されすぎている部分もあります。しかし、認知科学を専門とする私から見ても、この本が提起する問いは極めて重要です。
興味深いことに、虚構を信じる能力こそが、私たちに未来を変える力を与えているのです。気候変動、格差、戦争 - これらの問題を解決するためには、新しい「物語」が必要かもしれません。
すべての知識は、つながっている - これが私の信条です。『サピエンス全史』を読むことで、人類の過去と未来、そして私たち一人一人の認知能力がどのようにつながっているかが見えてくるはずです。
『サピエンス全史』をもう一度
文庫版下巻。科学革命から現代まで、そして人類の未来への問いかけ。じっくりと考えながら読みたい一冊。
¥1,155(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
人類の歴史と未来を考えた後は、現代を生きる一人の女性の視点から社会を見つめ直してみませんか。