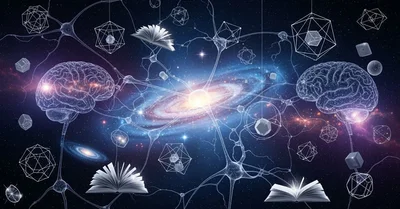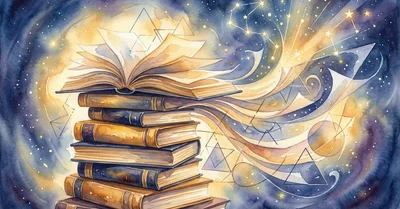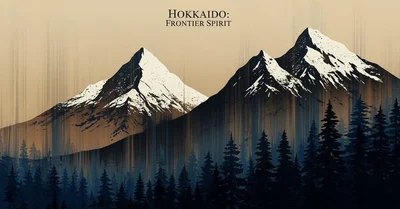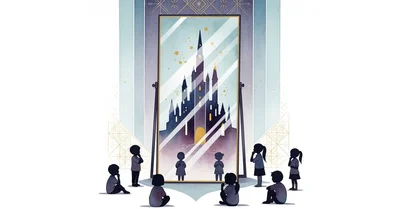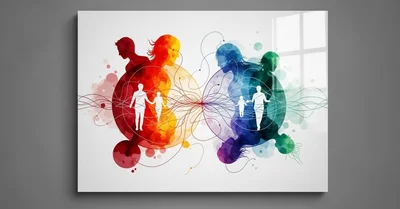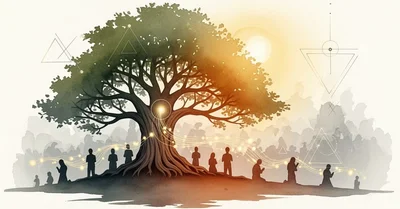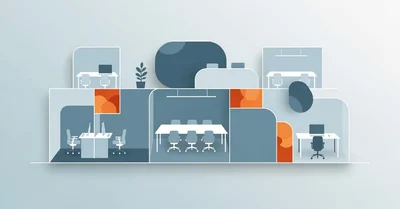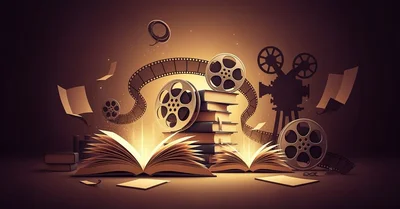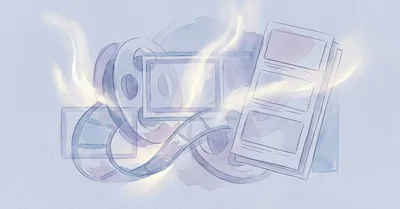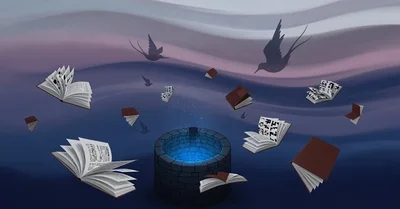『ハンチバック』感想レビュー|28歳が語る芥川賞受賞作の衝撃と現代への問いかけ
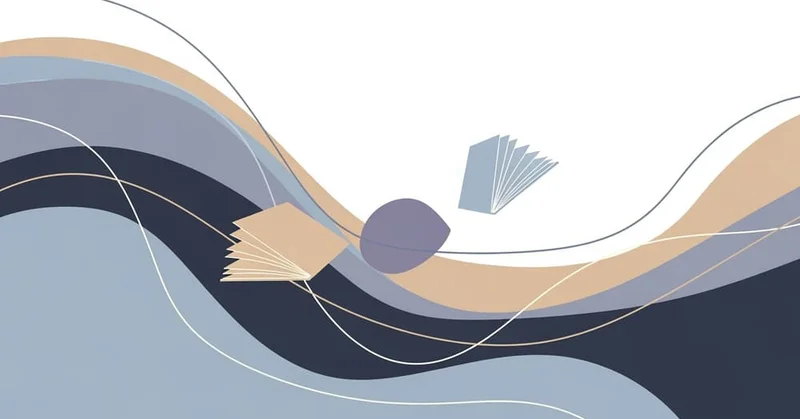
あなたは「みんな」という言葉を使う時、誰を想像していますか?
2023年7月、Twitterのタイムラインに流れてきた芥川賞受賞のニュースを見た時、正直に言うと「ハンチバック」というタイトルから、私は全く違う内容を想像していました。実は最初、何かファンタジー系の作品かな?なんて思ってしまったんですよね。
でも、受賞理由や選考委員のコメントを読んでいくうちに、これは全く違う、もっと現実的で重要な作品なんだと気づかされました。市川沙央さんという作家さんのことも、恥ずかしながらその時初めて知ったのですが、出版社時代に多くの作品を読んできた私でも、調べていくうちにこの作品がどれほど画期的で勇気ある挑戦なのかがわかってきました。
個人的に、SNS世代の私たちが抱えている孤独感や繋がりを求める気持ちと、どこか通じるものがありそうだと感じて、すぐに読んでみることにしました。読み終わった今、この作品が投げかけている問題は、私たちZ世代が真剣に向き合うべきテーマだと心から思っています。
『ハンチバック』ってどんな作品なの?
作者・市川沙央さんの背景
市川沙央さんは1979年生まれの43歳で、早稲田大学人間科学部を卒業された作家さんです。筋疾患先天性ミオパチーによる症候性側弯症を患っていて、人工呼吸器を使用し、電動車椅子で生活されています。
実は市川さんがこの作品を書いたのは「読書のバリアフリー」を訴えるためだったんです。2022年の夏に初めて純文学作品として『ハンチバック』を執筆されました。障害者と社会の関係性改善を訴える目的があったということを知って、私はとても感動しました。
あらすじと主人公・釈華について
主人公の井沢釈華は、先天性筋疾患のため背骨がS字に湾曲し、人工呼吸器と電動車いすを利用している重度障害者の女性です。親が遺したグループホームで裕福に暮らしていて、有名私大の通信課程に通いながら、ライターとしてコタツ記事を書いています。面白いのは、その収入を全額寄付していることなんですよね。
釈華は自分の部屋から、SNS、小説投稿サイト、ライター業務を通じて様々な形で言葉を発信しています。特に18禁TL小説をサイトに投稿しているという設定が印象的でした。これって、現代の私たちがオンライン上で自分を表現する方法と、本質的にはそう変わらないと思うんです。
物語は、釈華がTwitterで「妊娠と中絶をしてみたい」とツイートしたことから動き始めます。このツイートをヘルパーの男性に特定されてしまい、多額のお金と引き換えにあることを持ちかける、という展開になります。
釈華の日常と内面描写の鮮やかさ
釈華の一日は、朝のヘルパーさんとの会話から始まります。人工呼吸器の音が響く部屋で、彼女がどのように日常を過ごしているのか、市川さんの筆致は驚くほど細やかです。出版社時代に数多くの作品に触れてきましたが、これほど障害者の日常を内側から描いた作品は珍しいと感じました。
特に印象的だったのは、釈華がTL小説を書く場面です。恋愛や性愛を描きながらも、それが単なるエンターテイメントではなく、自分の内面を表現する手段として描かれています。「私にはできない体験だからこそ、想像で補う部分が多くなる。でも、それが逆に純粋な感情を描くことにつながっている」という釈華の心情描写は、創作の本質を突いていて胸に響きました。
釈華がコタツ記事を書いて得た収入を全額寄付しているという設定も、単なる善行としてではなく、社会への複雑な感情の表れとして描かれているのが深いんですよね。
ここまで読んで、私は「この作品をもっと多くの人に読んでもらいたい」と強く思いました。特に私たちZ世代には、きっと響くものがあると思います。
芥川賞選考委員からの圧倒的な評価
選考委員の平野啓一郎さんは「主人公が抱えている困難な状況を通じて社会的な通念、われわれが常識と信じているものを批評的に解体しながら、自分の存在を描き出している。圧倒的な支持を集めた」とコメントされています。
選考会では「文学的才能と主題が高い水準で拮抗する稀有な作品」として評価され、特に以下の点が高く評価されました:
- 言語表現の豊かさと文章の巧みさ
- 読者に「知らない世界に触れている」実感を与える力
- 社会批評性を持った「健常者優位主義」への糾弾
- 圧倒的迫力とユーモアのある表現
主人公・釈華が抱える現代的な孤独
物理的・社会的な孤立が生み出すもの
釈華が自室で過ごさざるを得ない状況は、確かに物理的な制約によるものです。でも、これって現代の多くの人が経験している社会的孤立と、根本的には同じような感覚なのではないかと思います。
コロナ禍を経験した私たちZ世代にとって、部屋から外の世界とつながることの難しさや、リアルな人間関係を築くことの困難さは、決して他人事ではありません。釈華の状況は極端かもしれませんが、現代社会の孤独・孤立問題の本質を浮き彫りにしていると感じます。
SNSや小説投稿サイトでの自己表現
釈華がTwitterで発信したり、小説投稿サイトで作品を公開したりする姿は、まさに現代の私たちそのものですよね。オンライン上で自分を表現し、誰かとつながろうとする行動パターンは、SNSネイティブ世代の私たちにはとても馴染み深いものです。
特に印象的だったのは、釈華が18禁TL小説を書いているという設定です。これは単なる娯楽ではなく、自分の内面や欲望を表現する手段として描かれています。SNSでの投稿も、ブログでの発信も、結局は「自分を知ってもらいたい」「誰かとつながりたい」という根源的な欲求の表れなんですよね。
Z世代の私が感じた共通点
釈華の孤独感や社会への違和感は、物理的制約があるかないかという違いはあっても、現代を生きる私たちの多くが感じているものと共通していると思います。
例えば、Twitterで本音をつぶやいて炎上してしまったり、オンライン上での発言が現実の人間関係に影響したりする経験って、多くの人が持っていますよね。釈華がヘルパーの男性にTwitterアカウントを特定されてしまうシーンは、私たちがSNSで感じる「見つかってしまう怖さ」と同じものだと感じました。
また、内閣府の2024年調査によると、39.3%の人が孤独感を感じていて、特に20代〜50代で孤独感を「頻繁に・常に」感じる割合が高いことがわかっています。私たち20代女性では特にその傾向が顕著だそうです。釈華の孤独感は決して特別なものではなく、現代社会の構造的問題の一つの現れなのかもしれません。
この作品が投げかける社会への問題提起
「健常者優位主義」への鋭い批判
『ハンチバック』が最も強烈に批判しているのは「健常者優位主義」です。社会のシステムや価値観が健常者を基準に作られていて、それ以外の人々が排除されてしまう構造を、釈華の視点から鋭く描いています。
これまで私は、バリアフリーという概念を物理的なアクセシビリティの問題としてしか捉えていませんでした。でも、この作品を読んで、それがもっと根深い社会の意識や構造の問題だということを痛感しました。実は以前、『82年生まれ、キム・ジヨン』を読んで感じた現代女性の生き方への共感でも書いたのですが、社会の構造的な問題は性別や障害の有無に関わらず、様々な場面で私たちの前に現れるんですよね。
現代社会の孤独・孤立問題の構造
警察庁のデータによると、年間約6.8万人の高齢者が孤独死していて、発見まで平均18日かかっているそうです。この数字を見ると、孤独・孤立は個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき構造的な課題だとわかります。
『ハンチバック』は、障害者が直面する社会からの排除を通じて、この構造的問題を可視化しています。全国の障害者総数は約1,164.6万人(人口の約9.3%)で、多くの人が社会の主流から取り残されている現実があります。
読書バリアフリーという新しい視点
市川さんが「読書のバリアフリー」を訴える目的でこの作品を書かれたということを知って、私は読書という行為についても考え直しました。文字を読むこと、本を手に取ること、図書館に行くこと。私たちが当たり前だと思っていることが、実はすべての人にとって当たり前ではないんですよね。
2024年4月には「孤独・孤立対策推進法」が施行され、障害者への合理的配慮提供も義務化されました。でも、法制度だけでは解決できない意識の問題があることを、この作品は教えてくれます。
私たちが『ハンチバック』から学べること
多様性への理解を深める具体的な方法
『ハンチバック』を読んで、私は自分の「常識」を疑ってみることの大切さを学びました。例えば、普段何気なく使っている「みんな」という言葉。「みんなそう思ってる」「みんなできる」という表現の中に、実は排除されている人たちがいることを意識するようになりました。
この作品を読んでから、私のSNSでの発信方法も変わりました。例えば、先日カフェの写真をInstagramに投稿する時、「みんなでわいわい楽しめるスポット!」って書きかけたんですが、ふと手が止まったんです。「みんな」って誰のこと?車椅子でも入れるのかな?って。
結局、「友人とゆっくり話せる落ち着いたカフェでした。店内はバリアフリー対応で、ゆったりとした席配置です」と投稿し直しました。小さな変化かもしれませんが、こういう積み重ねが大切だと思っています。
街を歩いていても意識が変わりました。渋谷のスクランブル交差点を歩いている時も、「ここは車椅子の人には使いづらいかも」「この表示は視覚に障害のある人には伝わりにくいかも」と自然と考えるようになったんです。
身近な孤独感への気づき方
内閣府の調査で明らかになったように、私たちの世代でも多くの人が孤独感を抱えています。『ハンチバック』を読んで、孤独を感じることは恥ずかしいことではなく、現代社会の共通の課題なんだと理解できました。
友人や家族とのコミュニケーションを見直す 「大丈夫?」「最近どう?」という声かけを、もっと意識的に行うようになりました。うちのハムスターのぽんずでさえ、一人でいると寂しそうにしているのを見ると、人間ならなおさらだと思います。
オンラインとオフラインのバランス SNSでのつながりも大切だけれど、リアルでの交流も意識して作るようにしています。釈華のように物理的制約がある場合は別ですが、選択肢がある私たちは両方を活用できるはずです。
あなたも経験ありませんか?SNSでの「炎上」への恐怖
釈華がTwitterで本音をツイートして問題になるシーン、読んでいて胸がドキドキしました。皆さんも、投稿ボタンを押す前に「これって炎上しないかな?」って不安になったこと、ありませんか?私は正直、何度もあります。
SNSでの発言が現実に影響することの怖さと、それでも発信したい気持ちの両方がリアルに描かれていて、まさに現代の私たちの心境そのものだと感じました。
プライバシーの境界線を考える どこまでが個人的な内容で、どこからが公開してもよい内容なのか。釈華の経験を見ていると、この境界線をもっと慎重に考える必要があると感じました。
発信する目的を明確にする ただなんとなく投稿するのではなく、「誰に何を伝えたいのか」を意識することで、より良いコミュニケーションができるのではないでしょうか。
「常識」を疑ってみる大切さ
『ハンチバック』が最も強く訴えているのは、私たちが当たり前だと思っていることを疑ってみることの重要性です。平野啓一郎さんも評価していた「社会的な通念、われわれが常識と信じているものを批評的に解体」する視点は、現代を生きる私たち全員が身につけるべきスキルだと思います。
日常の中で立ち止まって考える エレベーターのボタンの位置、階段の幅、文字の大きさ。普段気にしていないことが、誰かにとっては大きなハードルになっていることに気づけるようになりました。
メディアの情報を批判的に見る 障害者についての報道やSNSでの議論を見る時も、「誰の視点で語られているのか」「当事者の声は含まれているのか」を考えるようになりました。
現代を生きる私たちへのメッセージ
『ハンチバック』を読み終わって、私は現代社会の孤独・孤立問題について、以前とは全く違う角度から考えるようになりました。障害者の視点から描かれた物語でしたが、そこで描かれている孤独感や社会への違和感は、多くの現代人が共有しているものだと感じます。
この作品が芥川賞を受賞したことの意味は、単に優れた文学作品が認められたということだけではありません。これまで文学の世界であまり取り上げられてこなかった視点や声が、ついに正当に評価されたということだと思います。
年間約6.8万人の孤独死、39.3%の人が感じる孤独感。これらの数字が示しているように、現代日本の孤独・孤立問題は深刻です。でも、『ハンチバック』のような作品を通じて、私たちは新しい視点を獲得し、より包容的な社会を作っていくことができるはずです。
個人的に、この作品を読んで一番変わったのは、「みんな違って、それでいい」ということを本当の意味で理解できたことです。これまでは頭では分かっていても、心の底からは受け入れられていなかったのかもしれません。
SNS世代の私たちは、オンライン上でつながることに慣れています。でも、その一方で本当の意味でのつながりを作ることが苦手になっているのかもしれません。『ハンチバック』は、つながることの困難さと大切さの両方を、重度の障害を持つ主人公の視点から描いています。
これからの社会を作っていく私たちZ世代にとって、この作品から学べることはとても多いと思います。多様性、包容性、そして何より「誰一人として取り残さない」社会を目指していくために、まずは私たち一人一人の意識を変えていくことから始めませんか?
最後に:あなたの「常識」を教えてください
この記事を読んでくださったあなたに質問です。最近、自分の「当たり前」が誰かの「困難」になっていることに気づいた経験はありますか?小さなことでも構いません。SNSでも、日常生活でも、「あ、これって私だけの視点だったのかも」と思った瞬間があれば、ぜひ教えてください。
みんなでシェアすることで、より包容的な社会を作る一歩になるかもしれません。『ハンチバック』を読んで、あなたはどんなことを考えましたか?
以上の理由から、この本を多くの方に読んでいただきたいと思います。
この作品を読むことで、私たちの「当たり前」がいかに多くの人を排除しているか、そして本当の意味での包容的な社会とは何かを考えるきっかけになると思います。