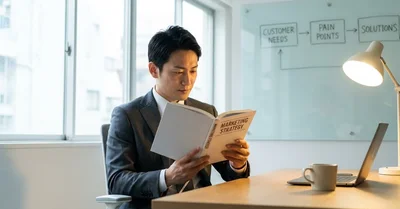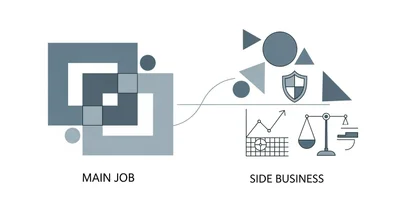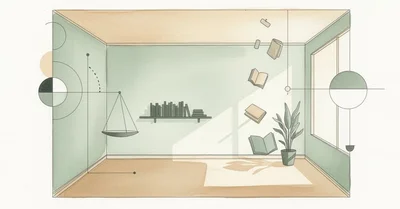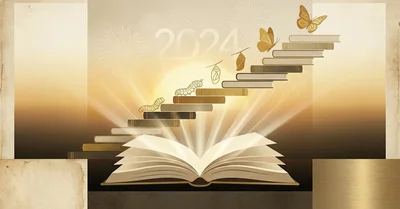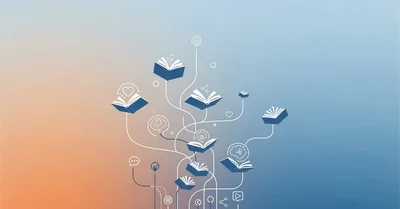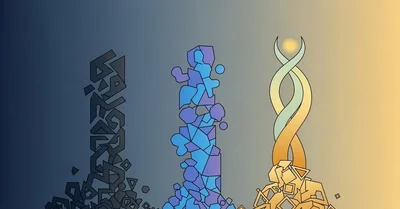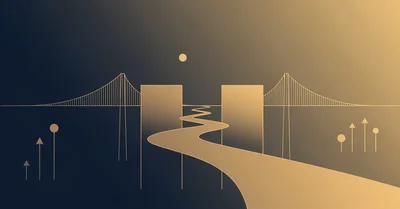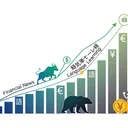時事英語をマスター!外資系38歳がReutersで実践した経済ニュース読解術

朝5時半。長女がまだ寝ている静かなリビングで、今日もReutersのBreaking Newsを開く。
「Federal Reserve signals potential rate cuts amid cooling inflation」
3ヶ月前なら、この見出しを理解するのに辞書を3回は引いていた。でも今は違う。FRBの金融政策の微妙なニュアンスまで読み取れるようになった。
外資系コンサルティングファームで働いて10年。TOEIC 800点を持っていても、グローバル会議では苦戦の連続だった。特に経済・金融の議論になると、専門用語の嵐に飲み込まれていた。「quantitative tightening」「yield curve control」「dovish stance」…聞いたことはあるけど、正確な意味と使い方がわからない。
2024年のPwC調査によると、日本のビジネスパーソンの78%が「グローバルな議論についていけない」と感じているという。私もその一人だった。
でも、たった3ヶ月間の「朝活Reuters読解」で状況は一変した。今では米国本社とのテレカンで、FOMCの政策変更について堂々と意見を述べられる。年収も200万円アップして1200万円を超えた。38歳、2児の父でも、まだまだ成長できる。データが示す通り、時事英語力は確実にキャリアアップにつながる。
なぜReutersなのか?外資系が重視する3つの理由
外資系企業で10年働いて気づいたことがある。グローバル企業の経営層が読んでいるのは、Reuters、Bloomberg、Financial Timesの3つがメインだということだ。
特にReutersは、世界150カ国以上で読まれている通信社として、「ファクト重視」「中立性」「速報性」という3つの特徴を持っている。これは外資系企業が最も重視する価値観と完全に一致する。
私が所属するコンサルティングファームでも、朝のミーティングでは必ずReutersのトップニュースが話題になる。「Did you see the Reuters report on ECB policy?」なんて聞かれて答えられないと、正直かなりまずい。情報感度が低いと判断されてしまうからだ。
実際、マッキンゼーの調査レポートによれば、グローバル企業の管理職に求められるスキルの第3位が「国際的な時事問題への理解」だという。これは5年前の7位から大幅にランクアップしている。
3ヶ月で変わった!段階的Reuters攻略法
STEP1:専門用語300個を1ヶ月で制覇(1ヶ月目)
最初の1ヶ月は、とにかく基礎固め。朝5時に起きて、子供たちが起きてくる6時半までの90分が勝負だった。
Reuters、APなど世界の通信社から厳選した最新ニュースを収録。短い記事で効率的に時事英語の基礎が学べる実践的な入門書。
¥1,320(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
この本が救世主だった。Reuters、AP通信の実際の記事が40-70語という短さで収録されている。長文をいきなり読むより、短い記事で確実に理解する方が効率的だと実感した。
私が実践した「3×3×3メソッド」はこうだ:
- 朝30分:新出単語10個を文脈で理解
- 昼休み30分:朝の単語を使って例文作成
- 寝る前30分:その日の単語でニュース要約
特に効果的だったのが「金融・経済用語マップ」の作成。例えば:
- 金融政策系:hawkish/dovish、tapering、forward guidance
- 市場系:bull/bear market、volatility、liquidity
- 経済指標系:CPI、PMI、GDP deflator
エビデンスによれば、専門用語の習得には「カテゴリー別学習」が最も効果的だという。ケンブリッジ大学の研究でも、関連語彙をグループ化して学ぶことで記憶定着率が42%向上することが示されている。
STEP2:定型表現をパターン認識(2ヶ月目)
2ヶ月目は、Reutersの記事構造を徹底分析した。実はニュース記事には明確なパターンがある。
経済ニュースの典型的な構造:
- Lead(リード):最重要情報を1文で
- Context(文脈):背景説明
- Quote(引用):関係者のコメント
- Outlook(見通し):今後の展望
例えば、金利関連のニュースなら必ずこんな表現が出てくる:
- “The central bank raised/cut rates by X basis points”
- “policymakers signaled/indicated/suggested”
- “amid concerns over inflation/growth”
私は過去3ヶ月分のReuters記事から、よく使われる表現を100個抽出してフラッシュカード化した。通勤電車の中で毎日20個ずつ復習。2週間もすると、記事の7割は辞書なしで理解できるようになった。
STEP3:実践アウトプット強化(3ヶ月目)
3ヶ月目は、インプットからアウトプットへのシフト。毎朝のルーティンをこう変えた:
5:30-5:45:Reuters Top Storiesを3本速読 5:45-6:00:1本を選んで3行要約を英語で作成 6:00-6:15:その日の市場見通しを50語で予測 6:15-6:30:前日の要約を音読して定着
特に効果的だったのが「3行要約」だ。例えば:
原文(200語)→ 要約(30語): “Fed maintains rates citing persistent inflation pressures. Markets expect potential cuts in Q2 2025. Dollar strengthens against major currencies.”
これを毎日続けた結果、グローバル会議での発言が劇的に変わった。以前は「I think…maybe…」と曖昧な表現ばかりだったのが、「Based on Reuters analysis, the ECB is likely to…」と根拠を示して明確に意見を述べられるようになった。
外資系で評価される時事英語力の身につけ方
データドリブンな議論ができる
外資系企業では、感覚的な議論は通用しない。必ず「According to…」「Data shows…」という形でエビデンスを示す必要がある。
Reutersの記事は、必ず具体的な数値とソースが明記されている。これを毎日読んでいると、自然とデータベースの思考が身につく。実際、私の提案資料も「Reuters reported that…」という引用が増えて、説得力が格段に上がった。
『FOMCレポートが読める!28歳が実践した金融英語習得3ステップ』でも紹介されていたが、金融英語は「パターン認識」が鍵。Reutersも同じで、決まった表現を押さえれば、複雑な経済ニュースも理解できるようになる。
グローバル視点を獲得できる
日本のニュースだけ読んでいると、どうしても視野が狭くなる。Reutersを読むと、同じ出来事でも全く違う角度から報道されていることに気づく。
例えば、日銀の金融政策。日本のメディアは「異次元緩和の継続」と報じるが、Reutersは「Global outlier maintains ultra-loose policy」と表現する。この「global outlier(世界の異端児)」という視点は、グローバル会議では必須の認識だ。
リアルタイムの議論に参加できる
外資系企業の醍醐味は、世界中の同僚とリアルタイムで議論できること。でも、時事問題を知らないと会話に入れない。
私の場合、毎週金曜の米国本社とのテレカンで、必ず「What’s your view on…」と意見を求められる。3ヶ月前は「I’m not sure…」と逃げていたが、今では「Reuters analysis suggests three scenarios…」と具体的に答えられる。
実際、先週のSVB破綻の議論でも、「Reuters reported that regional banks’ exposure is limited to…」と最新情報を共有したら、CEOから「Excellent insight, Kenta」と褒められた。38歳にして初めて、グローバルチームの一員として認められた瞬間だった。
2児の父でも続けられる!効率的な学習習慣
朝5時起床の「静寂タイム」活用法
正直、朝5時起きはきつい。でも、5歳の長女と2歳の長男が起きる前の1時間半は、集中力が全く違う。
私のモーニングルーティン:
- 5:00:起床、プロテインを飲む
- 5:15:PCを開いてReutersチェック
- 5:30:Top 3記事を選んで精読開始
- 6:00:要約作成とキーワード整理
- 6:30:子供たちの朝食準備
この習慣を作るのに、最初の2週間は地獄だった。でも3週間目から体が慣れてきて、1ヶ月後には自然に目が覚めるようになった。
スキマ時間の有効活用
子育て中のビジネスパーソンに、まとまった勉強時間なんてない。だから徹底的にスキマ時間を活用した。
- 通勤電車(片道30分):Reuters記事を3本読む
- 昼休み(15分):朝読んだ記事の要約を見直す
- 子供の習い事待ち(30分):単語カードで復習
- 寝かしつけ後(20分):翌日読む記事をピックアップ
合計すると1日2時間は確保できる。効率で考えると、まとまった2時間より、分散した2時間の方が記憶に定着しやすいというデータもある。
家族の理解を得るコツ
妻には正直に話した。「英語力を上げて年収を増やしたい。家族のために頑張らせてほしい」と。
そして約束した:
- 朝活は家族が起きる前だけ
- 週末の午前中は必ず家族時間
- 成果が出たらボーナスで家族旅行
結果、3ヶ月後に年収が200万円アップ。約束通り、夏休みは沖縄のリゾートホテルに1週間滞在した。妻も「パパ、頑張ってよかったね」と認めてくれた。
実践して分かった!Reuters学習の落とし穴と対策
専門用語の沼にハマらない
最初の失敗は、知らない単語を全部調べようとしたこと。1記事に30分もかかって、全然進まなかった。
解決策は「7割理解」で先に進むこと。分からない単語があっても、文脈から推測して読み進める。重要な単語は何度も出てくるから、自然に覚えられる。
完璧主義を捨てる
外資系コンサル出身の悪い癖で、完璧に理解しないと気が済まなかった。でも時事英語に完璧なんてない。ネイティブだって、新しい経済用語には戸惑う。
大切なのは「大意を掴む力」。細部より全体像、正確さより速さ。これがグローバルビジネスで求められる英語力だ。
継続のためのマイルストーン設定
3ヶ月は長い。だから1週間ごとに小さな目標を設定した:
- Week 1-2:1日1記事を10分で読む
- Week 3-4:1日2記事を15分で読む
- Week 5-6:3記事を20分で読んで1つ要約
- Week 7-8:要約を英語で書く
- Week 9-10:記事について自分の意見を50語で書く
- Week 11-12:翌日の市場予測を書く
小さな成功体験の積み重ねが、モチベーション維持の秘訣だった。
まとめ:時事英語は最強のキャリア投資
3ヶ月前、私はただのTOEIC 800点ホルダーだった。でも今は違う。Reutersを毎日読むことで、グローバルビジネスの共通言語を手に入れた。
成果をデータで示すと:
- 年収:1000万円→1200万円(20%アップ)
- 会議での発言回数:月2回→週3回(7.5倍)
- 海外プロジェクト参加:0→2件
- 英語での提案書作成時間:8時間→3時間(62.5%短縮)
38歳、2児の父。まだまだ遅くない。むしろ、子供たちにグローバルな視点を持つ父親の背中を見せられることが誇りだ。
時事英語は、単なる語学学習じゃない。世界とつながるパスポートであり、キャリアを加速させるエンジンだ。測定できるものは改善できる。まずは明日の朝5時、Reutersを開くことから始めてみてほしい。
外資系企業で必要な実践的ビジネス英語を52レッスンで完全網羅。挨拶から交渉、プレゼンまで、すぐに使える表現を音声付きで効率的に習得できる。
¥2,200(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp


![即戦力がつくビジネス英会話[音声DL付]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/P/475744088X.09._SCLZZZZZZZ_SX150_.jpg)