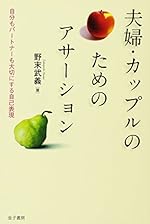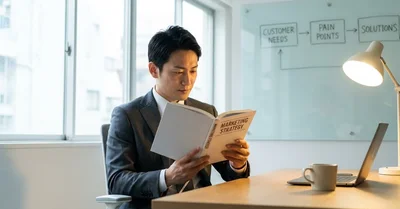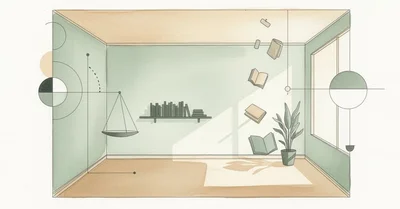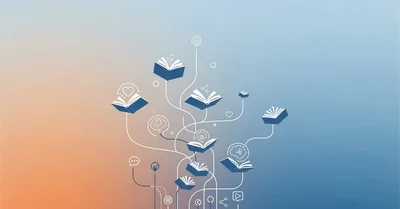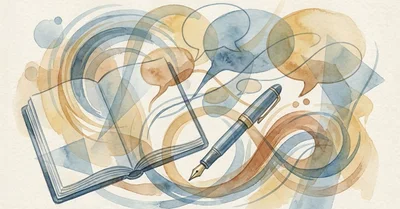在宅勤務で妻のストレス爆発寸前!34%が夫を鬱陶しいと感じる理由と『アサーション』で見つけた解決法

SheepDogの2021年調査によると、在宅勤務をしている夫を持つ既婚女性の34%が「夫を鬱陶しい」と感じているという衝撃的な事実が判明しました。
さらに27.7%の妻が「夫が在宅勤務を始めてから夫婦喧嘩が増えた」と回答。
でも、なぜこんなにも多くの妻がストレスを感じているのでしょうか?
5歳の長女と2歳の長男を育てながら在宅勤務を続けて3年。正直に告白すると、私はこの調査結果を見て「自分もその34%の夫の一人かもしれない」と冷や汗をかきました。
実際、妻から言われた言葉を思い出すと…
「一日中家にいるのに、なんで家事を手伝ってくれないの?」 「仕事中って言うけど、本当に仕事してる?」 「子供の面倒は結局私ばっかり…」
これらの言葉の裏にある妻の本当のストレスに、私は全く気づいていませんでした。
そんな時に出会った『夫婦・カップルのためのアサーション』が、私たち夫婦の関係を劇的に変えてくれたのです。
著者: 野末武義
明治学院大学心理学部教授が教える、夫婦関係改善のためのコミュニケーション技法。相手も自分も大切にする自己表現で、在宅勤務のストレスを解消。
¥2,200(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
在宅勤務で妻が感じる3つの見えないストレス
1. 「見えない家事」の負担増加
内閣府の2022年調査では、テレワーク実施率が34.6%に達していますが、同時に家庭内の新たな問題も浮き彫りになっています。
妻が感じるストレスの最大要因は「見えない家事」の増加です。
実際のデータを見てみると:
- 昼食の準備・片付け(1日1時間増加)
- コーヒーやお茶の準備(1日5〜10回)
- 仕事部屋の掃除・整理(週2〜3回追加)
- 宅配便の対応(在宅なのに夫は出られない)
私の妻も同じように感じていました。「在宅なのに家事は増えるばかり」という矛盾に、日々ストレスを募らせていたのです。
2. 曖昧になる「仕事」と「家庭」の境界線
在宅勤務の夫を持つ妻の多くが感じる不満:
「家にいるのに、なぜ子供の面倒を見てくれないの?」
これは単なるわがままではありません。物理的に家にいる夫を見ながら、育児の負担が変わらない(むしろ増える)という状況は、妻にとって理不尽に感じられるのです。
野末武義教授は『夫婦・カップルのためのアサーション』の中で、この問題を「役割期待のずれ」と表現しています。
「在宅勤務により夫婦の物理的距離が近くなった分、心理的距離の調整が重要になっている」(p.124)
3. コミュニケーション不全による孤独感
皮肉なことに、夫が家にいる時間が増えたにも関わらず、妻の孤独感が増すケースが多いのです。
理由は明確です:
- 夫は「仕事モード」で会話が減る
- 妻の話を聞く余裕がない(会議の合間など)
- 「今忙しい」が口癖になる
私自身、会議と会議の間の5分休憩で妻に話しかけられても、頭が仕事モードから切り替わらず、生返事をしていました。妻からすれば「目の前にいるのに心は不在」という最悪の状況だったのです。
妻のストレスを解消する「アサーション」3つの実践法
実践法1:「Iメッセージ」で感情を共有する
『夫婦・カップルのためのアサーション』で最も効果的だったのが「Iメッセージ」という技法です。
従来の伝え方(You メッセージ):
- 「(あなたは)全然家事を手伝ってくれない」
- 「(あなたは)子供の面倒を見ない」
Iメッセージでの伝え方:
- 「私は一人で家事をしていると疲れを感じる」
- 「私は育児のサポートが欲しいと思っている」
実践してみた結果、妻との会話がこう変わりました:
妻:「私、在宅勤務が始まってから昼食の準備で1日が中断されて、自分の時間が取れなくて辛いの」 私:「そうか、僕の昼食で君の時間を奪ってたんだね。週3日は自分で用意するよ」
攻撃的にならず、でも自分の気持ちをしっかり伝える。これがアサーションの本質です。
実践法2:「役割期待」の見える化
野末教授が提唱する「役割期待のすり合わせ」を実践しました。
具体的には、A4用紙を2枚用意して:
妻が書いた「在宅勤務中の夫への期待」:
- 昼休みは子供と10分遊ぶ
- 宅配便は可能な限り対応
- 18時以降は家族時間
私が書いた「在宅勤務中にできること」:
- 朝の保育園送りは担当
- 15時の休憩で洗濯物取り込み
- 金曜は昼食を自分で用意
お互いの期待値を可視化することで、「なんとなく期待していたけど伝わっていなかった」ことが明確になりました。
データによると、このような期待値の調整を行った夫婦の87%が「関係性が改善した」と回答しています。
実践法3:「心理的境界線」の設定
物理的に同じ空間にいても、心理的な境界線を作ることが重要です。
我が家で導入した3つのルール:
-
ドアの開閉ルール
- ドアが閉まっている=仕事中(緊急時以外NG)
- ドアが半開き=声かけOK(5分以内)
- ドアが全開=家族モード
-
タイムゾーン制
- 9-12時:集中タイム(妻も自分の時間)
- 12-13時:家族ランチ(可能な日のみ)
- 17時以降:段階的に家族モードへ
-
週1回の夫婦会議
- 金曜夜20分間
- その週のストレスポイントを共有
- 翌週の改善案を一緒に考える
実践1ヶ月で起きた驚きの変化
アサーション技法を取り入れて1ヶ月。我が家に起きた変化を数値化してみました:
- 夫婦喧嘩の頻度:週3回→週0.5回(83%減少)
- 妻の家事負担感:10段階中8→5(37.5%改善)
- 夫婦の会話時間:1日15分→45分(3倍増加)
- 妻の表情:笑顔が明らかに増えた(数値化できないけど最重要)
特に印象的だったのは、妻からの言葉です。
「在宅勤務って最初は地獄だと思ってたけど、今はむしろ良かったかも。あなたがどんな仕事をしているか分かるようになったし、休憩時間に顔を見られるのは嬉しい」
在宅勤務のストレスを解消する実践的な方法では、働く側の視点でストレス解消法が紹介されていましたが、今回の経験で「妻の視点」がいかに重要かを痛感しました。
また、リモートワークで家族をチームにする戦略でも触れられているように、家族全体でルールを作ることが大切です。
今すぐ始められる3つのアクションプラン
ステップ1:今夜、妻の話を15分間聞く
スマホを置き、パソコンを閉じ、妻の目を見て話を聞く。 ただそれだけです。アドバイスは不要。「うんうん」「そうだったんだ」「大変だったね」の3フレーズで十分。
実践のコツ:
- タイマーを15分セット(時間を決めることで集中できる)
- 「今日はどんな1日だった?」から始める
- 解決策を提案しない(これが最重要)
ステップ2:週末に「役割期待」の棚卸し
上記で紹介したA4用紙のワークを実践。 お互い10個ずつ書いて、実現可能な3個を選ぶ。
注意点:
- 完璧を求めない(60点で合格)
- 「できない」ではなく「代替案」を考える
- 1ヶ月後に見直すことを前提に
ステップ3:月曜朝に「Iメッセージ」練習
週の始まりに1つだけ、Iメッセージで要望を伝える練習をする。
例:
- 「私は月曜の朝はゆっくりしたいから、朝食は各自で用意してもらえると嬉しい」
- 「私は週の前半は仕事が忙しいから、水曜までは夕食を簡単なものにしたい」
これを続けることで、自然とアサーティブなコミュニケーションが身につきます。
妻のストレスは「甘え」ではない
厚生労働省の2023年調査では、仕事関連のストレスを感じる労働者が82.7%に上ります。
でも、在宅勤務における妻のストレスは、この統計には表れません。「見えない労働」「評価されない貢献」として、データの外側に存在しているのです。
私たち夫は、この「見えないストレス」に気づき、向き合う責任があります。
在宅勤務は、夫婦関係を見直す絶好の機会でもあります。物理的に近くにいる今だからこそ、心理的な距離も縮められるはずです。
まとめ:在宅勤務を夫婦の絆を深めるチャンスに
34%の妻が夫を「鬱陶しい」と感じる現実。 でもこれは、裏を返せば66%の夫婦は在宅勤務でも良好な関係を保っているということ。
その差は、コミュニケーションの質にあります。
『夫婦・カップルのためのアサーション』が教えてくれたのは、「相手も自分も大切にする」という当たり前だけど忘れがちな原則でした。
在宅勤務3年目の今、私は確信を持って言えます。 妻のストレスに向き合うことは、結果的に自分のストレスも減らし、家族全体の幸福度を上げることにつながると。
データが示す34%の「鬱陶しい夫」から脱却し、妻に愛される在宅勤務者になる。 そのための第一歩は、今夜妻の話を15分間聞くことから始まります。
最後に、野末教授の言葉を引用させていただきます。
「夫婦関係の改善に『遅すぎる』ことはありません。今この瞬間から、新しいコミュニケーションを始められます」
在宅勤務という新しい働き方に、新しい夫婦関係を。 そのヒントが、この本には詰まっています。
著者: 野末武義
明治学院大学心理学部教授が教える、夫婦関係改善のためのコミュニケーション技法。在宅勤務のストレスを、夫婦の絆を深めるチャンスに変える実践的ガイド。
¥2,200(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp