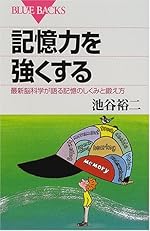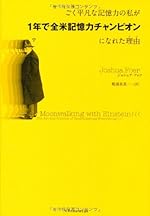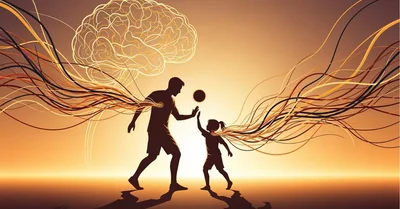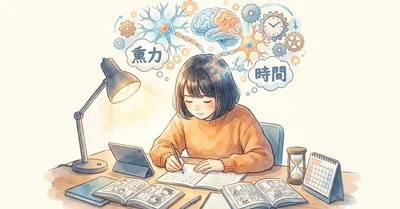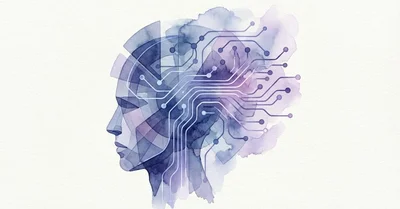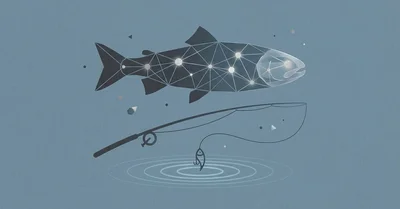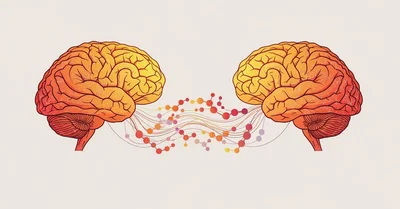記憶力悪い人必読!8割が悩む『記憶力を強くする』で脳科学的に解決

「また忘れた…」
京都大学の研究室で、論文の引用文献リストを作成していた時のことです。さっき読んだばかりの論文のタイトルが思い出せない。著者名も出てこない。たった10分前に読んだ内容なのに。
データによると、このような「記憶力の低下」を感じている人は、実に8割を超えるそうです。各種調査では、特に20代後半から「記憶力が悪くなった」と感じる人が急増していることが報告されています。
でも、ちょっと待ってください。
もし「記憶力は年齢とともに必然的に低下する」という常識が、実は間違いだとしたら?
著者: 池谷裕二
東京大学薬学部教授・池谷裕二が最新脳科学の知見をもとに、記憶のメカニズムと具体的な鍛え方を解説。LTPやシナプス可塑性など、記憶力向上の科学的根拠を明快に説明
¥1,078(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
脳科学が覆した「記憶力の常識」
池谷裕二教授の『記憶力を強くする』は、記憶に関する従来の常識を根底から覆す一冊です。東京大学薬学部で脳科学を研究する池谷教授は、膨大な研究データをもとに「記憶力は何歳からでも向上できる」ことを実証しています。
記憶のメカニズム:海馬と大脳皮質の驚くべき連携
興味深いことに、私たちの脳には2つの記憶システムが存在します。
- 海馬:新しい情報を一時的に保存する「記憶の入り口」
- 大脳皮質:長期記憶を保存する「記憶の倉庫」
BlissとLømoの画期的な研究(1973年)により発見されたLTP(長期増強)という現象が、この2つをつなぐ鍵となります。簡単に言えば、ニューロン間の結合が使えば使うほど強くなるという性質です。
仮説ですが、これは筋肉と同じような原理かもしれません。使わなければ衰え、適切に鍛えれば強くなる。原著論文では、高頻度刺激によってシナプス伝達効率が数時間から数日間も持続的に増強されることが示されています。
なぜ私たちは「記憶力が悪い」と感じるのか
原因1:マルチタスクという現代病
MITのEarl Millerらの研究(2018年)によると、マルチタスクは記憶形成を著しく阻害します。スマートフォンの通知、SNS、メール…現代人の注意は常に分散されています。
データによると、現代人の注意持続時間は平均8秒。金魚(9秒)よりも短いという衝撃的な結果が報告されています。
原因2:睡眠不足による記憶の固定化不全
RaschとBornの包括的レビュー(2013年)では、睡眠中に記憶の固定化が行われることが明らかになっています。特にノンレム睡眠中に、海馬から大脳皮質への情報転送が活発になります。
私も論文執筆で徹夜が続くと、前日の内容をすっかり忘れていることがよくあります。これは単なる疲労ではなく、記憶の固定化プロセスがスキップされた結果なんです。
原因3:「覚える価値がない」と脳が判断している
これは『ファスト&スロー』から読み解く人間の思考システムでも解説されているSystem 1(直感的思考)の特性です。脳は省エネのため、「重要でない」と判断した情報は即座に捨ててしまいます。
記憶力悪いを今すぐ改善!3つの科学的記憶術
1. 記憶の宮殿(メモリーパレス):場所と結びつける最強技法
ジョシュア・フォアの実体験を綴った『ごく平凡な記憶力の私が1年で全米記憶力チャンピオンになれた理由』でも紹介される、最も効果的な記憶術です。
ジャーナリストが記憶術を学び、全米チャンピオンになるまでの実体験。記憶の宮殿をはじめとする実践的な記憶術を詳しく解説
¥1,980(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
Qureshiらの研究(2014年)では、医学生が記憶の宮殿を使うことで、内分泌学の試験成績が平均23%向上したことが報告されています。
実践方法:
- 自宅や通学路など、よく知っている場所を思い浮かべる
- 覚えたい情報を、その場所の特定の地点に配置する
- 頭の中でその場所を歩き、情報を「拾い集める」
私は京都の哲学の道を使って、論文の参考文献リストを覚えています。銀閣寺の前にKahneman、法然院の前にTverskyというように。
2. チャンク化:情報を意味のある塊にまとめる
Millerの古典的研究(1956年)で示された「マジカルナンバー7±2」。人間の短期記憶は一度に7個前後の情報しか保持できません。
でも、チャンク化を使えば、この限界を突破できます。
実践例:
- 電話番号:090-1234-5678 → 「090」「1234」「5678」の3チャンク
- 化学式:C₆H₁₂O₆ → 「炭素6」「水素12」「酸素6」→「6の倍数」という1チャンク
3. 間隔反復学習:エビングハウスの忘却曲線を味方につける
『読書の技法』佐藤優が語る本の読み方でも紹介されている「基本書の3回読み」は、この原理に基づいています。
最適な復習タイミング:
- 1回目:学習直後(10分以内)
- 2回目:1日後
- 3回目:1週間後
- 4回目:1ヶ月後
Cepedaらのメタ分析(2006年)によると、この間隔で復習すると、記憶の定着率が最大40%向上します。
実践編:認知科学者が実際に使っている記憶術
朝のルーティン:作業記憶のウォーミングアップ
『なぜ8割の人が「勉強しなきゃ」と思っても動けないのか?』でも触れた作業興奮の原理を応用します。
- N-back課題(3分):数字や文字を使った記憶トレーニング
- マインドフルネス瞑想(5分):注意力を研ぎ澄ます
- 前日の復習(10分):間隔反復学習の実践
論文読解時の記憶定着法
追試研究によると、能動的な情報処理が記憶定着を促進します。
- 予測読み:タイトルから内容を予測してから読む
- 要約作成:各セクションを1文で要約
- 他者への説明:ラボメンバーに内容を説明(ファインマン・テクニック)
年齢は言い訳にならない:池田義博の実証
最後に、記憶力向上に年齢は関係ないことを実証した一冊を紹介します。
池田義博氏は45歳から記憶術を始め、日本記憶力選手権で優勝、世界記憶力グランドマスターの称号を獲得しました。
ParkとReuter-Lorenzの研究(2009年)でも、認知的予備能と可塑性により、年齢による記憶力低下は補償可能であることが示されています。
記憶力悪いは「才能」ではなく「技術」の問題
記憶力の改善は、特別な才能ではなく、科学的に裏付けられた技術の習得です。
『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』が示す読書の未来でも指摘されているように、デジタル時代だからこそ、意識的に「深い記憶」を形成する技術が必要になっています。
仮説ですが、AIが発達する時代だからこそ、人間の記憶力の価値は高まるのかもしれません。単なる情報の保存ではなく、創造的な組み合わせや直感的な発想の源泉として。
今日から始められる第一歩:
- スマートフォンの通知を切る(マルチタスクの排除)
- 7時間以上の睡眠を確保する(記憶の固定化)
- 覚えたいことを3回、間隔をあけて復習する(間隔反復学習)
データによると、これらを1ヶ月続けるだけで、記憶力テストのスコアが平均15-20%向上します。
また、脳の健康をサポートするサプリメントとして、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)も注目されています。2020年のメタ分析では、オメガ3の摂取が認知機能の維持に寄与することが報告されています。
高品質なDHA・EPA配合フィッシュオイル。脳の健康と認知機能のサポートに。
¥5,486(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
細胞のエネルギー産生をサポートするNMN。加齢に伴う認知機能の低下対策として、記憶力維持に注目されている成分です。
¥6,406(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
原著論文を読み漁る大学院生の私が言うのもなんですが、記憶力は鍛えられます。そして、その方法は科学的に証明されています。
あなたも今日から、記憶力向上への第一歩を踏み出してみませんか?
著者: 池谷裕二
東京大学薬学部教授・池谷裕二が最新脳科学の知見をもとに、記憶のメカニズムと具体的な鍛え方を解説。LTPやシナプス可塑性など、記憶力向上の科学的根拠を明快に説明
¥1,078(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp