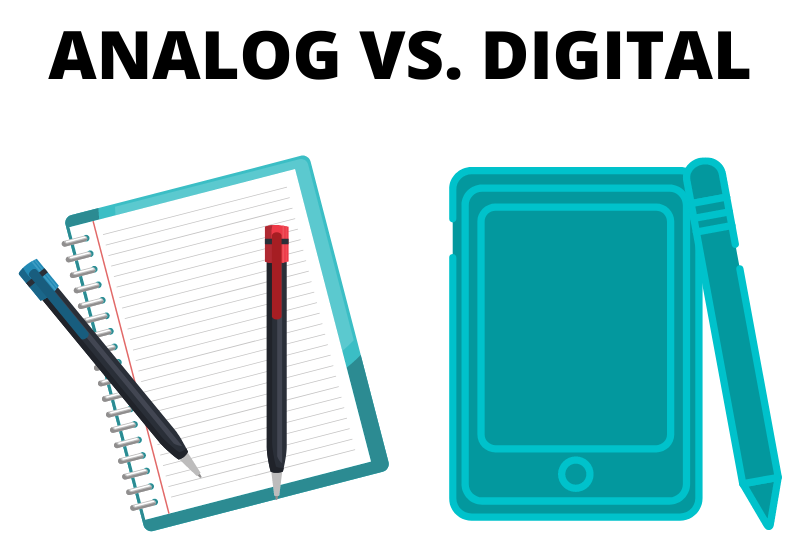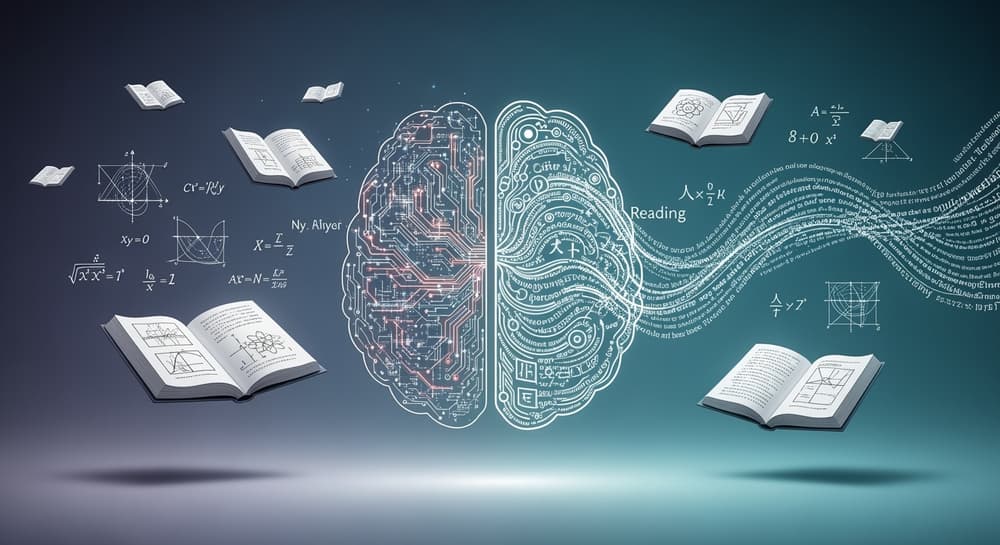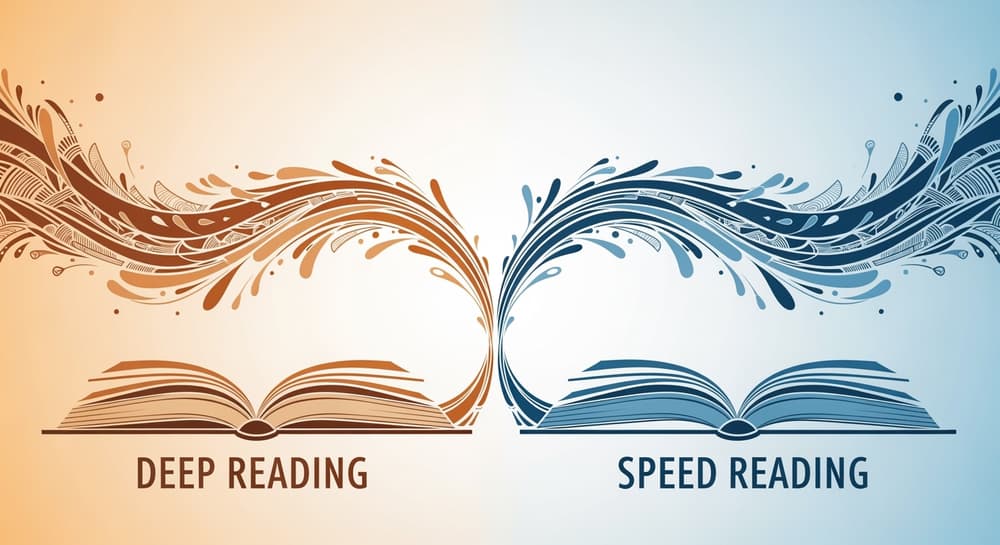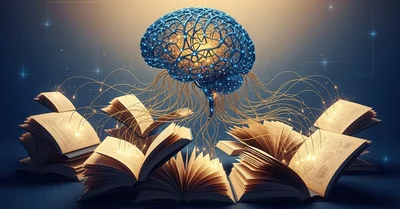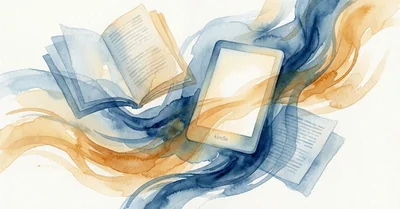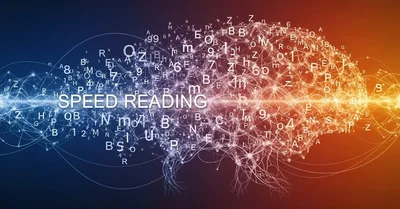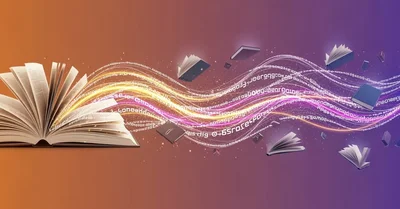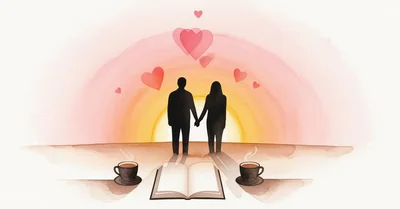『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』が示す読書の未来:編集長が考えるバイリテラシー時代
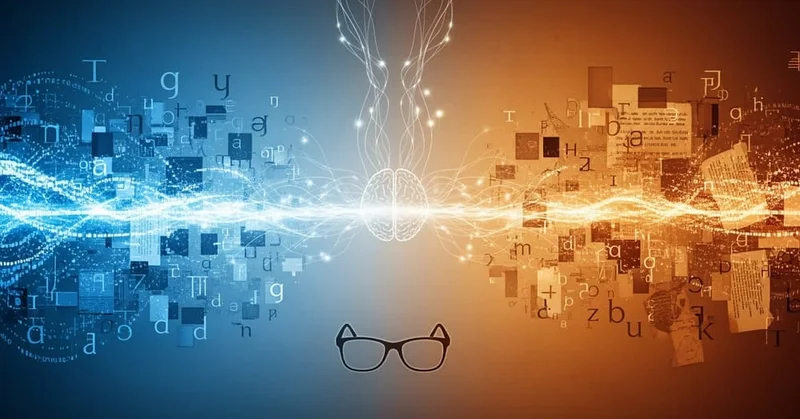
出版業界20年の変化を振り返って
編集者として大手出版社で働き始めてから、もう20年が経ちました。その間に見てきた変化は、まさに革命的と言えるものでした。
2004年、私が入社した頃は、まだ紙の原稿を赤ペンで校正していた時代。それが今では、原稿のやり取りはすべてデジタル、校正もPDF上で行うことが当たり前になりました。電子書籍の売上が全体の3割を超える出版社も珍しくありません。
年間200冊以上読む私自身の読書スタイルも、この20年で大きく変わりました。通勤電車ではスマートフォンでビジネス書を流し読みし、週末は紙の文学作品にじっくりと向き合う。5歳の息子には紙の絵本を読み聞かせながら、仕事の資料はタブレットで確認する日々です。映画化された作品は必ず原作も読むようにしていますが、最近では原作を電子で速読してから、映画館で観て、気に入ったら紙の本でじっくり読み返すという三段階の楽しみ方をしています。
そんな中で出会ったのが、認知神経科学者メアリアン・ウルフの『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』でした。この本は、私が漠然と感じていた違和感に、科学的な裏付けを与えてくれたのです。
認知神経科学者メアリアン・ウルフが明かす、デジタル時代の読書と脳の関係。『プルーストとイカ』の続編として、バイリテラシーという新しい読書能力の必要性を説く話題作。
¥2,420(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
本書の核心:バイリテラシーという新概念
『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』で、ウルフが提唱する最も重要な概念が「バイリテラシー(biliteracy)」です。これは、デジタルと紙の両方の読み書き能力を指します。
「深い読み」とは何か
ウルフによれば、読書には大きく分けて2つのモードがあります。
- 表層的な読み(スキミング):情報を素早く処理し、要点だけを把握する読み方
- 深い読み(ディープ・リーディング):じっくりと文章に向き合い、行間を読み、想像力を働かせ、批判的に思考する読み方
デジタル機器での読書は、その特性上、どうしても「表層的な読み」に偏りがちです。ハイパーリンクやプッシュ通知、無限にスクロールできる画面は、私たちの注意を分散させ、深く考える時間を奪ってしまうのです。
デジタル時代だからこそ必要な能力
しかし、ウルフはデジタル読書を否定しているわけではありません。むしろ、現代社会においてデジタル読書のスキルは必須だと述べています。問題は、デジタル読書「だけ」になってしまうことなのです。
研究によると、デジタルネイティブ世代の子どもたちは、情報処理速度は向上している一方で、深い理解力や共感力、想像力といった能力が低下している傾向があります。これは、脳の可塑性という観点から見ると、当然の結果とも言えます。
科学が証明する驚きの事実
編集者として論文を読むことも多い私にとって、『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』で紹介されている研究結果は衝撃的でした。
東大研究が示す記憶定着の差
東京大学の2021年の研究では、紙に書いた情報と、デジタル機器に入力した情報を1時間後に思い出す実験を行いました。その結果、紙に書いた情報を思い出す際の脳活動、特に記憶に関与する海馬での活動が、デジタル入力時よりも顕著に活発だったのです。
これは、紙という物理的な媒体が、脳内に「空間的な記憶の手がかり」を作るためだと考えられています。ページの右上に書いてあった、左下の余白にメモした、といった空間的な情報が、記憶の検索を助けるのです。
メタ分析が示す理解度の差
さらに驚くべきは、複数の研究を統合したメタ分析の結果です。Furenes et al. (2021)の研究では、39の研究を分析し、紙で読んだ場合の理解度が電子書籍よりも一貫して高いことを明らかにしました。
研究によると、この差が最も顕著に現れるのは「説明文」や「論説文」といった、深い理解を必要とする文章だそうです。つまり、私たちが仕事で扱うような企画書や報告書、学術的な文章こそ、紙で読むべきだということです。一方で、小説やエンターテインメント的な文章では差が小さくなる傾向があるため、娯楽的な読書ならデジタルでも問題ないでしょう。
脳波が明かす集中力の違い
2024年の最新研究では、脳波(EEG)を使って読書中の脳活動を測定しました。その結果、紙で読む際にはベータ波とガンマ波が高く、認知的関与と注意力が高い状態であることが分かりました。一方、画面で読む際にはアルファ波とシータ波が高く、リラックスはしているものの、注意力は低下している状態でした。
論文では、この現象を『ファスト&スロー』で説明される思考システムの観点から分析しています。デジタル読書はSystem 1(直感的思考)に偏りがちで、紙の読書はSystem 2(論理的思考)を活性化させやすいのです。
編集長の実践:ハイブリッド読書法
これらの研究結果を踏まえて、私は自分なりの「ハイブリッド読書法」を実践しています。
仕事での使い分け
編集者としての仕事では、内容に応じて明確に使い分けています。企画書や速報的な情報については、タブレットやPCで素早くチェックし、効率性を重視しています。しかし、原稿の精読や校正作業については、必ず紙に印刷して赤ペンでチェックするようにしています。これは経験上、画面上では見落としがちな細かなミスや文章の流れを、紙の方が正確に把握できるからです。参考文献の調査では、デジタルで幅広く検索した後、重要と思われるものは印刷して熟読するという二段階のアプローチを採用しています。
実際、紙で原稿を読むと、画面では気づかなかった矛盾や違和感に気づくことが多いのです。これは、私の経験則だけでなく、科学的にも裏付けられた現象だったわけです。
5歳の息子との読書体験
子育てにおいても、この知識は大いに役立っています。5歳の息子には、基本的に紙の絵本を読み聞かせています。先日、『ぐりとぐら』を読んでいたとき、息子が「パパ、このページのカステラ、昨日も見たよね?」と言って、前のページに戻って確認する姿を見て、はっとしました。これこそが、研究でいう「空間的記憶」なのです。ページの位置と内容が、彼の小さな脳の中で結びついているのです。
ただし、デジタルデバイスを完全に排除するわけではありません。例えば、動物の鳴き声が聞ける図鑑アプリや、インタラクティブな学習アプリも活用しています。重要なのは、それぞれの特性を理解して、適切に使い分けることなのです。寝る前の読み聞かせは必ず紙の絵本、朝の忙しい時間にはタブレットで短い動画付き絵本、というように、生活リズムに合わせて使い分けています。
『AIvs読解力』生成AI時代だからこそ求められる深い理解力でも論じられているように、これからの時代は情報を素早く処理する能力と、深く理解する能力の両方が求められます。バイリテラシーは、まさにその両立を可能にする鍵となるでしょう。
効率と深さを両立させる方法
私の一日は、朝のコーヒーと紙の本から始まります。この30分間は、スマートフォンを別室に置き、完全に本の世界に没頭する贅沢な時間です。最近では村上春樹の新作を、この朝の時間を使って2週間かけて読みました。ページをめくるたびに、紙の匂いと手触りが、学生時代に戻ったような感覚を呼び起こしてくれます。
通勤電車では電子書籍で新刊をチェックし、気に入った本は紙でも購入して週末にじっくり読み返すようにしています。実は先日、デジタル校正で見逃してしまった誤字を、後日紙で読み返したときに発見するという恥ずかしい経験をしました。論文でも証明されているとおり、やはり紙の方が細部への注意力が高まるようです。
重要な本には必ず物理的な痕跡を残すようにしています。付箋を貼り、線を引き、余白にメモを書く。私の本棚にある愛読書は、まるで戦場から帰還した戦士のように、付箋だらけでボロボロです。でも、それが愛着であり、記憶の定着を助けてくれているのです。
読書の未来への提言
テクノロジーを味方につける読書術
ウルフの主張で重要なのは、デジタルvs紙という二項対立ではないということです。むしろ、両方の長所を活かす「バイリテラシー」こそが、これからの時代に必要な能力なのです。
例えば、最近では興味深い技術的な工夫も生まれています。E-inkディスプレイの進化により、従来の液晶画面よりもはるかに紙に近い読書体験を提供できるようになりました。また、文部科学省の実証研究で行われているデジタル教科書の取り組みでは、紙の教科書との併用を前提とした設計になっており、まさにバイリテラシーの考え方が反映されています。さらに、読書記録アプリの活用により、読んだ本の記録や感想を残すことで記憶の定着を促進する試みも注目されています。
出版業界が進むべき道
編集者として、出版業界にはいくつかの重要な取り組みが必要だと感じています。実は、『読書の技法』で佐藤優が語る知的生産術でも触れられていますが、情報の取捨選択と深い理解の両立こそが、現代の読書に求められる技術なのです。
まず最も重要なのは、紙と電子のセット販売の推進です。同じ本を両方の形態で提供し、読者が状況に応じて使い分けられるようにすることで、真のバイリテラシーを支援できるでしょう。また、「深い読み」を促す電子書籍の開発も急務です。通知を切る「集中モード」や、意図的にゆっくりとしたページめくり機能を実装することで、デジタルでも深い読書体験を実現できるはずです。
さらに、出版業界全体で読書教育への貢献を強化し、学校や図書館と連携してバイリテラシー教育を支援していく必要があります。これは単なる社会貢献ではなく、未来の読者を育てる投資でもあるのです。
読者一人ひとりができること
最後に、読者の皆さんに3つの提案をさせていただきます。
まず、意識的に「深い読み」の時間を作ることが重要です。1日30分でも構いません。デジタルデバイスから離れて紙の本と向き合う時間を作ることで、脳の深い読みの回路を活性化できます。私自身、朝のコーヒータイムをこの時間に充てており、その効果を実感しています。
次に、読書の目的に応じて媒体を意識的に選択することです。情報収集や速読が目的ならデジタル、じっくりと考えを深めたい内容なら紙、というように使い分けることで、それぞれの特性を最大限に活かせるでしょう。
そして何より重要なのは、子どもたちに両方の読書体験を提供することです。デジタルネイティブ世代だからこそ、紙の本が持つ独特の価値を知ってもらう必要があります。私が5歳の息子に紙の絵本を読み続けているのも、この理由からです。
知識は実践してこそ価値がある
『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』を読んで、私は改めて読書の奥深さを認識しました。デジタル化は避けられない流れですが、だからこそ、紙の本が持つ価値を再認識し、両方をバランスよく活用することが重要なのです。
研究によると、私たちの脳は驚くほど柔軟で、使い方次第で変化します。バイリテラシーを身につけることは、単に読書スキルを向上させるだけでなく、思考力、想像力、共感力といった、人間として大切な能力を育むことにつながるのです。
知識は実践してこそ価値がある。これは私の座右の銘ですが、まさに読書においても同じことが言えるでしょう。『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』が示す未来は、どちらか一方を選ぶのではなく、両方の良さを活かす豊かな読書文化なのです。
認知神経科学者メアリアン・ウルフが明かす、デジタル時代の読書と脳の関係。編集者として、親として、読書家として、すべての人に読んでほしい一冊です。
¥2,420(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
読書と脳科学に関連する記事として、以下もおすすめです。