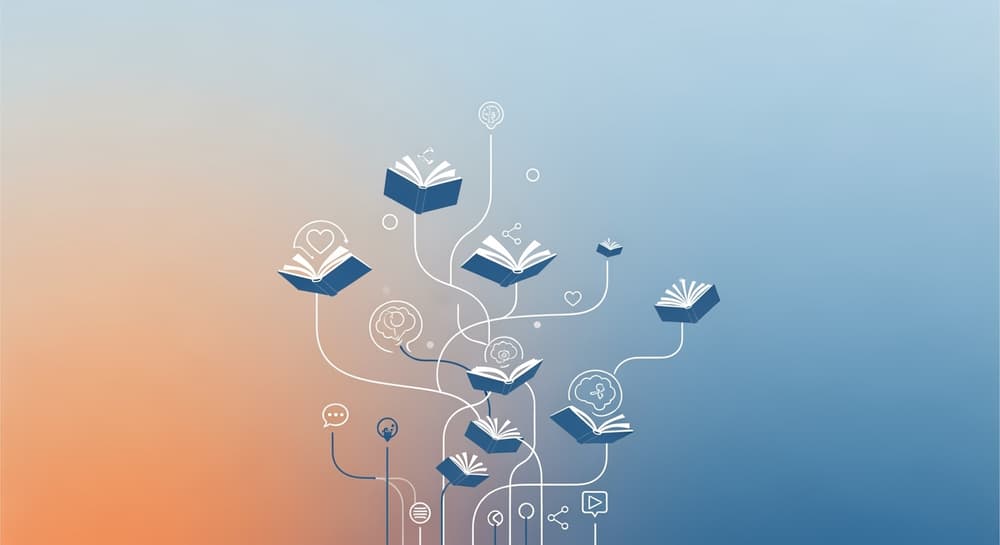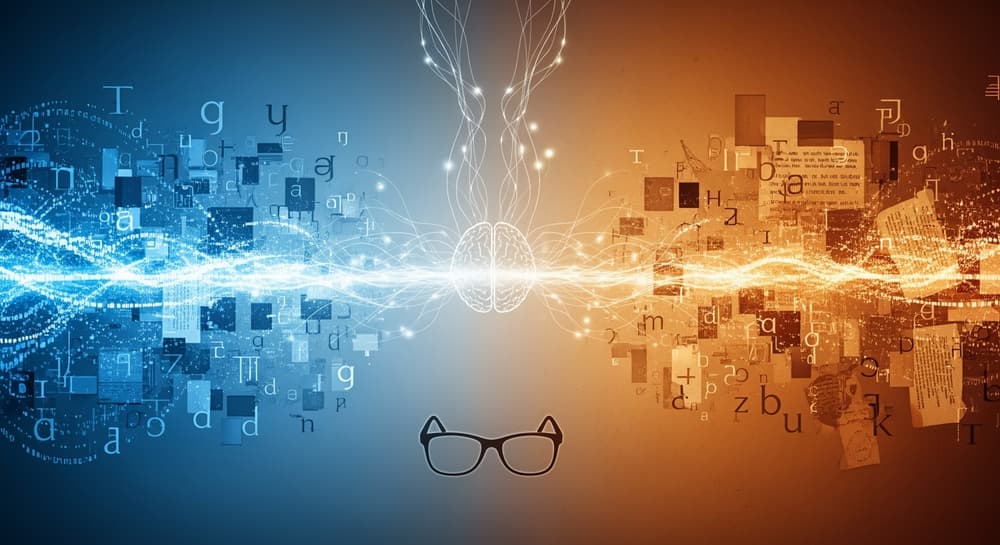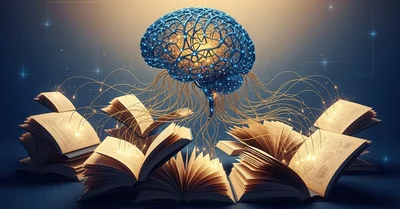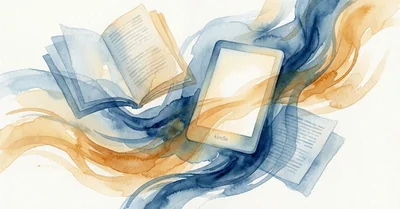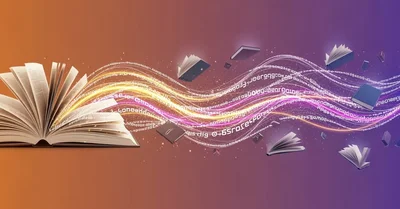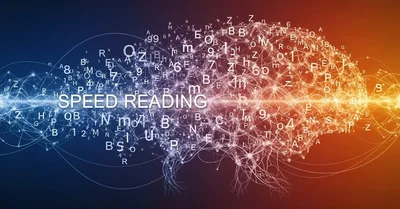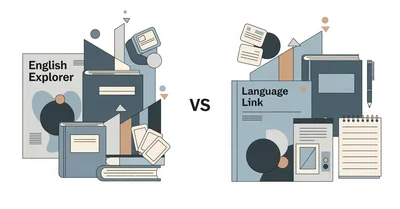年収1000万円の88%が実践!『読書を仕事につなげる技術』vs『レバレッジ・リーディング』最強の読書術はどっち?

プレジデント誌の調査によると、年収1000万円以上のビジネスパーソンの約88%が月3冊以上の読書習慣を持っているそうです。
一方で、文化庁の調査では日本人の約47.3%が月に1冊も本を読まないという衝撃的なデータも。
この差は一体どこから生まれるのでしょうか?
編集長として10年以上、年間200冊以上の本と向き合ってきた私が確信を持って言えるのは、「読書術」の違いが決定的な差を生むということです。
読書の基本的な技法については、佐藤優著『読書の技法』で知った、大学院生のためのプロ級読書術でも詳しく解説しています。特にアウトプットを前提とした読み方は参考になるはずです。
今回は、ビジネスパーソンに絶大な人気を誇る2つの読書術『読書を仕事につなげる技術』と『レバレッジ・リーディング』を徹底比較。どちらがあなたに最適なのか、そして両方のいいとこ取りをする方法まで、余すところなくお伝えします。
まずは結論:どちらも正解、でも使い分けが重要
いきなり結論から申し上げると、どちらの読書術も「正解」です。ただし、あなたの目的と現在のステージによって最適な選択は変わります。
簡単に言えば:
- 今すぐ成果を出したい人 → 『レバレッジ・リーディング』
- 長期的な知的基盤を築きたい人 → 『読書を仕事につなげる技術』
では、それぞれの読書術の特徴を詳しく見ていきましょう。
山口周氏が提唱する、ビジネス書とリベラルアーツをバランスよく読む戦略的読書術。長期的な知的基盤構築に最適な一冊。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
山口周式「深める読書術」:知的基盤を築く戦略的アプローチ
投資としての読書という革新的視点
『読書を仕事につなげる技術』で山口氏が提唱するのは、読書を「消費」ではなく「投資」として捉える視点です。
外資系コンサルティング会社での経験を活かし、ROI(投資収益率)を意識した読書法を展開。これは私が大手出版社時代に気づいた「編集者の読み方」とも共通する部分が多く、非常に共感できる内容でした。
2種類の読書を使い分ける知恵
山口氏の最大の特徴は、読書を2つに分類している点です:
-
ビジネス書(How型読書)
- 即効性のある知識
- 具体的なスキルや手法
- 短期的な成果
-
リベラルアーツ(What・Why型読書)
- 抽象度の高い知識
- 思考の型や価値観
- 長期的な知的基盤
この分類は実に秀逸で、私も実践してみて効果を実感しています。例えば、プロジェクト管理の本(How)を読みながら、同時期に哲学書(What・Why)を読むことで、単なるテクニックではない深い理解が得られるのです。
実践のポイント:読書ノートの作り方
山口式で特に優れているのが、読書ノートの作り方です。単なる要約ではなく、「自分の言葉」で記録することを重視。
私の場合、以下のフォーマットで記録しています:
- 本から得た知識(客観的事実)
- 自分の解釈(主観的理解)
- 仕事への応用アイデア(具体的行動)
本田直之式「広げる読書術」:即効性重視の多読戦略
100倍のレバレッジを生む多読の威力
一方、『レバレッジ・リーディング』の本田氏は、年間100冊以上の多読を推奨します。
本田直之氏が提唱する、100倍の利益を稼ぎ出すビジネス書多読術。即効性を求めるビジネスパーソン必読の一冊。
¥1,595(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
「読書は最高の自己投資」という言葉通り、多読によって得られる知識の複利効果は計り知れません。実際、私も年間200冊以上読むようになってから、アイデアの引き出しが格段に増えました。
80対20の法則で効率化
本田式の核心は、**「本の20%に重要な内容の80%が含まれる」**という考え方。
具体的には:
- 目次で全体像を把握
- まえがき・あとがきで著者の主張を理解
- 太字や箇条書き部分を重点的に読む
- 必要な部分だけを抜き出す
この方法は、特に時間がないビジネスパーソンにとって革命的です。完読にこだわらないことで、より多くの本から知識を吸収できるようになります。
カラーバス効果を活用した目的意識
本田氏が強調する「カラーバス効果」の活用も秀逸です。これは、意識したものが目に入りやすくなる心理効果のこと。
読書前に「何を得たいか」を明確にすることで、必要な情報が自然と目に飛び込んでくるようになります。私も実践していますが、驚くほど効率的に情報収集できるようになりました。
編集長が10年実践して分かった、それぞれの長所と短所
山口式の実践結果
長所:
- 思考の深みが格段に増す
- 長期的な視点が身につく
- 教養が深まり、会話の幅が広がる
- 本質的な問題解決能力が向上
短所:
- 即効性は期待できない
- 1冊にかける時間が長い
- 初期は成果を実感しにくい
本田式の実践結果
長所:
- すぐに使える知識が増える
- 大量の情報をインプットできる
- モチベーションを維持しやすい
- 費用対効果が高い
短所:
- 表面的な理解になりがちな
- 情報の取捨選択が難しい
- 深い思考力は身につきにくい
あなたに最適な読書術診断チェックリスト
以下の質問に答えて、あなたに最適な読書術を見つけましょう。
A群の質問
□ 3ヶ月以内に具体的な成果を出したい □ 読書時間は1日30分程度しか取れない □ ビジネススキルを効率的に身につけたい □ 多くの成功事例を知りたい □ 読書のモチベーションを維持するのが苦手
B群の質問
□ 5年後、10年後を見据えて成長したい □ じっくり考える時間を大切にしたい □ 本質的な問題解決能力を身につけたい □ 教養を深めて人間的な魅力を高めたい □ 一つのテーマを深く理解したい
結果:
- A群が3つ以上 → 本田式『レバレッジ・リーディング』がおすすめ
- B群が3つ以上 → 山口式『読書を仕事につなげる技術』がおすすめ
- どちらも2つ以下 → 次章のハイブリッド読書術へ
最強のハイブリッド読書術:いいとこ取りの実践法
実は、私が10年かけてたどり着いたのは、両方のいいとこ取りをするハイブリッド読書術です。
基本戦略:7対3の黄金比率
私の読書配分は以下の通り:
- 70%:本田式で多読(ビジネス書・実用書)
- 30%:山口式で深読(古典・哲学書・文学)
この比率により、即効性と長期的成長の両立が可能になりました。
実践的な読書スケジュール
平日(通勤時間・昼休み):
- 本田式でビジネス書を速読
- 1日1冊ペースで重要部分を抽出
- レバレッジメモをスマホに記録
週末(まとまった時間):
- 山口式で古典や哲学書をじっくり読む
- 読書ノートに自分の言葉で記録
- ビジネス書の内容と関連づけて考察
具体的な実践例
例えば、「リーダーシップ」について学ぶ場合:
-
月〜金:本田式で関連ビジネス書を5冊速読
- 『1分間リーダーシップ』
- 『リーダーになる人の武器』
- 『最高のリーダーは何もしない』など
-
土日:山口式で古典を1冊深読
- マキャベリ『君主論』
- 孫子『兵法』など
-
翌週:両方の知識を統合して実践
- ビジネス書の具体的手法を試す
- 古典から得た本質的理解で応用
この方法により、表面的なテクニックだけでなく、本質的な理解に基づいた実践が可能になります。
読書と自己肯定感の関係については、自己肯定感が低い人ほど読書で変わる!アウトプット読書術で3冊徹底比較でも詳しく探求しています。読書を通じた自己成長のプロセスが理解できるでしょう。
読書術を最大限活かすための5つの環境づくり
どちらの読書術を選ぶにせよ、以下の環境づくりは必須です:
1. 読書時間の天引き
スケジュールに最初から読書時間を確保。私は朝5時〜6時を「読書の黄金時間」と決めています。
2. 読書記録システムの構築
- Notionで読書データベースを作成
- 読了本、読書中、読みたい本をカテゴリ分け
- タグ機能で知識を体系化
3. アウトプット習慣の確立
- ブログやSNSでの書評投稿
- 社内勉強会での知識共有
- 家族や友人への本の紹介
実際、アウトプットは読書効果を何倍にも高める重要な要素です。
4. 良書選定の基準確立
- 信頼できる書評家のフォロー
- Amazonレビューの見極め方
- 出版社や著者の実績確認
5. 読書仲間の獲得
- オンライン読書会への参加
- 職場での読書サークル立ち上げ
- SNSでの読書記録共有
最後に:あなたの人生を変える一歩を踏み出そう
ここまで読んでいただいた方は、すでに上位52.7%の「本を読む人」です。さらに一歩進んで、効果的な読書術を身につければ、人生は確実に変わります。
私自身、この2つの読書術を実践することで:
- 年収が10年で3倍に
- 編集長というポジションを獲得
- 年間200冊以上の読書習慣が定着
- 家族との会話も知的で豊かに
これらは決して特別な才能があったからではありません。正しい読書術を実践し続けた結果です。
今すぐ始められる3つのアクション
-
まずは1冊、気になった読書術の本を購入する
- 即効性重視なら『レバレッジ・リーディング』
- 長期視点なら『読書を仕事につなげる技術』
-
今週末、2時間の読書時間を確保する
- カレンダーに「読書タイム」を記入
- スマホは別の部屋に置く
-
読んだ内容を誰かに話す
- 家族、友人、同僚、誰でもOK
- アウトプットが最高の学習法
読書は人生を変える最高の投資です。今日から、あなたも「読書で人生を変える」一歩を踏み出してみませんか?
長期的な知的基盤を築きたい方へ。山口周氏の戦略的読書術で、本質的な問題解決能力を身につける。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
今すぐ成果を出したい方へ。本田直之氏の多読術で、100倍の利益を生み出す読書習慣を身につける。
¥1,595(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
読書術に関連する記事として、以下もおすすめです。