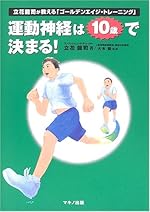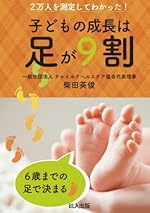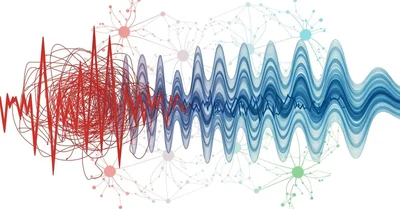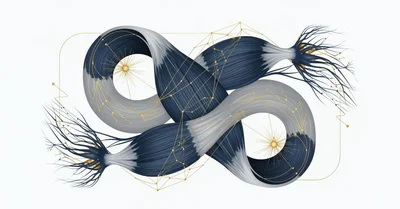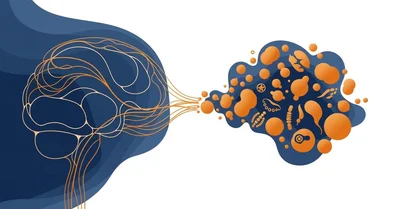私が子供の運動音痴を本気で変えた3冊!泣いてばかりだった娘が運動会で輝くまでの実体験記

娘の涙から始まった私の運動指導者への道
「パパ、私はどうして他の子みたいに走れないの?」
昨年の春、5歳になったばかりの長女みつきが、保育園から帰ってきてぽつりと呟いた言葉です。その日は保育園でかけっこの練習があったらしく、みつきはいつものように最下位だったそうです。私は娘の涙を見ながら、自分の無力さを痛感しました。
私自身も学生時代は運動が苦手で、「運動神経は遺伝だから仕方ない」と諦めていました。でも、娘の悲しそうな顔を見ていると、そんな諦めでは済まされない気持ちになったのです。
私は外資系コンサル時代に培ったデータ分析のスキルを活かして、子供の運動能力について徹底的に調べ始めました。そして驚くべき事実を発見したのです。スポーツ庁の調査によると、運動神経の遺伝的要因はたったの10%。残り90%は後天的な経験で決まるというのです。
その時、私は心に決めました。娘の運動能力を絶対に伸ばしてやる、と。
妻の美香も最初は半信半疑でしたが、「あなたがそこまで真剣なら協力するわ」と言ってくれました。2歳の長男けんたも、階段を降りるのを怖がる状態でしたが、私は家族全員で運動に取り組むことを決意したのです。
それから8ヶ月。今年の運動会で、みつきは見事に徒競走で2位になりました。けんたも公園の遊具で元気に遊んでいます。私が実践した3冊の本との出会いが、我が家の運動観を根本から変えてくれました。
元プロ野球選手の立花龍司氏が、スキャモンの発育曲線とゴールデンエイジ理論を基に、年齢別の最適なトレーニング方法を写真付きで解説。運動神経の90%が経験で決まることを科学的に証明する一冊。
¥1,430(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
私を変えた最初の一冊!立花龍司氏の「運動神経は10歳で決まる」
本屋で偶然見つけたこの本が、私の人生を変えました。子供の運動能力について調べていた私の目に飛び込んできたタイトルに、正直ドキッとしたのを覚えています。
本を開くと、人間の神経系は12歳までに95%が完成するという「スキャモンの発育曲線」の説明がありました。私は慌てました。みつきはもう5歳。時間があまり残されていないという焦りが襲ってきました。
でも、この本を読み進めると希望が見えてきました。立花龍司氏が元プロ野球選手の経験を活かして書いたトレーニング方法が、とても実践的だったのです。
私が最初にみつきと挑戦したのはボール投げでした。みつきは本当にボールを前に飛ばすことすらできませんでした。私も最初はイライラしてしまい、「どうして投げられないの?」と強い口調で言ってしまったこともあります。その時のみつきの悲しそうな顔を、私は今でも忘れることができません。
でも本書の「段階的練習法」を知って、私のアプローチは完全に変わりました。いきなり「投げて」と言うのではなく、まず「振る」動作から教える。私はみつきと一緒に、毎日10分間、公園でタオルを振る練習から始めました。
「みつき、今日はパパと一緒にタオルをブンブン振ってみよう!」 「うん、パパ!」
みつきの笑顔が戻ってきた瞬間でした。そして3週間後、みつきが初めてボールを10メートル先まで投げることができた時、私たち家族は抱き合って喜びました。妻も涙を流していました。
2歳のけんたには、この本のアドバイス通り、遊びを通じて基本動作を覚えてもらいました。私は毎週末、けんたと公園で鬼ごっこをするのが楽しみになりました。「パパ鬼だぞー!」と追いかけると、けんたのキャッキャッという笑い声が公園に響きます。私も童心に帰った気分でした。
足の専門家が教えてくれた衝撃の真実!私が見落としていた子供の足
延べ2万5千人の幼児の足を測定してきた柴田英俊氏が、足の発達と全身の運動能力の関係を科学的に解明。正しい靴選びから足のトラブル対策まで、実践的なアドバイスが満載。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
私が気づかなかった子供たちの足の異変
ボール投げが上達したみつきでしたが、私は別の問題に気づき始めました。みつきがよく転ぶのです。そして疲れやすい。30分も遊ぶとすぐに「疲れた」と言って座り込んでしまいます。
そんな時、妻が図書館で借りてきたのが柴田英俊氏の『子どもの成長は足が9割』でした。私は最初、「足なんて関係あるの?」と半信半疑でした。でも読み進めるうちに、背筋がゾッとしました。
現代の子供たちの足に深刻な問題が起きているというのです。私は慌ててみつきとけんたの足をチェックしました。すると、どちらも土踏まずがほとんど発達していませんでした。
「みつき、ちょっと足を見せて」 「どうしたの、パパ?」 「うーん、ちょっと気になることがあるんだ」
私はその夜、妻と真剣に話し合いました。足の発達不良は、バランス感覚の低下や疲れやすさにつながる。だからみつきは転びやすくて、すぐに疲れてしまうのかもしれない、と。
家族で取り組んだ足育チャレンジ
私は本書の方法を家族全員で実践することにしました。まず驚いたのは、みつきの靴のサイズが1.5cmも大きすぎたこと。靴屋さんで正確に測ってもらうと、私の予想と全然違っていました。
「え、そんなに小さいの?」妻も驚いていました。
適正サイズの靴に変えただけで、みつきの走り方が明らかに変わりました。以前は足音がペタペタしていたのが、軽やかになったのです。
次に始めたのが「足指じゃんけん」。これは本当に盛り上がりました。
「みつき、足でグーできる?」 「んー、できない!」 「けんたは?」 「できないー!」
みんなでお風呂上がりに足指じゃんけんをするのが、我が家の新しい習慣になりました。私も一緒にやってみましたが、これが意外に難しい!けんたは2週間で足指を自由に動かせるようになったのに、私はまだできません。子供の学習能力の高さを実感した瞬間でした。
週末の裸足タイムも始めました。近所の公園の芝生で、家族みんなで裸足になって遊ぶのです。最初は「気持ち悪い」と言っていたみつきも、慣れてくると「芝生、気持ちいい!」と言うようになりました。
子供の骨や筋肉の発達には、ビタミンDも重要な役割を果たします。特に室内で過ごす時間が長い子供は、日光浴の機会が少なく不足しがちです。
高含有ビタミンD3サプリ。子供の骨の健康と筋力発達をサポート。成長期のお子さんを持つ家庭に。
¥1,068(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
免疫力をサポートするビタミンC。子供の健康維持とコラーゲン生成を助け、活発に運動するお子さんの体づくりを応援します。
¥2,567(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
中野ジェームズ修一氏の本で我が家が変わった!
トップアスリートのトレーナーとして活躍する中野ジェームズ修一氏が、家庭で簡単にできる運動神経向上トレーニングを紹介。科学的根拠に基づいた効果的なメソッドが満載。
¥1,415(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
私の運動指導が劇的に変わった瞬間
みつきの足の問題が改善されてきた頃、私は更なる本との出会いを果たします。中野ジェームズ修一氏の『子どもの運動神経をグングン伸ばす スポーツの教科書』です。この本で、私の子供たちへの接し方が根本的に変わりました。
この本を読んで一番印象的だったのは、「遊び」の重要性でした。私は今まで、子供たちに「練習しよう」と言っていました。でもみつきは嫌がってしまう。なぜだろうと悩んでいた時に、この本が教えてくれました。子供は「練習」という言葉に拒否反応を示すけれど、「遊び」なら喜んで取り組む、と。
私は早速アプローチを変えました。「今日は特別なゲームをしよう!」という風に。
最初に挑戦したのは「ケンケンパ」でした。私は庭にチョークで輪を描いて、みつきとけんたに見せました。
「今日はケンケンパ大会だよ!優勝者にはアイスクリーム!」 「やったー!」
みつきの目がキラキラ輝きました。でも実際やってみると、みつきはバランスを崩してすぐに転んでしまいます。私は内心「大丈夫かな」と心配になりましたが、みつき本人は「もう一回!」と楽しそうです。
それから毎日15分、我が家の庭は子供たちの笑い声で溢れました。1ヶ月後、みつきの縄跳びの記録を測ってみると、なんと5回から32回に増加していました。私は嬉しくて、会社の同僚にも自慢してしまいました。
雨の日に発見した最高の室内ゲーム
梅雨の時期、外で遊べない日が続いて、子供たちはストレスが溜まっていました。そんな時、私は本書で紹介されていた「風船バレー」を思い出しました。
リビングに風船を膨らませて、「さあ、みんなで風船を落とさないゲームをしよう!」と提案しました。最初は簡単だと思っていたのですが、やってみるとこれが意外に難しい!
「あ、落ちる落ちる!」 「みつき、そっち!」 「パパ、取って!」
家族みんなで必死に風船を追いかける姿は、きっと傍から見ると滑稽だったでしょう。でも私たちは本当に楽しかった。妻も「こんなに笑ったの久しぶり」と言っていました。
この風船バレーを続けているうちに、みつきの反射神経が明らかに良くなりました。保育園の先生からも「みつきちゃん、最近ボールキャッチが上手になりましたね」と褒められました。私は心の中でガッツポーズでした。
週末の家族時間を活用した健康的アクティビティでも紹介しましたが、親子で一緒に体を動かすことは、運動能力の向上だけでなく、親子の絆を深める効果もあります。
私がデータで発見した子供の成長パターン
効果が出なくて諦めそうになった2週間
私は外資系コンサル時代のクセで、子供たちの運動能力を毎日記録するようになりました。50メートル走のタイム、ボール投げの距離、縄跳びの回数…。でも最初の2週間、数字はほとんど変わりませんでした。
「本当に効果あるのかな?」私は不安になりました。妻も「あなた、子供にプレッシャーかけすぎじゃない?」と心配していました。
でも3週目に入った頃、突然変化が起きました。みつきのボール投げの距離が急に伸びたのです。1週間前まで5メートルだったのが、8メートルも飛ぶように!
「みつき、すごいじゃない!」 「本当?パパ、私上手になった?」 「めちゃくちゃ上手になってる!」
私は娘を高い高いして喜びました。妻も「あら、本当に効果があるのね」と驚いていました。
でも6週目頃、また記録が停滞しました。私は「このまま伸びないのかな」と不安になりましたが、8週目からまた向上が始まりました。子供の成長には波があることを、身をもって学んだのです。
我が家の週間スケジュール大公開
私は子供たちの年齢に合わせて、週間プログラムを作りました。でも最初はきっちりやりすぎて、子供たちに嫌がられてしまいました。
「パパ、今日は遊びたくない」 「えー、なんで?」 「毎日やるの疲れる」
みつきの言葉にハッとしました。私は子供のことを考えているつもりで、実は自分の満足のために厳しくしていたのかもしれません。
それから私はアプローチを変えました。けんた(2歳)には、とにかく自由に遊ばせることを重視しました。月曜日は公園で好きなように遊ばせる。水曜日は家の階段を一緒に上り下り。楽しそうにしている時だけ、15分程度で切り上げます。
みつき(5歳)には、もう少し構造的なアプローチを取りましたが、あくまでも「遊び」として。月曜日の鬼ごっこは私も本気で参加します。火曜日の縄跳びは一緒に数を数えて盛り上がります。木曜日の鉄棒では「今度はパパが逆上がりに挑戦する番だ!」と言って、私が必死に練習する姿を見せました(結果、まだできませんが…)。
何より大切だと気づいたのは、子供が「楽しい」と感じることです。私が無理強いすると、子供たちの顔は曇ります。でも楽しみながら取り組んでいる時の子供たちの笑顔は、本当に輝いています。
私が犯してしまった大きな間違いと気づき
娘を傷つけてしまった私の失敗
運動指導を始めて1ヶ月ほど経った頃、私は大きな間違いを犯してしまいました。ある日、みつきが保育園のかけっこで3位になって帰ってきました。前まではいつもビリだったので、本来なら大進歩です。
でも私は思わず言ってしまいました。
「3位か。○○ちゃんはいつも1位なのに、どうしてみつきは…」
その瞬間、みつきの顔がサッと曇りました。私はすぐに自分の言葉を後悔しましたが、もう遅かったです。その日の夜、みつきは「パパ、私ってダメな子?」と聞いてきました。私は胸が締め付けられる思いでした。
妻からも厳しく注意されました。
「あなた、何やってるの?みつきがどれだけ頑張ってるか分からないの?」 「ごめん、つい…」 「つい、じゃ済まないでしょ。みつきの気持ち考えなさいよ」
私は深く反省し、その夜、みつきに謝りました。
「みつき、パパがごめんね。3位になったこと、本当にすごいよ。パパはみつきが頑張ってるのが一番嬉しいんだ」 「パパ、私のこと好き?」 「大好きに決まってるじゃない。みつきが世界で一番大切だよ」
その時、私は親として最も大切なことを学びました。結果ではなく、子供の努力を認めること。他の子と比較するのではなく、その子なりの成長を喜ぶこと。
効果的だった私の声かけの変化
それ以降、私の声かけは完全に変わりました。練習前には「今日はどんな発見があるかな?みつきと一緒だから楽しみ!」と言うように。練習中は「すごい!さっきよりもずっと足が上がってる!」と具体的な改善点を伝える。練習後は必ず「みつきが頑張る姿、パパは見てて嬉しいよ。明日はどんな成長があるかな」と言います。
すると、みつきの表情が明るくなりました。「パパ、今日は楽しかった!明日も一緒にやる?」と言ってくれるようになったのです。
私は運動指導だけでなく、親として大きく成長できたと思います。子供の笑顔こそが、最高の成果だということを学んだのです。
私と子供たちが一緒に乗り越えた挫折の日々
縄跳びで親子そろって大泣きした日
運動指導を始めて2ヶ月目、私はみつきに縄跳びを教えようとしました。でも私のアプローチは完全に間違っていました。
「みつき、縄跳び跳んでみて」 「分からない」 「えー、こうやって跳ぶんだよ」
私が見本を見せても、みつきは全くできません。私はだんだんイライラしてきて、「どうしてできないの?」と強い口調で言ってしまいました。
すると、みつきは「わー!」と泣き出してしまいました。私も自分の感情をコントロールできなくなって、「もういい!」と言って家に入ってしまいました。その時、みつきも私も大泣きしていました。
妻が仲裁に入って、私たちは仲直りしましたが、私はこの日のことを深く反省しました。「私は子供の気持ちを全然考えていなかった」と。
それから私は、3冊の本を読み直しました。そして段階的な練習法があることを知ったのです。
私は翌日、みつきに謝って、新しい方法を提案しました。「みつき、昨日はごめん。今度は違うやり方でやってみよう」
最初の週は、縄を地面に置いて、それを跨ぐだけ。「縄跳びごっこ」と名付けて、ゲーム感覚で取り組みました。2週目は縄を持たずにジャンプの練習。3週目は片手で縄を回す練習。
毎日少しずつ、私とみつきは一緒に成長していきました。そして3ヶ月後、みつきが連続30回跳べた時、私たちは抱き合って喜びました。あの日の涙が、今度は嬉し涙に変わりました。
けんたの鉄棒恐怖症を克服した日々
2歳のけんたは、公園の鉄棒を見ると逃げ出してしまいます。無理に近づけようとすると、ギャーギャー泣いてしまう。私は困り果てていました。
でも本に書いてあった通り、まずは「ぶら下がるだけ」から始めました。私が最初に手本を見せると、けんたはキャッキャッと笑います。
「パパ、お猿さんみたい!」 「そうだね、けんたもお猿さんになってみる?」 “ううん、怖い”
でも毎日続けていると、けんたも少しずつ興味を示すように。ある日ついに、私の手を握りながらですが、鉄棒に触ることができました。
“できた!」けんたの嬉しそうな顔を見て、私も泣きそうになりました。
今では、低い鉄棒なら一人で前回りができます。あの恐がりだったけんたが、です。
家族の絆を深めた「できたねシール」
私は子供たちのモチベーションを保つために、「できたねシール」を作りました。台紙には可愛いイラストを描いて、小さな目標を達成するたびにシールを貼る。10個貯まったら、好きなおやつを選べるシステムです。
でも一番嬉しかったのは、みつきが私にもシールをくれたことです。
“パパ、今日はみつきと一緒に頑張ったから、パパにもシールあげる” “ありがとう、みつき”
私も自分用の台紙を作りました。「良いパパシール」。子供たちが私のことを褒めてくれた時に貼るシールです。これが意外に嬉しくて、私も毎日頑張るようになりました。
家族みんなでお互いを褒め合う習慣ができて、我が家の雰囲気がとても良くなりました。
親子運動で絆が深まる脳科学的メカニズムでも解説されていますが、共同運動を通じて親子の愛着ホルモン(オキシトシン)が増加し、信頼関係も深まります。運動は、体だけでなく心も育てるのです。
私が実践した3ステップで、あなたの家族も変われます
ステップ1:私がやった現状把握の方法
最初に私がやったことは、子供たちの「今」を知ることでした。でも測定と言っても、堅苦しくしません。家族みんなで「運動会ごっこ」として楽しみながら記録しました。
みつきの50メートル走は、近所の公園で測りました。妻がスマホのストップウォッチ係、私がスタート係、けんたが応援係。“頑張れー!“けんたの声援で、みつきも楽しそうに走りました。
ボール投げは、公園の芝生で実施。私が子供たちと一緒にやってみたら、実は私が一番下手でした。“パパ、下手だね”みつきに笑われましたが、家族みんなで大笑い。
これらの記録を表にまとめて、リビングに貼りました。子供たちも興味深そうに見ています。
ステップ2:私たち家族専用プログラムの誕生
本で学んだ知識を基に、我が家専用のプログラムを作りました。でも最初は欲張りすぎて、毎日何かしらの運動を計画してしまいました。結果、子供たちは疲れてしまって…。
妻から”もっとゆるくしましょう”と提案され、週3回、各15分から始めることにしました。月曜日、水曜日、土曜日。この3日間を”家族運動デー”として、みんなで楽しく体を動かします。
雨の日は室内で風船バレー、晴れの日は公園で鬼ごっこ。プログラムと言うより、家族の遊び時間です。私も童心に返って、本気で楽しんでいます。
ステップ3:3ヶ月後の奇跡的な変化
3ヶ月後、同じ項目を測定した時、私は自分の目を疑いました。みつきの50メートル走のタイムが5秒も縮まっていたのです!ボール投げの距離も倍以上に。
“すごいじゃない、みつき!“私は娘を抱き上げて回りました。けんたも階段を一人で上り下りできるようになって、得意げです。
でも一番嬉しかったのは、子供たちの表情です。運動が楽しいものだと思ってくれている。これが私にとって最大の成果でした。
この成功体験が、私たち家族にとって大きな自信となりました。“やればできるんだ”ということを、子供たちも私も実感したのです。
あの涙の日から8ヶ月。今、私が伝えたいこと
“パパ、私はどうして他の子みたいに走れないの?“あの日の娘の言葉から始まった私たちの運動チャレンジ。今振り返ると、それは我が家にとって最高の贈り物でした。
私は38歳にして2児の父となり、“測定できるものは改善できる”という座右の銘を持っていましたが、子育てにおいては数字以上に大切なことがあることを学びました。それは、子供たちの笑顔です。
運動神経は遺伝ではありませんでした。私たち親子が証明しました。適切な時期に、適切な方法で、そして何より楽しみながら取り組めば、必ず成長できるのです。
私が実践した3冊の本それぞれに、深い感謝の気持ちがあります。
『運動神経は10歳で決まる!』は、私に希望を与えてくれました。年齢別のアプローチを知ることで、焦らずに子供たちと向き合えるようになりました。
『子どもの成長は足が9割』は、見落としがちな基礎の大切さを教えてくれました。足から始めることで、子供たちの体全体が変わっていく様子を目の当たりにしました。
『子どもの運動神経をグングン伸ばす スポーツの教科書』は、家族の時間を豊かにしてくれました。遊びを通じて学ぶことの素晴らしさを実感しました。
でも一番大切だったのは、私自身が変わったことです。完璧を求める父親から、子供たちと一緒に成長する父親へ。データを重視する私から、子供たちの気持ちを大切にする私へ。
今年の運動会で、みつきが徒競走で2位になった瞬間、私は観客席で泣きました。嬉し涙でした。でも1位じゃなくても、私は娘を心の底から誇らしく思いました。なぜなら、みつきが最後まで楽しそうに走っていたから。
運動は義務ではありません。家族の幸せな時間です。子供は親の姿を見て育ちます。私が楽しんでいれば、子供たちも楽しむ。私が一緒に成長しようとすれば、子供たちも成長してくれる。
もしあなたのお子さんが運動で悩んでいるなら、まずは一緒に楽しむことから始めてみてください。3ヶ月後、きっと想像以上の変化に驚くでしょう。そして何より、家族の絆が深まっていることを実感できるはずです。
私たち家族の8ヶ月間の挑戦は、まだまだ続きます。次の目標は、家族全員でマラソン大会に参加すること。私も頑張らなきゃ!
スキャモンの発育曲線とゴールデンエイジ理論を基に、2~12歳の年齢別トレーニング法を写真付きで解説。運動神経は後天的に伸ばせることを科学的に証明し、家庭で実践できる具体的な方法を提供する必読書。
¥1,430(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp