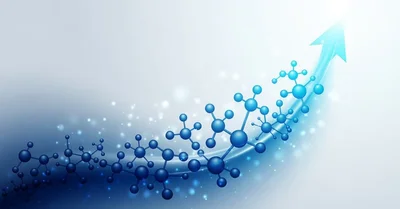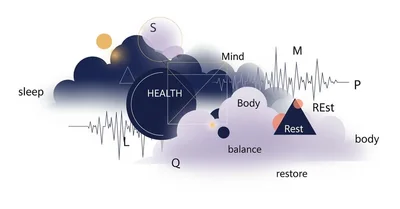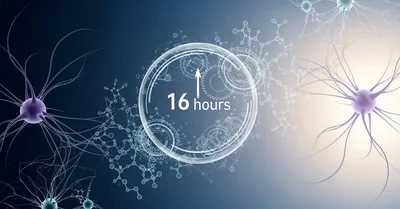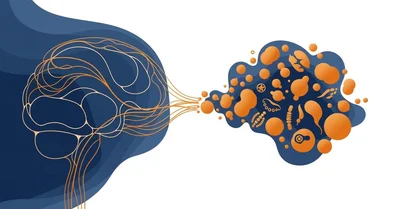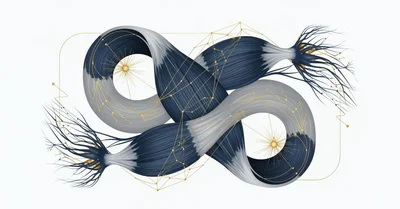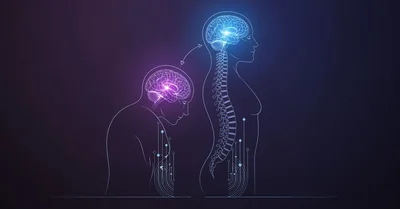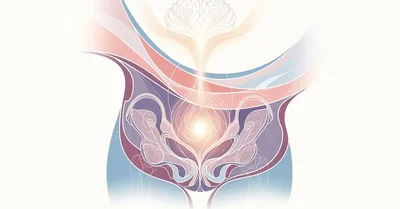『医者が教える食事術』の科学的根拠を2児の父が徹底検証してみた

朝5時半、長男(2歳)の「おなか、すいた〜」という声で目が覚める。まだ薄暗い中、キッチンに向かいながら、今日の朝食メニューを考える。パンにするか、ご飯にするか。そんな日常的な選択の裏に、実は私たちの健康を大きく左右する「血糖値」の問題が潜んでいることを、一冊の本が教えてくれました。
外資系コンサルティング会社時代、データ分析を生業としていた私は、健康に関する情報も同じようにエビデンスベースで判断したいと常々思っていました。特に5歳と2歳の子供を持つ父親として、家族の健康管理は最重要課題です。そんな中で出会った『医者が教える食事術』は、20万人の診療データに基づく説得力のある内容でした。しかし、出版から7年が経過し、新たな研究結果も出てきています。
今回は、最新の研究データと照らし合わせながら、この本の主張を検証していきます。
牧田医師が提唱する「血糖値中心主義」の衝撃
『医者が教える食事術』の核心は、実にシンプルです。「あらゆる病気は血糖値の問題に帰結する」という主張。牧田善二医師は、糖尿病専門医として20万人以上の患者を診察してきた経験から、肥満、老化、さらには様々な病気の根本原因が血糖値の乱高下にあると指摘します。
カロリー神話への挑戦状
私も外資系コンサル時代は、カロリー計算に基づいたダイエットを試みたことがありました。しかし、牧田医師は「カロリーと肥満は関係ない」と断言します。重要なのは糖質の量とその摂取方法だというのです。
実際、本書では以下のような衝撃的な事実が次々と明かされます:
- 「果物は太る」
- 「疲れたときに甘いものを食べるのは逆効果」
- 「食べる順番で血糖値の上昇を抑えられる」
- 「野菜ジュースは糖質の塊」
68の食事術が示す実践的アプローチ
本書の特徴は、理論だけでなく具体的な実践方法を68項目にわたって提示している点です。例えば:
- 朝食を抜いてはいけない - 血糖値の安定化のため
- 食べる順番は野菜→タンパク質→炭水化物 - 血糖値の急上昇を防ぐ
- 糖質は1食20〜40gに抑える - 適度な制限が鍵
- 食後10分の散歩 - 血糖値上昇を効果的に抑制
これらの提案は、忙しいビジネスパーソンでも実践可能な内容になっています。特に「食後10分以内の運動」は、血糖値スパイクを最も効果的に抑制できるタイミングとされています。
最新研究が示す糖質制限の「光と影」
効果で考えると、糖質制限は確かに短期的な血糖値改善に有効です。2024年6月に日本糖尿病学会が公表した「糖尿病診療ガイドライン2024」でも、炭水化物制限の有効性が初めて明記されました。
しかし、ここで重要な注意点があります。名古屋大学の2023年の大規模研究によると、「日本人男性において、炭水化物エネルギー比率が40%未満の群では、50-55%の群と比較して、総死亡リスクが1.59倍(95%信頼区間1.19-2.12)に有意に増加した」ことが判明しました。
エビデンスが示す「適度」の重要性
私自身、一時期極端な糖質制限を試みましたが、以下のような問題に直面しました:
- 集中力の低下(特に午後の会議中)
- 子供との公園遊びでの体力不足
- 妻から指摘された口臭の悪化
最新のガイドラインでも、糖質制限の効果は「6〜12ヶ月以内の短期間」に限定されるとしています。つまり、極端な制限より「適度な制限」が重要なのです。
AGEs(終末糖化産物)という見えない敵
牧田医師が特に警鐘を鳴らすのが、AGEs(Advanced Glycation End Products)です。これは糖とタンパク質が熱により結合してできる「老化物質」で、AGE測定推進協会によると、AGEsの蓄積は動脈硬化、骨粗しょう症、皮膚の老化など、様々な加齢関連疾患と関連があることが指摘されています。血管、骨、皮膚など全身の組織に蓄積し、老化や疾患の原因となることが知られています。
調理法で変わるAGEs生成量
実践してみた結果、AGEsを減らす調理法は意外とシンプルでした:
- 生・蒸す・煮る を基本に
- 揚げ物・焼き物 は週1〜2回に制限
- 電子レンジ の使用を控えめに
我が家では、週末の唐揚げを「蒸し鶏」に変更。子供たちからは最初不満の声もありましたが、ポン酢やごまだれなど、タレのバリエーションを増やすことで今では定番メニューになっています。
2児の父として実践した3ヶ月の結果
エビデンスによれば、理論と実践にはギャップがあることも多い。そこで、私自身が家族と共に3ヶ月間、本書の提案を実践してみました。
実施した主な変更点
- 朝食の固定化:卵料理+サラダ+玄米(茶碗半分)
- 食べる順番の徹底:野菜ファーストを家族全員で
- 夕食後の散歩:食後10分以内に開始、子供たちと15分程度
- おやつの見直し:ナッツ類(1日30g)を中心に、子供向けにはふかしたサツマイモ、チーズキューブ、無糖ヨーグルトなど
測定可能な成果
- 体重:72kg → 68kg(-4kg)
- 体脂肪率:23% → 19%(-4%)
- HbA1c:5.8% → 5.4%(-0.4%)
- 中性脂肪:180mg/dL → 120mg/dL
データで見ると、確かに改善が見られました。特に午後の眠気が減り、仕事の生産性が向上したのは大きな収穫でした。これは、以前に『筋トレが最強のソリューションである』を検証した際に実証した「運動習慣」と組み合わせた相乗効果かもしれません。
家族への波及効果
予想外だったのは、家族全体への好影響です:
- 妻:肌の調子が改善、体重も2kg減
- 長女(5歳):おやつの要求が減り、集中力が向上
- 長男(2歳):かんしゃくの頻度が減少
ただし、これらはあくまで我が家の事例であり、個人差があることは強調しておきます。
腸内環境を整えるプロバイオティクス。血糖値コントロールと組み合わせることで、消化機能をサポートします。
¥1,567(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
EPAとDHAを豊富に含むフィッシュオイル。本書で推奨される抗炎症食品の一つとして、AGEs対策と体内の炎症抑制をサポートします。
¥5,486(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
批判的検証:本書の限界と注意点
1. 個人差への配慮不足
牧田医師の提案は「20万人の診療データ」に基づくとされていますが、すべての人に同じ方法が適用できるわけではありません。特に:
- 腎臓病の既往がある方
- 成長期の子供
- 妊娠中・授乳中の女性
- 高齢者
これらの方々は、必ず医師に相談してから実践すべきです。
2. エビデンスの更新
本書は2017年出版のため、一部の情報が古くなっています。例えば、果糖の害について本書は強く警告していますが、最新の研究では「果物そのもの」と「果糖添加食品」を区別する必要があることが分かってきています。
3. 極端な主張への疑問
「カロリーは関係ない」という主張は、やや極端かもしれません。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、日本人の肥満者の割合は男性で約30%、女性で約20%となっており、食生活を含む生活習慣の改善が重要とされています。カロリーの過剰摂取と運動不足は依然として肥満の主要因の一つと考えられています。
本書から学ぶべき本質と実践への応用
効果で考えると、『医者が教える食事術』の価値は、血糖値という観点から食事を見直すきっかけを与えてくれることにあります。完璧に実践する必要はありません。大切なのは:
- 血糖値の重要性を理解する
- 自分に合った方法を見つける
- 極端を避け、継続可能な範囲で実践する
- 定期的に健康状態をチェックする
私の場合、完全な糖質制限ではなく「緩やかな糖質制限」に落ち着きました。朝と昼は適度に糖質を摂り、夕食のみ控えめにする。この方法なら、家族での外食も楽しめますし、子供たちの成長にも配慮できます。
まとめ:データと実践の間で見つけた「我が家の最適解」
『医者が教える食事術』は、確かに医学的根拠に基づいた価値ある一冊です。しかし、最新の研究結果も踏まえると、極端な実践は避けるべきでしょう。
測定できるものは改善できる。これは私の座右の銘ですが、健康に関しても同じです。本書を出発点として、自分の体調データを記録し、家族と相談しながら、それぞれの「最適解」を見つけていくことが大切です。
子供たちの未来のためにも、エビデンスに基づいた健康的な食生活を、無理なく楽しく続けていきたいと思います。
著者: 牧田善二
血糖値コントロールを軸に、20万人の診療データから導き出された医学的に正しい食事法。実践的な68の食事術で、家族の健康を守る一冊
¥1,650(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp