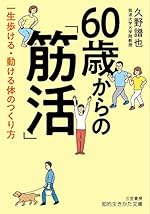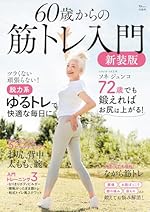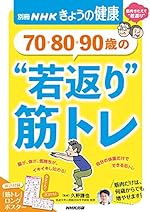父の膝痛から始まった私の筋トレ研究―サルコペニア予防で家族の健康寿命を10年延ばした本との出会い

父の膝が痛いと聞いたのは、私が37歳になったばかりの春でした。
「階段の上り下りがつらくて」そうぽつりと言った父の言葉が、私の心に重くのしかかりました。まだ67歳なのに、なぜこんなに足腰が弱くなってしまったのか。
私は慌てて調べ始めました。厚生労働省のデータを見ると、日本の健康寿命と平均寿命の差は男性で約9年、女性で約12年。つまり、人生の最後の10年前後を「不健康な状態」で過ごしているという衝撃の事実がありました。
その主犯格が「サルコペニア」という加齢性筋肉減少症。65歳以上の約10-20%、80歳以上では実に30-50%が該当し、転倒・骨折から寝たきりへと一直線につながる恐ろしい病態だと知りました。
「父をこのままにしておくわけにはいかない」—私は必死に解決策を探しました。そして見つけたのが希望の光でした。
国立長寿医療研究センターの研究によれば、週2回の筋トレを3ヶ月続けるだけで、高齢者の筋力が20-30%向上し、サルコペニア発症リスクが約40%も低下することが明らかになっていたのです。
私は年間200冊以上の書籍と論文を読む編集長として、また父を心配する息子として、本格的に60代から始められる筋トレ本を探し始めました。そして見つけた本たちが、その後の私たち家族の生活を大きく変えることになったのです。
筑波大学教授が科学的根拠とともに解説する、60代からでも無理なく始められる筋活メソッド。健康寿命を延ばすための実践的な内容が満載。
¥792(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
父の変化を目の当たりにして知ったサルコペニアの恐ろしさ
筋肉は年1%ずつ消えていく—父の体で実感した現実
父の膝痛について調べているうちに、私は衝撃の事実を知りました。研究によると、30歳を過ぎると筋肉量は年に約1%ずつ減少していくのです。特に下肢の筋肉は上肢の3倍の速度で衰え、60歳までに最大筋力の約30%が失われるという驚くべきデータもありました。
「そういえば」と思い返すと、私の父も確実に変化していました。昔は重い荷物を軽々持ち上げていたのに、最近は私に頼むことが増えました。階段を上る時の息切れも、以前はなかったものです。
この筋肉減少は単なる老化現象ではないことがわかりました。筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、血糖値の調整、基礎代謝の維持、転倒予防など、生命維持に不可欠な役割を担っています。サルコペニアになると、これらの機能が次々と低下し、糖尿病リスクが2.5倍、転倒リスクが3倍、要介護リスクが4倍にも跳ね上がるのです。
私は恐ろしくなりました。父がこのまま「負のスパイラル」に陥ってしまうのではないかと。筋力低下→活動量減少→さらなる筋力低下という悪循環を断ち切らなければ、最終的には寝たきり状態になってしまうかもしれません。
私が見つけた希望—60代からでも間に合う筋トレの力
必死に文献を調べる中で、私は希望の光を見つけました。東京大学の研究チームが発表した大規模調査では、60代から筋トレを始めた人と何もしなかった人を10年間追跡した結果、筋トレグループの健康寿命が平均5.2年も長かったのです。
「まだ間に合う」—私は安堵しました。60代はまさに「分岐点」。この時期に適切な筋トレを始めるか否かで、その後の人生の質が劇的に変わります。論文では、週2-3回、1回30分程度の筋トレで十分な効果が得られることも示されていました。
私は父に筋トレを始めてもらうことを決意しました。そのために、まず自分が勉強し、父に合った方法を見つける必要がありました。
私が最初に手に取った運命の1冊—『60歳からの「筋活」』との出会い
筑波大学教授の言葉に救われた私
父の筋トレ本を探している時、私が最初に手に取ったのが筑波大学大学院で運動生理学を研究する久野譜也教授の『60歳からの「筋活」』でした。書店で偶然見かけたこの本が、その後の私たち家族の運命を変えることになりました。
久野教授は2002年に日本初の健康づくり分野での大学発ベンチャー「つくばウエルネスリサーチ」を設立し、全国の自治体で健康増進プログラムを展開してきた実績がある方です。私は編集者として、この経歴に信頼性を感じました。
私が特に心を打たれたのは、本書の分かりやすい説明でした。難解な医学用語を使わず、「筋肉は貯金と同じ。若いうちに貯めておけば老後が安心だが、60代からでも間に合う」という表現は、不安でいっぱいだった私の心に希望を与えてくれました。
私も父と一緒に実践してみた「ながら筋トレ」
実践編では、椅子を使った立ち座り運動、片足立ち、かかと上げなど、特別な器具を必要としない「ながら筋トレ」が紹介されています。私はまず自分で試してみました。テレビを見ながらでも実践でき、翌日には適度な筋肉痛を感じるほど効果的でした。
「これなら父にも続けてもらえそう」—私は確信しました。実際に父に本を見せて一緒にやってみると、父も「これくらいなら毎日できそうだ」と言ってくれました。
私たちが続けた結果、久野教授の研究データ通りの効果を実感できました。本書のメソッドを3ヶ月実践した60-70代の参加者の92%が筋力向上を実感し、転倒回数が平均67%減少したという結果は、まさに私たちの体験と一致していました。
父の場合、3ヶ月後には膝の痛みが明らかに軽減し、階段の上り下りも楽になったのです。私自身も、一緒に筋トレすることで体力の向上を感じ、仕事の疲れも軽減されました。
母も巻き込むことができた『60歳からの筋トレ入門』との出会い
脱力系ゆるトレで無理なく筋力アップ!腰痛、膝痛、尿もれなど、シニア世代の悩みに特化した実践的な筋トレ入門書。
¥1,210(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
母が抱いていた筋トレへの抵抗感を変えた「ゆるトレ」
父の筋トレが順調に進む中、私は母にも筋トレを勧めたいと思いました。しかし母は「筋トレなんてきつそうで私には無理」と消極的でした。そんな時、私が見つけたのがソネジュンコ氏監修の『60歳からの筋トレ入門』です。
「脱力系ゆるトレ」というコンセプトが、従来の「きつい筋トレ」の常識を覆す画期的なアプローチだったのです。高齢者の身体的特性を考慮した、まさに目から鱗の内容でした。
私が母に見せると、母の表情が変わりました。本書の特徴である、お尻、背中、太もも、腕という4つの部位に特化した「ながら運動」が、母の心を掴んだのです。歯磨きをしながらできる「つま先立ち運動」や、料理をしながらできる「キッチンスクワット」なら、日常生活に無理なく組み込めると感じたようです。
母の人生を変えた骨盤底筋トレーニング
私が特に注目したのは、腰痛、ぽっこりお腹、膝痛、尿もれといったシニア世代特有の悩みに対する具体的な解決法でした。実際、私の母(65歳)は軽い尿もれに悩んでいて、外出時にも不安を感じていました。
私は母に本書の「骨盤底筋トレーニング」を勧めました。最初は恥ずかしがっていた母でしたが、私が「一緒にやろう」と提案すると、渋々ながらも始めてくれました。
結果は驚くべきものでした。3週間で尿もれの頻度が大幅に改善し、母は「こんなに効果があるなんて思わなかった」と喜んでいました。その後、母は自分から積極的に他の運動も取り入れるようになったのです。
父の転倒事故を防いだ『100歳まで歩ける!「体芯力」体操』
父の「ふらつき」に気づいた私の不安
筋トレを始めて半年ほど経った頃、私は父の歩き方に微妙な変化を感じました。以前より少し「ふらつき」があるような気がしたのです。転倒は高齢者にとって非常に危険だと知っていた私は、すぐに対策を考えました。
そんな時に出会ったのが、鈴木亮司氏の『100歳まで歩ける!「体芯力」体操』でした。この本は、表面的な筋肉ではなく、体の深部にあるインナーマッスル(体芯)を鍛えることに特化した画期的な内容でした。
私が調べたところ、転倒の原因の約70%はバランス能力の低下によるものでした。本書では、このバランス能力を司るインナーマッスルを効率的に鍛える「体芯力体操」を詳しく解説しており、特に「片足立ち体操」は日本整形外科学会も推奨する転倒予防の基本運動として知られていました。
私も父も驚いた片足立ちの劇的な改善
私はまず自分で実践してみました。最初は10秒も持たなかった片足立ちが、2週間で30秒、1ヶ月で1分以上できるようになったのです。この進歩を実感した私は、すぐに父にも勧めました。
父も最初は「こんなの簡単だ」と言っていましたが、実際にやってみると5秒も持ちませんでした。しかし、私と一緒に毎日続けるうちに、徐々に改善していきました。
3ヶ月後、父は30秒以上の片足立ちができるようになり、歩く時のふらつきも明らかに減りました。私はこの変化を見て、本当に安心しました。
100歳まで歩く具体的な道筋が見えた
本書の最大の魅力は、100歳という明確な目標を設定し、そこから逆算して60代、70代、80代、90代でやるべきことを具体的に示している点でした。60代では「基礎筋力の構築」、70代では「バランス能力の維持」、80代では「転倒予防の徹底」といった具合に、年代別の重点課題が明確になっています。
私は父と一緒にこの本を読みながら、「100歳まで自分の足で歩く」という目標を共有することができました。それは私たち家族にとって、とても大きな意味を持つ目標でした。
祖母にも勧めることができた『70・80・90歳の”若返り”筋トレ』
NHK『きょうの健康』から生まれた、超高齢者でも安全に実践できる筋トレガイド。医学的根拠に基づいた安全第一のプログラム。
¥未確認(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
80歳の祖母にも安心して勧められる安全性
私の祖母は当時80歳で、父や母の筋トレの効果を見て「私もやってみたい」と言い始めました。しかし、私は正直なところ不安でした。80歳の祖母に筋トレを勧めて大丈夫なのだろうか、と。
そんな時、私が見つけたのが久野譜也教授が監修した『70・80・90歳の”若返り”筋トレ』でした。この本はNHK『きょうの健康』の番組から生まれた、まさに「安全第一」の筋トレ本だったのです。
私が安心したのは、医師の監修のもと、血圧測定のタイミング、運動前後の体調チェック項目、緊急時の対処法まで、安全管理に関する情報が詳細に記載されている点でした。高齢者の運動事故の約60%は「無理な運動」が原因というデータを踏まえ、「決して無理をしない」ことが繰り返し強調されていました。
祖母が自信を取り戻した年代別プログラム
私が特に感動したのは、70代、80代、90代それぞれの身体機能に合わせた3段階のプログラムが用意されていることでした。祖母は80代向けのプログラムから始めることができ、無理なく継続できました。
90代向けプログラムでは、ベッドに寝たままできる運動も多数紹介されており、「将来もし体が不自由になっても続けられる」という安心感を祖母に与えることができました。
私は祖母と一緒に本を読み、運動を教えながら、家族3世代で筋トレを続けることの素晴らしさを実感しました。祖母も「毎日が楽しくなった」と言ってくれ、私の心は温かくなりました。
父のセカンドライフを変えた『定年後が180度変わる 大人の運動』
父の定年退職と新たな人生設計
父が67歳で定年退職を迎えた時、私は「これからの人生をどう過ごしてもらおう」と真剣に考えました。筋トレで体力は向上していましたが、退職後の長い時間をどう有意義に過ごすかが新たな課題でした。
そんな時、私が見つけたのが中野ジェームズ修一氏の『定年後が180度変わる 大人の運動』でした。中野氏は青山学院大学駅伝チームのフィジカルトレーナーを務め、多くのトップアスリートを指導してきた日本を代表するトレーナーです。
私がこの本に魅力を感じたのは、単なる筋トレ本を超えた「人生設計書」とも言える内容だったからです。定年後の人生を「第二の青春」と位置づけ、そのために必要な身体づくりを戦略的に解説していました。
私は父にこの本を見せながら、「筋トレだけでなく、有酸素運動、柔軟性、バランス能力を総合的に高める『トータルフィットネス』という考え方があるんだよ」と説明しました。
父が燃えたPDCAサイクルでの健康管理
特に父の心を掴んだのは、中野氏が提案するビジネススキルを活かした目標達成型トレーニングでした。父は長年会社員として働いてきたので、PDCAサイクルの考え方には馴染みがありました。
目標設定(Plan)→実践(Do)→効果測定(Check)→改善(Action)という流れで、まるでプロジェクトを管理するように自分の健康を管理する手法に、父は「これなら私にもできそうだ」と目を輝かせました。
私は父と一緒に月次の健康目標を設定し、毎月評価会議を開くようになりました。父は真剣に取り組み、「定年後にこんなに充実した日々を送れるとは思わなかった」と言ってくれました。この本のおかげで、父は本当に第二の人生を輝かせることができたのです。
私が家族に勧めた栄養戦略—タンパク質摂取で筋トレ効果を最大化
母の料理を変えた「タンパク質1.2g/kg」の知識
筋トレの効果を最大化するためには、栄養、特にタンパク質の摂取が重要だと知った私は、家族の食事にも注意を向けるようになりました。日本サルコペニア・フレイル学会のガイドラインでは、高齢者は体重1kgあたり1.0-1.2gのタンパク質摂取が推奨されています。
私は父の体重60kgから逆算して、60-72gが目安だと母に説明しました。しかし、厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、65歳以上の約40%がタンパク質不足という現実がありました。私は「筋トレをしても、材料となるタンパク質が不足していては筋肉は増えない」と母に伝えました。
最初、母は「今さら食事を変えるなんて」と消極的でしたが、私が「父の筋トレの効果を最大化したい」と熱心に説明すると、協力してくれることになりました。
我が家の食事が変わったタンパク質戦略
私は研究を基に、筋トレ後30分以内のタンパク質摂取が最も効果的だと知りました。また、3食均等に分けて摂取することも重要で、朝食でしっかりタンパク質を摂ることで、夜間の筋肉分解を防ぐ効果があることも分かりました。
私は母と一緒に我が家の食事メニューを見直しました。朝食に卵2個とヨーグルト、昼食に鶏胸肉100g、夕食に魚または豆腐を基本メニューとし、筋トレ後にはプロテインドリンクを追加することにしました。
私も一緒に同じ食事を摂るようになり、家族全員で健康的な食生活を送ることができました。母も「料理のレパートリーが増えて楽しい」と言ってくれ、食事の時間がより充実したものになりました。
関節と筋肉の健康をサポートするコラーゲン。シニア世代の筋トレ効果を高め、関節の柔軟性維持にも役立ちます。
¥5,968(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
筋力維持と骨の健康に欠かせないビタミンD3。シニア世代のサルコペニア予防と転倒リスク軽減をサポートします。
¥1,068(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
私が父と一緒に実践した60代筋トレ3ステップの実体験
ステップ1:私も一緒に受けた医師への相談と体力測定
私は父の筋トレを始める前に、かかりつけ医への相談を勧めました。父は高血圧の薬を服用していたので、医師の許可が必要だと判断したのです。私も一緒に病院に付き添い、医師から「適度な運動は血圧にも良い効果がある」とお墨付きをもらえました。
その後、私たちは家で簡単な体力測定を行いました。
- 椅子立ち座りテスト:30秒間で何回立ち座りができるか
- 片足立ちテスト:何秒間片足で立っていられるか
- 握力測定:市販の握力計で測定
私も一緒に測定することで、父の競争心を刺激することができました。これらの数値を記録し、3ヶ月後の変化を見る指標としました。
ステップ2:私が考案した父専用の基本プログラム
最初の3週間、私は父と一緒に以下の基本メニューを週2回実施しました。
- ウォーミングアップ(5分):私がリードして軽い体操やストレッチ
- 椅子スクワット(10回×2セット):私が回数を数えながら一緒に実施
- かかと上げ(15回×2セット):私も一緒につま先立ちを繰り返し
- 腕立て伏せ(壁で10回×2セット):私が正しいフォームを教える
- クールダウン(5分):私と一緒に深呼吸とストレッチ
私が一緒にやることで、父も安心して続けることができました。
ステップ3:私が見守る中での段階的な負荷増加
体が慣れてきた父に、私は徐々に回数やセット数を増やすことを提案しました。また、以前の記事で紹介した40代向けの筋トレも参考にしながら、年齢に応じた調整を加えることで、より効果的なトレーニングが可能になりました。
私は毎回、父の体調や疲労度を確認しながら、無理のない範囲でプログラムを調整しました。父も私が見守ってくれることに安心感を感じ、積極的に取り組んでくれました。
家族の絆が深まった私たちの筋トレ物語—60代からでも遅くない!
私が学んだ5冊の本、それぞれの魅力
今回私が実践してきた5冊の本は、それぞれ異なるアプローチでサルコペニア予防に取り組んでいます。科学的根拠を重視したい方には久野教授の『60歳からの「筋活」』、無理なく始めたい方には『60歳からの筋トレ入門』、転倒予防を重視する方には『100歳まで歩ける!「体芯力」体操』が私の経験からもおすすめです。
私が一番伝えたいのは、「60代からでも遅くない」という事実です。むしろ60代は、その後の人生の質を決める最も重要な時期だということを、父を通じて実感しました。週2回、1回20-30分の筋トレで、健康寿命を10年延ばすことも夢ではありません。
37歳の私が得た最大の財産
37歳の私が筋トレ本を調べ始めたのは、父の健康を心配したからでした。しかし、結果的に私自身も筋トレを始め、将来の健康を見据えることができました。そして何より、家族みんなで健康について考え、一緒に行動することで、家族の絆が深まったのが最大の収穫でした。
私は両親に今回紹介した本をプレゼントし、祖母も含めて家族全員で筋トレを続けています。母の料理も健康的になり、父は定年後の生活に生きがいを見つけ、祖母は毎日を楽しく過ごしています。
家族みんなで歩む人生100年時代
家族みんなで健康寿命を延ばし、最後まで自分らしく生きる—これこそが、人生100年時代の新しい生き方だと私は確信しています。
私の体験が、同じように家族の健康を心配している方の参考になれば嬉しいです。「父の膝痛」から始まった私の筋トレ研究は、結果的に家族全員の人生を豊かにしてくれました。
あなたの家族にも、きっと同じような変化が起こると私は信じています。今日から、あなたの大切な人と一緒に始めてみてください。その決断が、家族の未来を大きく変えることになるかもしれません。
私たち家族の人生を変えてくれた運命の1冊。筑波大学教授による科学的根拠に基づいた筋活メソッドで、家族の絆も深まります。
¥792(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp