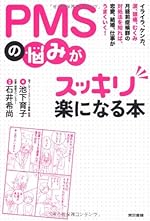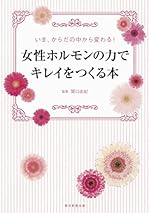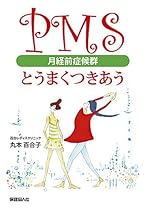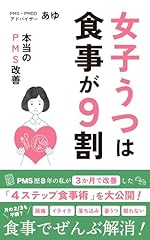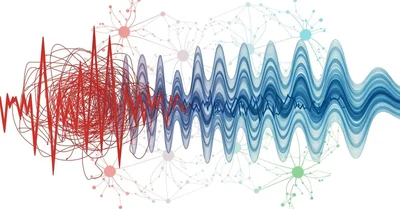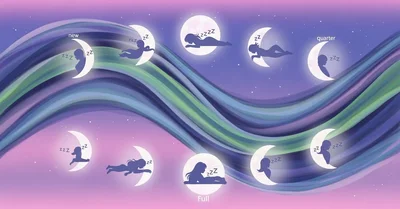PMS本おすすめ5選!月経前の不調を根本から改善する実践ガイド

「また今月も来た…」月経の1週間前になると、わけもなくイライラして夫に八つ当たりしてしまう。頭が重くて仕事に集中できない。甘いものが無性に食べたくなって、体重計に乗るのが怖い——。
厚生労働省の調査によると、月経のある女性の約70〜80%が何らかのPMS症状を経験しており、そのうち5〜8%は日常生活に支障をきたすほど重症だそうです。
私の妻も毎月PMSに悩まされていて、「なんで私だけこんなに辛いの?」と泣きながら訴えることがあります。4歳の息子の世話をしながら仕事もこなす妻を見ていて、男性である私にできることは限られていますが、せめて理解し、サポートしたいと思い、PMS関連の書籍を片っ端から読み漁りました。
今回は、その中から特に実践的で効果が期待できる5冊を厳選してご紹介します。医師監修の専門書から、実体験に基づく改善記録まで、様々な角度からPMSにアプローチできる本を選びました。
PMSの真実:なぜ毎月同じ症状に悩まされるのか
PMSは「月経前症候群」の略で、月経開始の3〜10日前から始まる心身の不調を指します。症状は200種類以上あると言われ、イライラ、憂うつ、頭痛、腹痛、むくみ、乳房の張りなど多岐にわたります。
最新の研究では、PMSの原因は単純なホルモンバランスの乱れだけでなく、脳内の神経伝達物質(セロトニン、GABA)の変動、炎症反応、栄養不足など、複数の要因が絡み合っていることが分かってきました。以前紹介した栄養療法の記事でも触れましたが、特に現代女性の食生活の偏りが症状を悪化させている可能性が高いのです。
おすすめPMS改善本5選
1. PMSの悩みがスッキリ楽になる本|池下育子
池下レディースクリニック銀座院長による、マンガとイラストで分かりやすくPMSを解説。恋愛・結婚・仕事のシーン別に対処法を紹介。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
池下レディースクリニック銀座院長の池下育子医師による、PMSの総合ガイドブックです。
この本の特徴
- マンガとイラストで複雑な医学知識を分かりやすく解説
- 「恋愛」「結婚」「仕事」のシーン別に具体的な対処法を提示
- セルフチェックシートで自分のPMSタイプを診断できる
私が特に参考になったのは、「パートナーができること」という章でした。妻の症状を記録するカレンダーの作り方や、PMSの時期の接し方など、男性目線でも理解しやすく書かれています。実際、妻と一緒にセルフチェックをやってみたら、「むくみ型」と「イライラ型」の混合タイプだということが分かり、それぞれに適した対処法を実践できるようになりました。
2. 女性ホルモンの力でキレイをつくる本|関口由紀
女性泌尿器科の第一人者による、ホルモンバランスを整える生活習慣と食事法の実践ガイド。
¥1,430(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
横浜元町女性医療クリニックLUNA理事長の関口由紀医師が、女性ホルモンの仕組みから実践的な改善法まで解説した一冊です。
この本の特徴
- 女性ホルモンの基礎知識を医学的に正確に解説
- 年代別(20代〜50代)のホルモンケア方法を提示
- 骨盤底筋トレーニングなど、具体的なエクササイズを図解付きで紹介
関口医師は女性泌尿器科の第一人者で、骨盤底筋の重要性を日本で最初に提唱した医師の一人です。PMSだけでなく、更年期や尿もれなど、女性特有の悩み全般に対応できる内容になっています。
私の妻は出産後から軽い尿もれに悩んでいたのですが、この本で紹介されている骨盤底筋トレーニングを3ヶ月続けたところ、尿もれが改善しただけでなく、PMSの腹部膨満感も軽減したと喜んでいました。
3. これってホルモンのしわざだったのね|松村圭子
成城松村クリニック院長による、日常の不調とホルモンの関係を分かりやすく解説した実践書。
¥1,430(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
成城松村クリニック院長の松村圭子医師による、女性ホルモンとの上手な付き合い方を解説した本です。
この本の特徴
- 「なんとなく調子が悪い」の原因をホルモンの観点から解明
- 28日間の実践プログラムで習慣を変える
- チェックテストで自分のホルモンバランスを把握
松村医師の文章は親しみやすく、まるで診察室で相談しているような感覚で読み進められます。特に「ホルモンの波に乗る」という考え方は目から鱗でした。PMSを「闘う相手」ではなく「上手に付き合うパートナー」として捉え直すことで、精神的な負担が軽くなるという視点は新鮮でした。
4. PMS(月経前症候群)とうまくつきあう|丸本百合子
PMSとの付き合い方を実践的に解説。症状管理と日常生活での対処法を豊富な事例で紹介。
¥1,320(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
丸本百合子氏による、PMSとの上手な付き合い方を実践的に解説した本です。
この本の特徴
- 実際の症例を豊富に紹介し、共感しやすい内容
- 症状日記の付け方と活用法を詳しく解説
- 家族や職場での理解を得るためのコミュニケーション術
この本の最大の特徴は、「完璧に治そうとしない」というスタンスです。PMSをゼロにするのではなく、「生活に支障がない程度まで軽減する」という現実的な目標設定が、かえって気持ちを楽にしてくれます。
妻はこの本を読んで、「無理に頑張らなくていいんだ」と肩の力が抜けたようでした。症状日記をつけ始めてから、自分のパターンが見えてきて、事前に対策を立てられるようになったと言っています。
5. 女子うつは食事が9割:本当のPMS改善|PMS・PMDDアドバイザーあゆ
栄養療法に特化したPMS改善法。食事改善、サプリメント、プロテイン活用の4ステップで症状を根本から改善。
¥498(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
PMS・PMDDアドバイザーあゆ氏による、栄養療法に特化したPMS改善本です。
この本の特徴
- 栄養不足がPMSの根本原因という視点から解説
- 具体的な食事メニューとレシピを多数掲載
- サプリメントの選び方と摂取タイミングを詳しく説明
- 4ステップの実践プログラムで段階的に改善
著者自身が重度のPMDDを栄養療法で克服した経験をもとに書かれているため、説得力があります。特に「タンパク質不足が諸悪の根源」という主張は衝撃的でした。
試しに妻と一緒にプロテインを飲み始めたところ、2ヶ月後には明らかにPMS症状が軽くなったと実感しています。朝食をプロテインスムージーに変えただけという手軽さも続けやすいポイントです。
実践して分かった3つの重要ポイント
これらの本を読み、妻と一緒に様々な方法を試してきて分かったことが3つあります。
1. 記録することの重要性
症状日記をつけることで、自分のパターンが見えてきます。いつ頃からイライラが始まるのか、どんな時に症状が悪化するのか。データが蓄積されると、予防的な対策が立てられるようになります。
2. 栄養改善は即効性がある
特にタンパク質とビタミンB群、マグネシウムの補給は、早い人なら1〜2週間で効果を実感できます。サプリメントも有効ですが、まずは食事から改善することが基本です。
特にマグネシウムはPMS症状の緩和に研究で効果が示されており、食事だけでは不足しがちな場合はサプリメントでの補給も検討に値します。
吸収率の高いグリシン酸マグネシウム。PMS症状の緩和、筋肉の緊張緩和、睡眠の質向上をサポート。
¥3,311(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
ストレスによるホルモンバランスの乱れをサポート。マグネシウムと併用することで、PMSに伴うイライラや不安感の緩和が期待できます。
¥1,245(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
3. パートナーの理解が症状を軽減する
男性がPMSを理解し、適切にサポートすることで、女性の精神的ストレスが大幅に軽減されます。「気のせい」「甘え」ではなく、医学的な症状であることを理解することが第一歩です。
PMSは改善できる——希望を持って一歩ずつ
PMSは「仕方ない」「我慢するしかない」というものではありません。適切な知識と実践により、必ず改善の道筋が見えてきます。
私の妻も、1年前は毎月PMSで寝込んでいましたが、今では「ちょっと調子悪いかな」程度まで改善しました。完璧を求めず、少しずつ改善していくことが大切です。
今回紹介した5冊は、それぞれ異なるアプローチでPMSに立ち向かう方法を教えてくれます。医学的な知識を求める方は池下医師や関口医師の本を、実践的な方法を知りたい方は丸本氏やあゆ氏の本を、まずは手に取ってみてください。
毎月の不調から解放され、本来のあなたらしさを取り戻せる日は必ず来ます。一緒に、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
マンガとイラストで分かりやすくPMSを解説。医師監修の確かな内容で、今すぐ実践できる対処法が満載。
¥1,540(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp