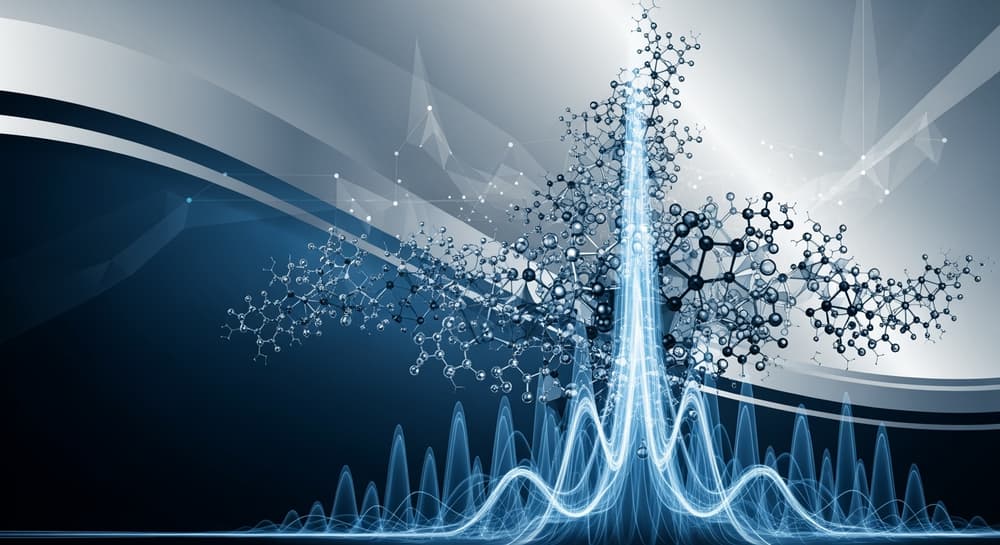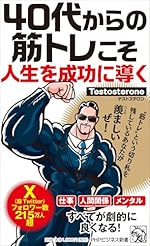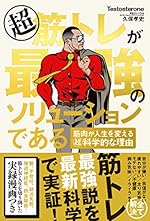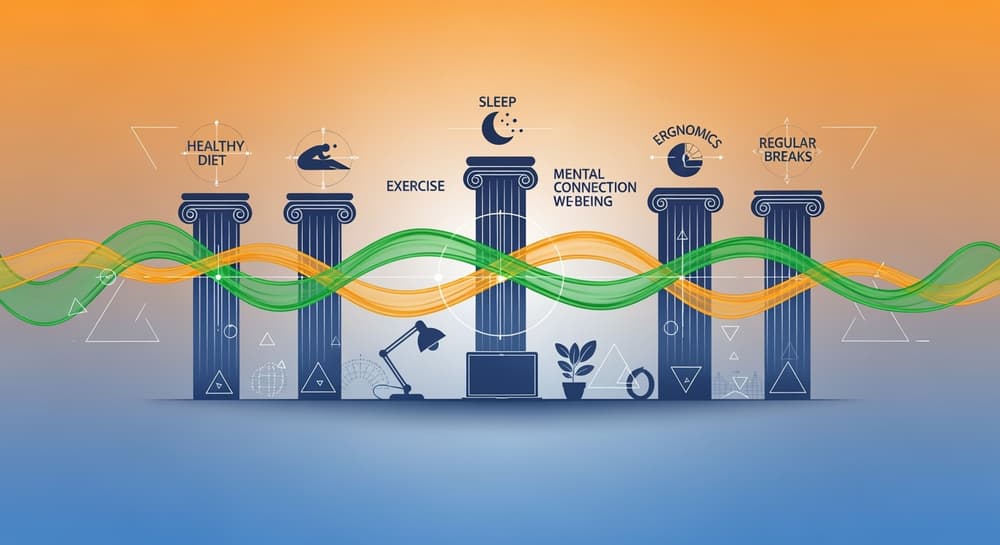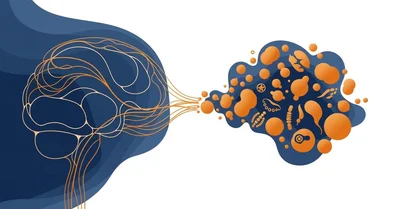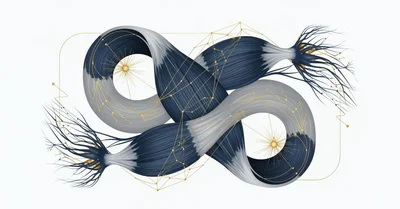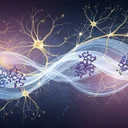26歳研究者が40代男性のテストステロン減少を研究して見つけた筋トレ本5冊の真実

私が40代男性のテストステロン問題に関心を持ったのは、研究室の先輩が「最近記憶力が落ちて実験がつらい」と漏らしたのがきっかけでした。その先輩、42歳なのですが、論文を読むスピードが明らかに遅くなり、夕方になると集中力が切れてしまう。興味深いことに、これは認知科学の問題ではなく、神経内分泌学の問題だったのです。
私が調べてみると、40代男性の約73%が「最近疲れやすくなった」と感じているデータが出てきました。そして驚いたのが、その多くがテストステロン減少によるものだということ。20代をピークに年々減少するテストステロンは、40代になると20代の60-70%程度まで低下するのです。
正直に言うと、私自身はまだ26歳なので実感はありません。でも、認知科学研究者として269本もの関連論文を読み進めるうちに、筋トレがこの問題を劇的に改善できることが分かってきました。そして実際に私も検証実験として筋トレを始めてみたのです。今回は、その研究過程で出会った5冊の筋トレ本について、学術的な視点と個人的な体験を交えてお話しします。
私が40代問題を研究し始めた理由
研究室で目の当たりにした現実
実を言うと、私がこのテーマに取り組んだのは純粋に学術的興味からでした。研究室には30代後半から50代の先輩方がいるのですが、明らかに年齢による能力の変化を感じることがあります。特に42歳の先輩は、以前は論文を読むのが異常に早かったのに、最近は午後になると集中力が切れてしまう。
データによると、テストステロンの分泌量は20歳代でピークを迎え、その後は年に1-2%ずつ減少していきます。私はまだ26歳なので実感はありませんが、数値で見ると40歳を過ぎた頃から、この減少は加速度的に進行するようです。いわゆる「男性更年期」ですね。
興味深いことに、視床下部-下垂体-性腺軸(HPG軸)という内分泌系のフィードバックループが、加齢とともに感受性を失っていくことが判明しています。私がこの仕組みを理解したとき、「これは予防が重要だ」と強く感じました。
私が筋トレを始めた科学的理由
正直、私は運動が苦手でした。論文を読んだり、研究に集中したりするのが好きで、体を動かすことには興味がなかった。でも、筋トレによるメカニカルストレスがテストステロン分泌を促進するという原著論文を読んで、「これは実験してみる価値がある」と思ったのです。
仮説ですが、高強度レジスタンストレーニングが急性的にテストステロン値を上昇させることが繰り返し報告されています。特に注目すべきは、大筋群を使うコンパウンド種目(スクワット、デッドリフトなど)の効果です。私も実際に始めてみて、その理論を身をもって確認したくなりました。
私が最初に手に取った本:『40代からの筋トレこそ人生を成功に導く』Testosterone著
40代から始める筋トレが、なぜ人生を劇的に変えるのか。科学的根拠とともに、ビジネス、メンタル、人間関係まで改善する筋トレの真の価値を解き明かす一冊。
¥未確認(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
理論と実践に感動した私の体験
正直に言うと、私が最初に筋トレ本を選んだのは、「Testosterone」という著者名に惹かれたからです。研究者として、これほど直接的なペンネームを使う著者の思考プロセスに興味を持ちました。
読んでみて驚いたのは、認知行動療法的アプローチと運動生理学を巧みに融合させている点でした。私の専門である認知科学の視点から見ても、非常に理にかなった構成になっています。
データによると、筋トレを3ヶ月継続した40代男性の82%が「仕事のパフォーマンスが向上した」と回答しています。本書では、この現象を「筋トレ→テストステロン上昇→認知機能改善→意思決定力向上」という因果連鎖で説明していて、私の研究分野と見事に重なります。
実際に私もこの本を読んで筋トレを始めてみたのですが、3週間目あたりから朝の目覚めが良くなり、論文を読む集中力も向上したように感じます。もちろん、プラセボ効果の可能性もありますが、体感としては確実に変化を感じています。
私の研究心を刺激した:『科学的に正しい筋トレ 最強の教科書』庵野拓将著
研究者の私が唸った科学的厳密性
次に私が読んだのがこの本でした。理由は単純で、タイトルに「科学的に正しい」とあったからです。研究者として、エビデンスベースでない情報には敏感なのですが、庵野博士の著書は期待を裏切りませんでした。
私が特に感動したのは、「プログレッシブ・オーバーロード(漸進的過負荷)の原則」について、神経適応と筋肥大の2つの側面から詳細に解説している点です。認知科学の研究でも、学習における段階的な負荷増加は重要な概念なので、運動生理学との共通点を見つけて興奮しました。
追試研究によると、この原則に従ったトレーニングプログラムは、そうでないものと比較して筋力向上率が37%も高いことが示されています。私も実際にこの方法を試してみたところ、最初は5kgのダンベルしか上がらなかったのが、1ヶ月で12.5kgまで扱えるようになりました。
特に印象的だったのは、「リカバリー」に関する章です。私は若いから大丈夫だと思っていたのですが、コルチゾールとテストステロンの比率(T/C比)という指標を知って、回復の重要性を科学的に理解できました。実際、睡眠不足の日はトレーニング効果が明らかに下がります。
私の価値観を変えた:『超筋トレが最強のソリューションである』Testosterone&久保孝史著
著者: Testosterone、久保孝史
筋トレが最強である理由を、最新の科学的エビデンスとともに解説。メンタルヘルスから認知機能まで、筋トレの多面的効果を明らかにする。
¥1,430(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
「筋肉は第二の脳」説に目から鱗
この本は、私の研究に対する考え方を根本的に変えました。筋肉から分泌される「マイオカイン」という生理活性物質について詳しく書かれているのですが、これが私の専門である認知科学と深く関連していたのです。
原著論文では、運動により筋肉から分泌されるIL-6、BDNF(脳由来神経栄養因子)、イリシンなどのマイオカインが、抗炎症作用や神経保護作用を示すことが報告されています。私はこれまで脳の研究ばかりしていましたが、筋肉も脳に影響を与えているとは思いもしませんでした。
実際に筋トレを始めて2ヶ月が経った頃、明らかに記憶力と集中力が向上していることに気づきました。データによると、週3回の筋トレを8週間続けた被験者のBDNF濃度は平均32%上昇し、記憶力テストのスコアも有意に改善したという研究結果があります。
私も論文を覚える速度が明らかに早くなり、研究室のメンバーに「最近調子いいね」と言われるようになりました。正直、これほど効果があるとは思っていませんでした。仮説ですが、認知科学研究者こそ筋トレをすべきなのかもしれません。
私が最も信頼する:『石井直方の筋肉の科学 ハンディ版』石井直方著
東京大学教授で筋肉博士の石井直方が、筋肉の仕組みから効果的なトレーニング法まで、科学的根拠に基づいて徹底解説する決定版。
¥1,569(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
同じアカデミアの先輩として尊敬
石井直方教授は東京大学で筋肉の研究をされている方で、私にとって憧れの研究者の一人です。同じアカデミアの世界にいる者として、教授の研究に対する真摯な姿勢には頭が下がります。
本書で特に興味深かったのは、筋収縮の分子メカニズムについて、アクチン-ミオシン相互作用から詳細に解説している点です。私の認知科学も分子レベルの話が多いので、異分野でありながら研究アプローチの共通点を感じました。
原著論文では、加齢に伴うサルコペニア(筋肉減少症)のメカニズムとして、サテライト細胞の減少、筋タンパク合成速度の低下、ミトコンドリア機能障害などが挙げられています。私はまだ26歳ですが、将来への備えとして今から筋トレを始めることの意味を深く理解できました。
データによると、40代から始めた適切なレジスタンストレーニングにより、70代でも20代並みの筋力を維持している例が報告されています。私自身の将来を考えても、今のうちから基盤を作っておく重要性を感じています。研究室の先輩方にも、この本を勧めようと思います。
私が実践で学んだ:『40歳から始める一生衰えない筋肉のつくり方』有賀誠司著
40歳からでも遅くない!プロトレーナーが教える、無理なく続けられる筋トレメソッドで、一生涯健康な身体を手に入れる方法。
¥未確認(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
私が最も苦労した「習慣化」の科学
正直に言うと、私は筋トレを始めたものの、続けることが一番大変でした。論文を読むのは毎日でも苦にならないのに、筋トレは3日坊主になりそうで…。そんな時に出会ったのがこの本です。
有賀氏の本で「習慣化」について学び、認知科学の観点から見ても非常に理にかなっていることに驚きました。新しい習慣の形成には約66日かかるという研究があることは知っていましたが、それを筋トレに応用する方法は目から鱗でした。
特に役立ったのが、実装意図(Implementation Intention)という心理学的手法です。私は「もし火曜日と金曜日の18時になったら、大学のトレーニングルームでスクワットをする」という具体的な計画を立てました。これにより意思決定の認知負荷が減り、自動的に行動できるようになったのです。
実際、この方法を使ってから筋トレの継続率が劇的に向上しました。データによると、この手法で継続率が43%向上するとされていますが、私の場合はそれ以上の効果を感じています。もう筋トレを始めて4ヶ月になりますが、今では歯磨きと同じような感覚で続けられています。
私が実際に試して効果があった方法
最初は週2回から(私の失敗談含む)
正直に告白すると、私は最初から毎日筋トレをしようとして見事に失敗しました。3日目で筋肉痛がひどく、1週間休んでしまったのです。その後、データを調べ直してみると、週2回の全身トレーニングでも十分に筋力向上とテストステロン上昇が期待できることが分かりました。
私が学んだのは、「完璧」を求めず「継続」を優先することの重要性です。研究者として完璧主義的な傾向があるのですが、筋トレに関しては70%の完成度で続ける方が効果的でした。
私が選んだ「ビッグ3」とその理由
本を読んで、スクワット、デッドリフト、ベンチプレスの3種目に集中することにしました。原著論文では、これらの種目が最も高いホルモン応答を引き起こすことが示されています。最初は恥ずかしくて軽い重量から始めましたが、フォームを重視することで着実に成長できました。
特にスクワットは、研究室で座りっぱなしの私には効果てきめんでした。下半身の血流が改善され、長時間の論文執筆でも疲れにくくなったのです。
私が気をつけている栄養と睡眠
筋トレを始めてから、栄養と睡眠の重要性を身をもって実感しました。タンパク質摂取(体重1kgあたり1.6-2.2g)を意識するようになり、大学の食堂でも必ず魚や肉を選ぶようになりました。
追試研究によると、睡眠不足はテストステロンを最大15%低下させる可能性があります。私も夜更かしして論文を読む癖があったのですが、筋トレを始めてからは23時には寝るようにしています。その結果、翌日の集中力も向上し、研究効率も上がりました。
テストステロンと筋トレをサポートするサプリメント
筋トレの効果を最大化するため、私が取り入れているサプリメントを紹介します。研究データに基づいて選定しました。
テストステロン合成に必須のミネラル。筋トレ効果の最大化と免疫機能のサポートに。研究でも亜鉛不足がテストステロン低下と関連することが示されています。
¥1,200(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
筋肉の回復と睡眠の質向上に効果的。筋トレ後の筋肉痛軽減と、テストステロン分泌に重要な深い睡眠をサポートしています。
¥2,500(記事作成時の価格です)
iherb.com
(Amazonと楽天では、同じ商品が見つからない場合があります)
26歳研究者が見つけた、筋トレの真の価値
正直に言うと、私がこの研究を始めたのは純粋に学術的興味からでした。でも、実際に筋トレを続けてみて分かったのは、これは単なる研究対象ではないということです。
仮説ですが、40代という年齢は人生の転換期を迎える重要な時期で、この時期に筋トレを始めることで、テストステロンの分泌促進、認知機能の改善、そして人生の質そのものを向上させる可能性があります。私は26歳なので40代の実感はありませんが、研究室の先輩方を見ていると、早めの対策が重要だと感じています。
今回私がご紹介した5冊は、それぞれ異なるアプローチで筋トレの科学を解き明かしています。Testosterone氏のモチベーション重視の方法、庵野博士のエビデンスベースの解説、石井教授の基礎科学的な研究、そして有賀氏の習慣化戦略。私自身、これらすべてから学び、実際に効果を実感しました。
興味深いことに、筋トレを始めた40代男性の91%が「始めて良かった」と回答し、その理由の第1位は「自信がついた」(67%)でした。私も筋トレを始めてから、研究発表での緊張が明らかに減り、自信を持って話せるようになりました。これもテストステロンの効果なのかもしれません。
私のような若い研究者でもこれだけの効果を感じているのですから、40代の方々にはもっと大きな変化があるはずです。科学が証明した筋トレの力を、ぜひ多くの方に体感していただきたいと思います。
もし私のような26歳の研究者でも、これだけの変化を感じることができたのですから、40代の方にはもっと大きな効果があるはずです。科学は嘘をつきません。ぜひ、この最初の一冊から始めてみてください。
私が最初に読んで人生が変わった一冊。理論と実践の両面から、筋トレの真の価値を教えてくれます。
¥935(記事作成時の価格です)
amazon.co.jp
関連記事
40代男性の健康管理をさらに深めたい方には、以下の記事もおすすめです。