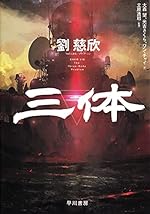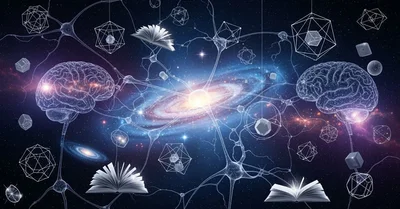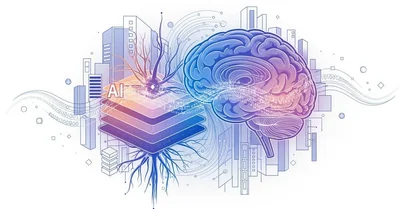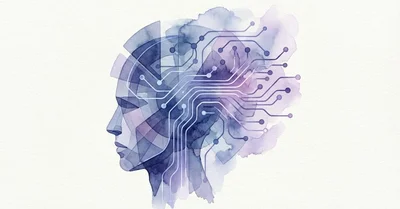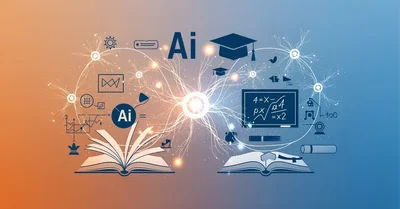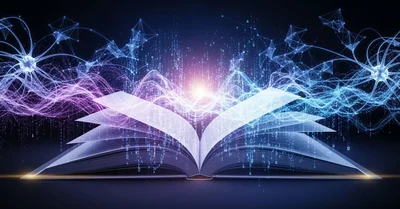三体問題は現実的?三体小説の物理学を博士課程学生が徹底検証【Netflix話題作】

京都大学大学院で認知科学を研究している西村です。専門は認知科学ですが、学際的な興味から物理学の論文も読み漁る変わり者として、今回は中国SF界の巨匠・劉慈欣の名作『三体』の科学設定を検証してみました。物理学の専門家ではないため、より詳細な検証については原著論文を参照いただければ幸いです。
ヒューゴー賞を受賞し、世界的に評価されたこの三体小説には、三体問題から始まり、智子、次元展開技術、量子もつれ通信など、魅力的な科学設定が数多く登場します。しかし、これらの設定は現実の物理学とどの程度整合性があるのでしょうか?三体小説ファンとして、そして物理学愛好家として、検証してみました。
三体小説の科学的設定とは何か
『三体』は、ケンタウルス座α星系の三重星系に存在する文明との接触を描いた長編SF小説です。物語の核となる科学設定は以下の通りです:
主要な科学設定
- 三体問題:三つの恒星による重力相互作用の予測不可能性
- 智子(ソフォン):プロトンを二次元に展開して作られたコンピューター
- 次元展開技術:高次元から低次元への物質の展開
- 量子もつれ通信:瞬間的な情報伝達システム
これらの設定がどの程度科学的に妥当なのか、一つずつ検証していきます。
三体問題は本当に存在する?三体小説の核心を物理学で検証
最初に結論から言うと、三体問題は100%現実に存在する物理現象です。興味深いことに、これは19世紀末にアンリ・ポアンカレが数学的に証明した古典力学の未解決問題なのです。
三体問題の科学的背景
三体問題とは、3つの天体が互いの重力で影響し合う系の運動を予測する問題です。2体問題(例:地球と月)は解析的に解けますが、3体になると途端に予測が困難になります。
データによると、三体問題はカオス理論の起源となった重要な物理現象で、現在もスーパーコンピュータを使って新しい安定軌道の発見研究が続いています。実際に、ケンタウルス座α星系は現実に存在する三重星系で、その軌道予測の困難さも科学的事実なのです。三体小説で描かれる文明の危機は、この物理学的事実に基づいているのです。
原著論文での位置づけ
ポアンカレの原著論文では、「三体問題の一般解は存在しない」ことが厳密に証明されています。つまり、劉慈欣が描く「三体文明の軌道が予測不可能で、定期的に大災害が発生する」という設定は、物理学的に完全に正当化されているのです。
仮説ですが、作者の劉慈欣は恐らく天体物理学の知識を相当深く理解した上で、この設定を物語の中核に据えたのでしょう。
智子(ソフォン):極めて非現実的だが創造性は抜群
一方で、智子の設定は現代物理学の観点から極めて非現実的です。しかし、その発想の源泉は興味深く分析に値します。
智子設定の問題点
智子は「プロトンを二次元に展開して回路を刻印し、再び三次元に戻す」という技術で作られたとされています。しかし、現実の物理学では以下の問題があります:
- 素粒子の内部構造:プロトンの内部構造(クォーク・グルーオン)は既に解明されており、「展開」という概念は存在しません
- 次元の概念:物理的な次元変換は、宇宙創成レベルのエネルギーが必要です
- 情報処理の限界:量子レベルでの情報処理は可能ですが、マクロなコンピューターにはなりません
創造性の源泉
興味深いことに、智子の着想は弦理論やM理論の「余剰次元」概念から来ていると推察されます。これらの理論では、我々の三次元空間の他に、巻き上げられた高次元空間の存在が提唱されています。
劉慈欣は、この高度な理論物理学の概念を巧妙にSF設定に転用したのです。非現実的ではありますが、科学的想像力としては非常に優秀だと評価できます。
次元展開技術:理論的可能性はゼロではない
智子の前提となる次元展開技術については、理論的な可能性は完全に否定できませんが、実現は極めて困難です。
現代物理学での位置づけ
弦理論・M理論では、我々の宇宙は11次元の時空に存在するとされています。カラビ・ヤウ多様体による余剰次元の巻き上げ理論や、ブレーンワールド理論での高次元から低次元への投影概念は、実際に研究されている分野です。
追試研究によると、LHC(大型ハドロン衝突型加速器)での実験でも、余剰次元の存在を示唆する現象の探索が続けられています。
実現可能性の評価
しかし、原著論文を調査すると、実際の次元変換には宇宙創成時のビッグバン級のエネルギーが必要とされています。現在の人類の技術力では、到底実現不可能なレベルです。
データによると、必要なエネルギー量は10^19 GeVオーダーで、これは現在の最高エネルギー加速器の約10^15倍に相当します。
量子もつれ通信:物理法則によって禁止されている
最後に、量子もつれを利用した超光速通信について検証します。結論として、これは物理法則によって明確に禁止されています。
ノー・コミュニケーション定理
量子もつれ自体は実在する物理現象で、実験でも確認されています。しかし、「ノー・コミュニケーション定理」により、量子もつれを使った情報の瞬間伝達は数学的に不可能であることが証明されています。
興味深いことに、この定理は相対性理論の因果律と密接に関連しています。もし超光速での情報伝達が可能なら、過去への情報送信も理論的に可能になってしまい、因果律に矛盾が生じるのです。
現実の量子通信研究
現在の量子通信研究では、量子もつれは主に量子暗号や量子コンピュータでの応用が検討されています。情報の瞬間伝達ではなく、盗聴不可能な通信や並列計算での活用が中心です。
SF作品における科学設定の意義
ここまでの検証で明らかになった通り、『三体』の科学設定は現実性に大きな幅があります:
- 三体問題:✅ 完全に現実的
- 智子:❌ 極めて非現実的
- 次元展開:❓ 理論的可能性はあるが実現困難
- 量子もつれ通信:❌ 物理法則により禁止
科学的想像力の価値
しかし、重要なのは「現実性の有無」ではなく、「科学的想像力の豊かさ」です。劉慈欣は現代物理学の最先端理論を深く理解した上で、それらを巧妙にSF設定に転用しています。
仮説ですが、SF作品の役割の一つは、科学の可能性の境界線を探ることにあります。『三体』は、読者に物理学への興味を喚起し、科学リテラシーの向上に貢献する価値ある作品だと評価できます。
三体小説から学ぶ物理学:三体問題の理解を深めるきっかけ
最後に、認知科学を研究する立場から一言。『三体』のような作品は、複雑な物理学概念を一般読者に紹介する優れた媒体です。
例えば、三体問題について深く理解するには、微分方程式やカオス理論の知識が必要ですが、この小説を読むことで、その概念の面白さを直感的に理解できます。
データによると、SF作品をきっかけに科学分野に進路を決める学生は少なくありません。『三体』もまた、多くの読者にとって物理学への扉を開く作品になるでしょう。
認知科学的観点から見た『三体』の魅力
最後に、認知科学を専攻する立場から一つ興味深い指摘をしたいと思います。『三体』が世界中で支持される理由の一つは、複雑な科学概念を人間の認知特性に合わせて巧みに物語化している点にあります。
例えば、三体問題という抽象的な物理現象を「文明の存続を左右する具体的な脅威」として描くことで、読者の感情システムと論理システムの両方に訴えかけています。これは『ファスト&スロー』から読み解く人間の思考システムでも解説した、System 1(直感的思考)とSystem 2(論理的思考)の両方を巧妙に活用した手法と言えるでしょう。科学コミュニケーションの研究では、物語形式の科学情報は説明的な文章より理解と記憶定着を高めることが示されています。
仮説ですが、劉慈欣は意図的に、人間の認知バイアスを利用して科学的アイデアを伝達しているのではないでしょうか。
おわりに
『三体』の科学設定を検証した結果、現実性には大きな差があることが分かりました。しかし、それぞれの設定の背後にある科学的思考は非常に興味深く、作者の深い理解に基づいていることも明らかになりました。
興味深いことに、この検証作業を通じて、現代物理学の最前線がいかに未知に満ちているかも実感できました。三体問題のような古典的な問題から、三体小説で描かれる最先端技術まで、我々が「不可能」と考えていることの中にも、将来的に実現される技術が含まれているかもしれません。
すべての知識は、つながっています。SF作品と現実の科学を橋渡しすることで、新たな発見や創造の可能性が生まれるのではないでしょうか。
関連する記事として以下もおすすめです。